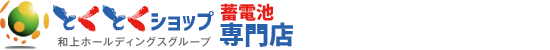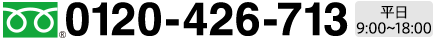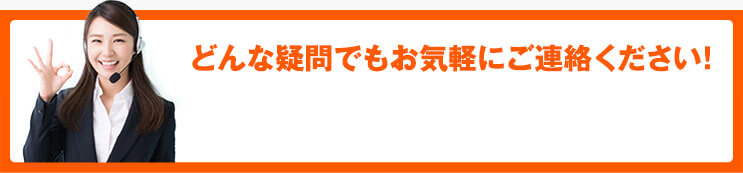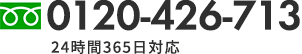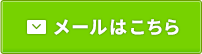蓄電池は大きければ良いと思っていませんか?
大きな容量の蓄電池をつけても電気の消費量によっては活用しきれない場合があります。
ご使用の太陽光パネル、普段の電気代や電気を良く使う時間帯などのライフスタイルや
節電のため、災害時のためなど用途に合わせた蓄電池を選びましょう。
蓄電池の種類別機能比較
【単機能タイプ】
7年未満の太陽光システムと組み合わせ、蓄電池単体もしくはエコキュート(オール電化)との組み合わせに適しています。どのメーカーでもOK!太陽光発電を追加する予定の無い方でも、単機能タイプの蓄電池の設置はおすすめです。
【創蓄連携タイプ】
10年以上太陽光発電システムとの組み合わせに適しています。太陽光発電と蓄電池両方を設置する際は、創蓄連携タイプがおすすめです。太陽光発電と蓄電池を上手く連携させることでより効率よく電気を活用できます。
リチウムイオン蓄電池
リチウム電池とは、正極にリチウム含有金属酸化物、負極にグラファイトなどの炭素材、電解液に有機電解液を用いた二次電池のことを言います。
ニッケル水素電池と比べると、エネルギー密度と充放電エネルギー効率が非常に高く、また残存容量や充電状態がかんし確認しやすいといった特長もあり、現在の蓄電池の中でも最も活発に普及や技術開発の取り組みが推進されている蓄電池と言えるでしょう。
現代に欠かせないものとなった携帯電話やノートパソコンを始めとする幅広い電子・電気機器に搭載されており、技術開発が進んだ近年においては、電気自動車などの交通機関の動力源やスマートグリッドのための蓄電装置としても研究開発が推進されています。
住宅や小規模店舗、オフィスに導入される蓄電池の多くはこのリチウムイオン蓄電池であり、リチウムイオン蓄電池を導入する方を対象とした補助金事業が設けられているケースもあります。
鉛蓄電池
鉛蓄電池とは、正極に二酸化鉛(PbO2)、負極に鉛(Pb)、電解液に希硫酸(H2SO2)を用いた二次電池のこと。二次電池の中でも最も古い歴史を持ち、開発から現在まで様々な用途で利用されています。
その用途は幅広く、自動車のバッテリーとして利用されているのを始め、非常用電源やバッテリー駆動のフォークリフト・ゴルフカートといった電動車用主電源としても用いられており、安価で使用実績が多く、信頼性に優れているという特長があります。
一方で、繰り返し充電することによって負極の金属に硫酸鉛の硬い結晶が発生しやすくなり、サイクル回数の増加に伴い性能が低下してしまうという欠点がありますが、放電しきる前に充電を行う等適切に利用することで、ある程度寿命を延ばすことが可能です。
鉛蓄電池は、極板の種類や構造によって更に細かく分類することが出来ます。
ニッケル水素蓄電池
ニッケル水素電池とは、正極にオキシ水酸化ニッケル(NiOOH)、負極に水素吸蔵合金、電解液に水酸化カリウムのアルカリ水溶液を用いた二次電池のこと。
本来は、高出力・高容量・長寿命の人工衛星用バッテリーとして開発が進められていたニッケル水素電池ですが、当時主流であったニカド電池が及ぼす環境への影響が問題視されるようになり、やがてニカド電池に変わる主流の乾電池型二次電池として普及することとなりました。
エネルギー密度が高く、過充電・過放電に強いという特長から、主にエネループをはじめとする乾電池二次電池やハイブリッドカーの動力源として用いられています。
近年では、急速充放電が出来るという強みを活かし、鉄道システムやモノレールシステムの地上蓄電設備(BPS)としても多く採用されており、平常時のピークカットや停電時の非常走行などの運用方法が可能となっています。
蓄電池ポータブル(可動式)と定置型の違い
ポータブル
ポータブル型の製品は、定置用リチウムイオン蓄電池と違い、自由に移動させることが可能で、 一般的な家庭用コンセントから充電し、本体に取り付けられたコンセントからすぐに電力を使用できるようになっています。ただし、ポータブル型はあくまで非常時に一時的に利用することを考慮して作られており、あまり蓄電容量が大きくないことから 「非常時でも家庭内の電気製品を利用したい」、「電気料金を削減したい」という方には適していません。
定置型
系統連系とは、電力会社の電力系統(電力網)に蓄電システムを接続することを指し、 これによって電力系統から直接蓄電システムに電気を貯めることが可能となっています。
系統連系型の蓄電池は基本的に屋外へ設置することになるため、ポータブル型と比較すると取り回しは非常に悪くなります。 しかし、十分な蓄電容量が確保できることや、分電盤に接続して家庭内の照明や電気製品に電力を供給できることから、 ポータブル型よりも圧倒的に優位性があると言えるでしょう。
また、ポータブル型と大きく異なる点として、非常に高いレベルでシステムが制御されていることが挙げられます。 電力使用量や太陽光発電システムの発電量に応じて、蓄電池からの放電量を調整することや、 停電時には自動で蓄電池から放電を行うといった制御が実装されています。