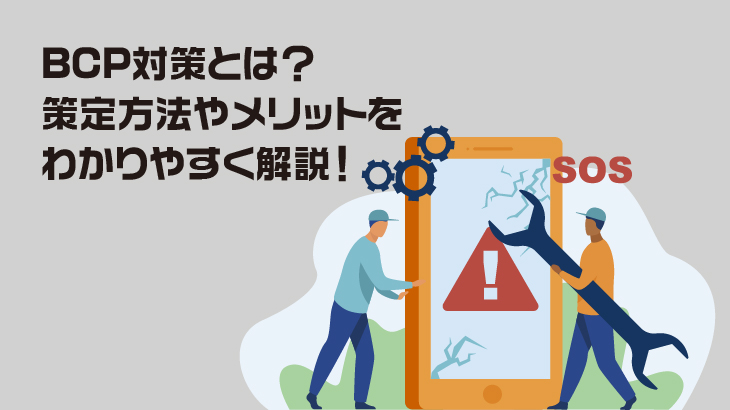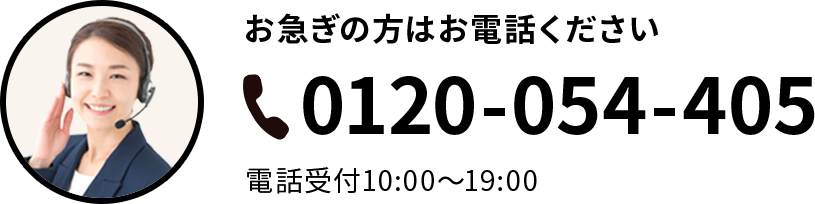BCP対策とは、災害や大きな事故などが生じても早期に事業を復旧し、継続するための対策や計画のことです。地震や台風、感染症などは突然発生するため、平時に体制を整える必要があります。
今回はBCP対策とは何か、策定のポイントや対策を始めるメリット、注意点についてわかりやすく詳しくご紹介します。BCP対策の基礎からあらためて確認したい方はぜひ参考にしてみてください。
BCP対策とは

BCP対策(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、非常時における被害の最小化や、事業の早期復旧に向けた対策全般を指します。
たとえば、災害をはじめとする緊急事態において、自社の損害を最小限に抑えるための対策、事業を早期復旧するための訓練や対策などがBCP対策に当たります。日本では自然災害のイメージが強いですが、感染症やテロ、事故など想定される「緊急事態」は多岐にわたります。
BCP対策が必要とされる理由

企業にとってBCP対策は、自社の従業員や資産、事業そのものを守るために必要です。介護系の業態では、義務化もされています。
BCPを策定しないまま事業を継続しようとすると、緊急事態の際に適切な避難や行動をとれず、被害を拡大させてしまう可能性もあります。被害が拡大すれば、事業の復旧に支障をきたし、事業停止の長期化や廃業のリスクも考えられます。
BCP対策を行っておけば、従業員や資産を守れるだけでなく、市場からの信頼にもつながるでしょう。
BCMや防災との違い
BCP対策と似た概念に、BCMや防災があります。続いては、BCMや防災との主な違いをわかりやすく解説します。
BCMは運用管理に関する用語
BCM(Business Continuity Management:事業継続マネジメント)は、BCPで策定した計画の運用・管理にかかわる専門用語です。つまり、BCMはBCPの一部といえます。
BCP対策で計画や訓練内容を策定しただけでは、実行可能かどうかわかりません。机上の空論とならないよう、訓練を実施したり準備を行ったりしながら、計画の妥当性を検討し、少しずつ自社の体制を整えていく「マネジメント」のことをBCMといいます。
防災は災害の被害を抑える対策
防災は、災害が発生した際の被害を小さくするための対策のことです。一方、BCPには事業の復旧や継続も含まれているため、目的や対応範囲に違いがあります。
防災で想定される事象は、地震や台風・噴火といった災害にかぎられています。BCP対策の場合は、災害だけでなくテロや感染症など、事業に損害を与える可能性のあるあらゆる事象が想定されているのも大きな違いです。
また一般的には防災に関連した部署が「防災」を取り組むのに対し、BCP対策は経営陣を含めた全部門で取り組みます。
BCP対策の策定方法

ここからは、BCP対策の策定方法や流れについてわかりやすく解説します。
BCP対策の方針を決める
まずはBCP対策の方針を策定します。事業の継続が第一目的ではありますが、ライフラインを支える事業や人の命を預かる事業などでは、最低限の事業継続や人命にかかわる設備保護が優先となることもあります。利益の確保だけが第一方針とならないこともあるので、自社に合わせて方針を決めましょう。
体制を構築する
BCPの基本方針や対策の範囲などを決めたら、BCP対策を実施するための社内体制を構築していきましょう。
プロジェクトチーム(BCP事務局)のメンバーや責任者を選定し、各部門のBCP対策チームを構築します。取引先や関連会社などと連携がとれるよう、連絡体制の構築や情報共有に関するルールづくりなども重要です。
復旧の優先順位を決める
事業にどの程度インパクトがあるのか、復旧が困難となった場合にどのようなリスクがあるのか分析し、優先順位を決めます。前者を「事業影響度分析」、後者を「リスク分析」と呼びます。
事業影響度分析は、資金繰り、従業員の雇用、自社の利益やマーケットシェアなどさまざまな点から、優先順位を評価します。被害発生からどの程度の時間で復旧させるのか(目標復旧時間)、平時のレベルを基準としてどの程度の水準まで復旧させるべきか(目標復旧レベル)を決めていきましょう。優先度に応じて復旧・継続に必要な資源や要素を確認し、確保できるかどうか、使えない場合の代替手段などを計画しましょう。
リスク分析では、地震や津波、台風などの災害、感染症、テロといった非常事態やリスクにどのようなものが想定されるか確認します。たとえば落雷による停電でシステムが落ちる、サイバー攻撃を受けるといったリスクも想定すべきです。被害の詳細、復旧までにどれだけの時間やコストがかかるのか、資源はどうなるのかなど、事業影響度と合わせて調査が必要です。
復旧時間や手順を設定する
実際に復旧したり、非常時に一部の事業を継続させたりするまで、どの程度の時間が必要か、どの程度の時間で復旧しなければならないか検討しましょう。長引けば長引くほど、事業への影響も大きくなります。自社の財源等を考慮し、許容できる時間として目標の復旧時間を設定してください。
復旧や事業継続に必要な人員や資源、代替拠点の確保などを詳細に決め、非常時も迷わず動くことができるよう具体的な手段や手順を策定します。
発動基準や体制・要因を定める
BCPをどのタイミングで発動させるのか、各チームの体制や役割などを明確に定めておきましょう。
被害発生から速やかに事業を復旧させるためには、迅速かつ適切なタイミングでBCPを発動させる必要があります。発動基準を決める際は、あらゆる被害を想定し、それぞれに対して誰が見てもわかるよう客観的で具体性のあるものにしましょう。
例)NG:地震が起きたら発動する / OK:震度6以上の地震が起きたら発動する
また各部門の責任者や関係者、指揮命令系統を明確にしておくことも大切です。情報共有や復旧がスムーズになります。また万が一の死傷者の発生に備えて、BCPの権限を別の担当者へ変更させる流れを取り決めたり、代行者を定めたりする必要もあります。
社内にBCP対策の情報を共有する
策定したBCPは社内や関連会社などへ共有してください。訓練を繰り返して課題や改善点を探し、BCP対策を強化して実現性のあるものにしていきましょう。また予備資源の確保などの準備も大切です。
BCPの準備例:
代替拠点の確保や非常時のマニュアル作成、早期復旧や事業継続に必要な機材や備品の調達、ライフラインの確保、データや重要書類のバックアップなど
BCP対策へ取り組むメリット

続いては、BCP対策へ取り組む主なメリットをわかりやすく解説します。
早期の復旧や業務の継続を行えるようになる
事業の早期復旧や業務の継続能力を向上させられるのが、BCP対策へ取り組む大きなメリットです。
感染症の流行による事業の縮小や自粛、災害などが発生したとき、スムーズに対応できなければ復旧が大幅に遅れたり、事業を停止しなければならなくなったりします。緊急事態における被害を最小限に抑え、スピーディに復旧して事業を再開するには、社内体制の構築、リソース確保、訓練と改善が重要です。
社員の命や自社の資産を守ることにつながる
BCP対策は社員や顧客の命、自社の事業資産を守ることにつながります。非常時の体制構築だけなく、地震・台風・津波といった災害やテロ、感染症などによる被害や影響を詳細に分析・調査するため、具体的な被害や損害を想定することが可能です。
このような評価分析は、人命を救うために何が必要なのか、どのような対策を行えば損害を抑えられるのかといった点を考える上で役立ちます。
自社の体制強化や弱点の発見につながる
自社の弱点やリスクも見つけられるのが、BCP対策へ取り組むメリットのひとつです。
通常業務において、災害などのリスクについて考える機会は少ないです。BCPの策定にあたって組織の体制を見直したり、資源を見直したりすることは、自社の体制の脆弱性を見つける機会にもなります。
取引先からの信頼性を向上させられる
BCP対策は、取引先などからの信頼性や評価向上にもつながります。事業の停止や復旧の大幅な遅れは、取引先にとっても大きな損害となりかねません。BCP対策の策定や運用管理によって被害を最小限に抑えることができれば、自社の信頼性や評価も高まるでしょう。
BCP対策の策定に関するポイント
BCP対策を進めていく際は、内閣府から提供されているガイドラインに沿うとスムーズです。内閣府などで提示されているガイドラインには、前半で紹介した対策の流れや細かなポイントが記載されています。
また、他社の事例を参考にすることで、BCP対策とはどのようなものなのかイメージしやすいでしょう。
また繰り返しになりますが、BCP対策を進めていく際は自社の重要な業務、中核事業を明確に決めておくことが大切です。緊急事態の際にすべての業務や資産を守ることは難しいため、とくに重要なものがどれなのか、区分しておきましょう。
BCP対策の具体例
トヨタL&F(ロジスティクス&フォークリフト)福島では、同地域の過去の水害事例から地盤のかさ上げ工事を行い、防水壁の設置などさまざまな対策を施しました。
2019年10月に発生した台風により、河川の氾濫や決壊が起きたことで同社も大きな被害に遭ってしまいます。しかしスピーディな経営判断で現在地での復旧・事業継続を決め、普及後はかさ上げ工事や防水壁の強化およびBCP対策の改善を行っています
このようにBCP対策が完全でないケースは珍しくありません。計画策定しただけで終わらず、繰り返し改善を図ることが重要です。
BCP対策で重要な電源設備!太陽光発電がおすすめの理由

BCP対策の一環として、太陽光発電の導入を検討する企業も増えています。最後は、BCP対策にも役立つ太陽光発電の強みをわかりやすく解説します。
燃料の調達コストを抑えられる
燃料の調達コストを抑えられる点が、太陽光発電の大きな強みといえます。
BCP対策における電力の確保は、ガス・ガソリン式の非常用電源も多いです。しかしこのような非常用電源は、あらかじめ燃料を調達しておく必要があり、コストや保管場所など維持管理の負担は少なくありません。
太陽光発電の場合は光を電気へ変換させるため、燃料の調達が不要なため負担が減ります。それほど大きな動力を必要としない場合など、自社の状況によっては太陽光発電の導入で十分なこともあるでしょう。
長期停電時でも電力を供給できる
太陽光発電を導入しておけば、長期にわたる停電が起きたときでも継続的に電力を確保することが可能です。
東日本大震災のような大規模災害が発生してしまうと、ライフラインも大きな損害を受けます。被害状況によっては1日や2日で復旧しない場合もあるため、長期停電を想定した対策が必要です。
太陽光発電は、晴れの日や曇り・雨の日でも発電を継続できるため、ガソリン式などの非常用電源と異なり長期停電に強い設備といえます。産業用蓄電池を併用すれば日中に発電した電気を貯めておき、夕方や夜間・早朝に電気を使用することも可能です。
平時でも電気料金削減効果などメリットがある
太陽光発電は、平時でも電気料金削減効果などさまざまなメリットを得られます。
発電した電気は、自社のオフィスや工場、倉庫などで消費することが可能です。電力会社から供給されている電力購入量(買電量)を削減し、電気料金を抑えることもできるでしょう。売電すれば収益源を増やすことも可能です。
また太陽光発電は発電時にCO2を排出しないため、脱炭素経営を目指す上でも役立つ再生可能エネルギー設備です。
BCP対策とは緊急事態に対応するための計画や体制づくり!
BCP対策とは、地震などの非常事態に備え、自社の早期復旧・事業継続のための計画などを策定する取り組みのことです。
BCP対策に向けて電源設備の導入を考え始めた方や、BCP対策のために再生可能エネルギーが活用できるかどうか気になる方などは、今回の記事を参考にしながら太陽光発電を検討してみてはいかがでしょうか。
15,000以上の実績を持つとくとくファーム0では、非FIT型太陽光発電(FIT認定を受けない太陽光発電)に関するご提案から、案件紹介、設計・施工・保守管理などを一括で行っております。さまざまなプランをご提案しており、状況に合わせた運用を検討いただけます。
無料の個別セミナーでは、脱炭素経営の基礎、太陽光発電事業の内容を丁寧にご説明しております。疑問点や不明点などはその場でご質問いただくことも可能です。少しでも気になった方は、お電話やメール、個別セミナーよりお気軽にご相談ください。