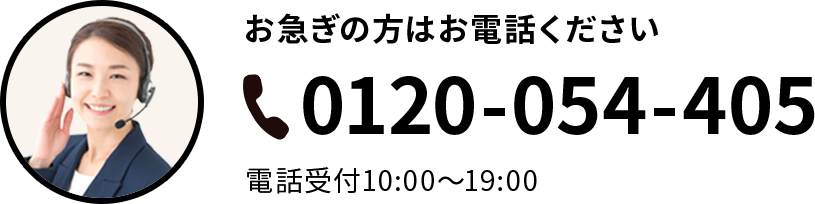経済産業省は、第7次エネルギー基本計画の原案を公表しました。脱炭素経営や再生エネルギーにかかわる重要な情報が多く含まれるため、基本的な内容は押さえておきたいところです。今回は、第7次エネルギー基本計画の原案で示された内容や、今後考えられる展開についてわかりやすくご紹介します。脱炭素経営のために国の政策を調べている方、脱炭素経営をどのように進めていくべきか悩んでいる方などは参考にしてみてください。
エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立する方針

経済産業省の「エネルギー基本計画(原案)の概要」では、エネルギー政策の基本方針として「S+3E」原則を維持するという方針が示されています。
S+3Eとは、エネルギーの安全性と安定供給、経済効率性、環境適合性のことです。つまり、国民の生活に大きく影響を与えるエネルギー(電気やガスなど)を安定的に供給できるよう保ち、そのうえで環境配慮も欠かさない方針であるということです。
たとえばカーボンニュートラル2050(2050年までに温室効果ガス実質0を目指す目標)を実現するために、CO2排出量をさらに削減していく方針や、エネルギー自給率向上に向けたエネルギー安全保障の強化なども盛り込まれています。
第6次エネルギー基本計画との主な違いは、エネルギー安全保障の確保に関する強化方針も示されている点です。2022年のウクライナ侵攻、2023年からの中東情勢緊迫化などでエネルギーの確保が不安定になったことなども背景にあります。
なお、今回解説している「第7次エネルギー基本計画」は原案のため、今後変更される可能性がある点も考慮して参考にしてください。
出典:「エネルギー基本計画(原案)の概要」(資源エネルギー庁)
エネルギー安全保障を確保するための戦略

第7次エネルギー基本計画の原案では、エネルギー安全保障の確保に向けて次のような戦略が示されています。
- 国際協力
- バランスの取れた電源構成の構築
- 化石資源の確保と安定供給
など
日本は化石燃料を自国で調達することが難しいため、国際協調や協力を通じて安定的なエネルギーの確保を目指していくということです。しかし当然ながら外部からの供給に依存するばかりではエネルギー供給が安定しないため、エネルギー自給率の向上も目標に入っています。2023年度の電源構成はエネルギー自給率15.2%で、大きな課題があるといえるでしょう。
第7次エネルギー基本計画の原案では、2040年までにエネルギー自給率3~4割程度へ引き上げて、火力発電の割合を3~4割程度へ抑える目標が示されています。2023年度時点で再生可能エネルギーの割合は22.9%ですが、2040年までに4~5割程度へ引き上げる方針です。このため次の見出しで説明するとおり、再生可能エネルギーの割合を向上させるための取り組みが増えていくことが予想されます。
ほかにも、化石資源の安定的な供給に向けて、危機管理やサプライチェーンの強化、供給減の多角化、資源外交などさまざまな方法を用いた対策が検討されています。
出典:「エネルギー基本計画(原案)の概要」(資源エネルギー庁)
脱炭素化に向けたエネルギー戦略

続いては、脱炭素化に向けたエネルギー戦略をわかりやすく解説していきます。
再生可能エネルギーの主力電源化を目指す
第7次エネルギー基本計画の原案では、再生可能エネルギーを主力電源とするためのさまざまな方針、その実現方法についても記載されています。再生可能エネルギーを導入する企業にとってはとくに注目したい内容でしょう。たとえば次のような目標が言及されています。
- 国民負担を抑えて再生可能エネルギー設備の導入量を増やす
- 事業環境の整備を進める
- 技術面の強化
など
太陽光発電をはじめ、EEZなどでの浮体式洋上風力発電、地熱発電、中水力発電などの導入拡大が目標とされています。また次世代型再生可能エネルギーの技術開発も行われる予定です。再生可能エネルギーの導入といっても1種類に依存するのではなく、さまざまな設備をバランスよく活用できるようにする方針であり、幅広い支援が整備される可能性が高いでしょう。
出典:「エネルギー基本計画(原案)の概要」(資源エネルギー庁)
電力システム改革
電力システムの脱炭素化や安定供給を実現するための改定案が検討されています。現在では、電力広域融通や電力小売自由化による価格の抑制、事業機会の創出などの取り組みがありますが、DXやGXによる電力需要の増加や燃料価格高騰による電気料金高騰といった点が課題となっています(※DX:デジタル技術を取り入れて企業の成長などを図る、GX:クリーンエネルギーを中心とした社会を目指す取り組み)。
第7次エネルギー基本計画では、こうした課題を解決するため次のような取り組みの実施案が出ています。
- 大規模な電力需要などに備えた電力ネットワークの構築
- 脱炭素電源の確保に向けた市場・事業規模・資金調達環境の整備
- 安定的な電力供給に向けた制度の整備
など
経済合理的な取り組み・支援の導入を検討
第7次エネルギー基本計画には、経済合理的な取り組みや支援の導入に関する案もあります。
カーボンニュートラル達成には、省エネだけでなく積極的な電化(EVなど)や非化石(化石燃料不使用、少ないエネルギー設備)への転換も重要とされています。しかし、単に電化・非化石への転換を実施すればよいというわけではありません。再生可能エネルギーなど新たな技術の中には、CO2の削減量がそれほど大きくなかったり、生産コストが高かったりして実用的ではない方法もあります。どれほどCO2を削減できるのか、経済合理性はあるのかといった視点からも取り組む必要があるのです。
そこで提案されているのが、次の内容です。
- 製造プロセスの抜本的な転換(半導体の省エネ性能向上や最先端技術の活用など)
- 省エネ関連制度の見直し
など
官民一体となって取り組む姿勢が強調されており、民間企業が参入できるような支援も期待されます。
次世代エネルギー・CCUS・CDRなどの開発
水素などの次世代エネルギーは、さまざまな分野での活用が期待されているほか、カーボンニュートラルにおいても重要な役割を果たします。CCUSは、二酸化炭素の回収と利用、貯留に関する技術で、エネルギーの安定供給や経済の成長、さらに脱炭素などにおいても欠かせません。CDRは二酸化炭素を除去するもので、CCUSと同様に脱炭素において欠かせない技術のひとつです。
こうした次世代エネルギーを活用・生産する企業の設備投資を促す政策、バイオ燃料の導入などを推進していくことが期待されます。原案では環境整備、市場の創出など、さまざまな取り組みが検討されています。
その他方針
ここでは大きく取り上げませんが、第7次エネルギー基本計画の原案には、脱炭素やエネルギーの安定供給以外の方針も示されています。
たとえば、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故に関係する諸課題について、処理水、福島県の復興・再生にかかわる取り組み方針などにも言及されています。またエネルギー安全保障の確保に向けた国際協調や協力に関する方針では、火力発電に頼っている東南アジア地域の国に対して、AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体:アジア11カ国のカーボンニュートラルに向けた枠組み)の枠組みを通じた脱炭素化のサポートや貢献を行っていくなどと示されています。
太陽光発電にかかわる検討事項

第7次エネルギー基本計画の原案では、太陽光発電に関する検討事項や提案なども細かく記載されています。太陽光発電事業にかかわる企業にとっては、やはり見逃せないポイントです。ここからは、太陽光発電にかかわる検討事項を解説します。
FIT・FIP制度の活用推進・関連ルール見直し
FITやFIP制度の活用推進やルールの見直しなどが検討されています。主に次の3つの視点によるものです。
- 太陽光発電の導入をさらに促すこと
- 現在ある太陽光発電設備の稼働効率を上げること
- 発電コストを改善すること
FIT・FIP制度における屋根設置型太陽光発電に関しては、導入を推進していくために調達期間や交付期間の見直しも検討されています。一方、地上設置型太陽光発電については、FIT・FIP制度を前提としない事業モデルの推進も検討されており、非FIT型を検討している企業を後押しするような支援も期待されます。
現状では送電線の不足・供給過多により出力制御が生じる時間帯もあります。太陽光発電設備などの導入が増加しても、ロスが生じないよう、連系線の整備、出力制御の順番見直し、発電予測や蓄電池の活用に関する支援強化などが予定されています。
またFIT・FIP制度によって導入された太陽光発電については、適用期間終了後も運用されるよう事業者に再投資やリパワリングなどを促していく方針です。現在国内における再生可能エネルギーの発電コストは、海外と比較して高くなってしまっているため、FIT・FIP制度において入札制の活用を推進していく方向です。
ペロブスカイト太陽電池の早期社会実装
太陽光発電のさらなる導入拡大を目指して、ペロブスカイト太陽電池の早期社会実装が検討されています。ペロブスカイト太陽電池は、従来の太陽電池よりも軽量で、柔軟性が高いため、耐荷重性の低い建築物などにも設置しやすいとして注目されています。
そこで政府は、耐荷重性の低い建築物へのペロブスカイト太陽電池を推進していくほか、強靭な生産体制の確立を座主方針です。2040年に約20GWの容量を目標としています。
ペロブスカイト太陽電池を含む次世代型太陽電池は、宇宙太陽光発電システム(SSPS)の研究開発・実証なども進められる予定で、技術開発に積極的な姿勢が見られます。
工場・オフィスにおけるZEB・自家消費などの普及拡大
工場やオフィスにおいては、ZEBや自家消費かつ屋根設置型太陽光発電の普及拡大に向けた取り組みも検討されています。(※ZEB:建物で消費されるエネルギーの収支を実質0にすることを目指したもの)
とくに製造業を中心に省エネや製造プロセスの転換が必要とされており、再生可能エネルギーを活用するなどしてエネルギー面での脱炭素化を支援することが期待されます。
オフィスを含む民間の部門に脱炭素化については、自家消費型太陽光発電やZEBの普及拡大、省エネ法に沿った定期報告制度の活用など、現状の取り組みをそのまま推進していく方針です。
荒廃農地への導入拡大
営農が見込まれない荒廃農地問題の解決策の一つとして、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの導入拡大を進めていく方針です。農地で設置可能なソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は、今後も導入拡大を前提として推進されていく見込みです。
義務的リサイクル制度の導入・構築
2022年7月に施行された廃棄等費⽤積⽴制度に関しては、今後も引き続き運用されていく予定です。
太陽光パネルは2030年代後半から廃棄量が増えるとされています。廃棄問題に対しては、義務的リサイクル制度を含む新しい制度によってリユース・リサイクル・廃棄処理を進めていく方針です。現時点で太陽光発電を導入している企業は、廃棄処理に関する対策や新制度の情報を集めておきましょう。
DXとセキュリティ対策の推進
第7次エネルギー基本計画の原案では、電気事業者自身による脱炭素化や非化石価値の活用のほか、DXの推進などによる収益性や成長性の向上が求められています。
需給管理を進めていくにあたって、すべての需要家に第二世代スマートメーターシステムが導入されることが検討されています。一方でこのようなデジタル技術を活用したエネルギーの管理には、サイバーセキュリティ対策も必要です。このため国は、サプライチェーン対策や、小型太陽光発電を含む分散型エネルギーのセキュリティ対策を進めていく方針です。
第7次エネルギー基本計画でも太陽光発電の導入量増加が示されている
第7次エネルギー基本計画には、エネルギー安全保障の確保に向けた新たな方針のほか、カーボンニュートラル達成に向けた脱炭素電源の主力化、省エネ・非化石への転換、太陽光発電の導入量増加に関する方針が示されています。
今後も再生可能エネルギーの導入・活用支援は続く見込みで、太陽光発電事業にかかわるすべての企業が注目していきたい情報です。
脱炭素経営のために再生可能エネルギーを検討している方や太陽光発電の運用について関心を持っている方は、今回の記事を参考にしながらとくとくファーム0で導入を検討してみてはいかがでしょうか。
とくとくファーム0は、再生可能エネルギーを求めている需要家様と土地のオーナー様をつなぐサポートを行っております。また、太陽光発電を求めている企業様には、非FIT型太陽光発電物件のご紹介から提案、機器の調達、施工、保守管理まで一括サポートも可能です。
個別セミナーを無料で行っているため、こうした支援制度などの最新情報も簡単にキャッチアップできます。少しでも気になった方は、お電話やメール、予約フォームよりお気軽にご相談ください。