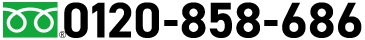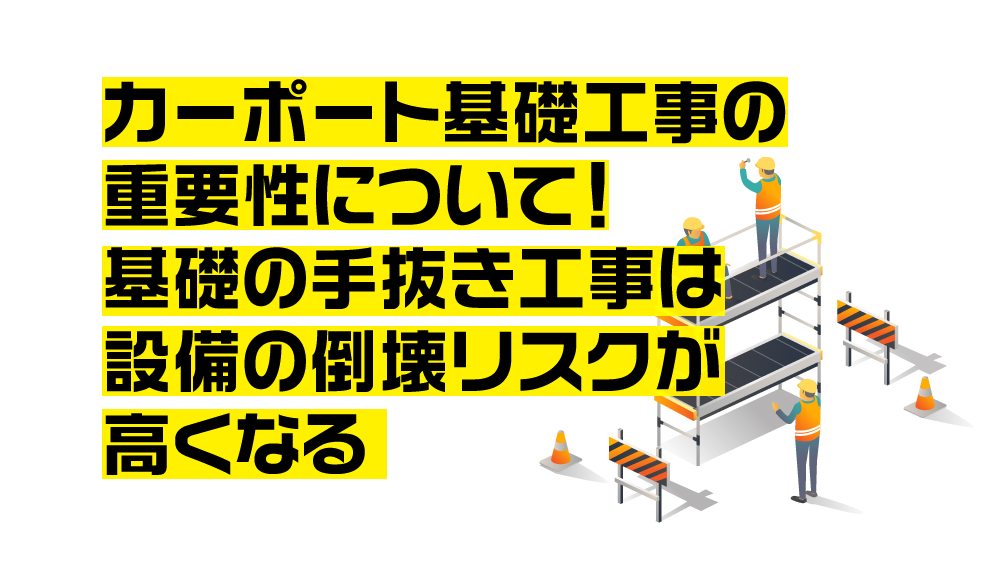2025.02.19
旗竿地にカーポートを設置することはできる?旗竿地の駐車場に関する注意点もご紹介
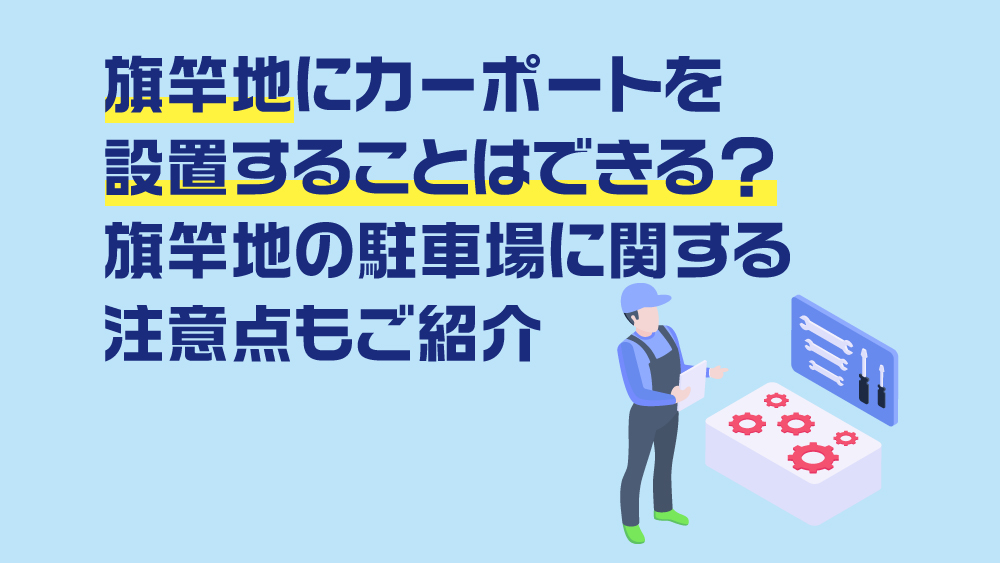
こんにちは、『ソーラーカーポート専門店 とくとくショップ』です。今回は、旗竿地に建設する住宅において、駐車場にカーポートを設置したいと考えた時の注意点を解説していきたいと思います。
一般の方の中には、「旗竿地(はたざおち)」と聞いても、これが何を意味するのか分からないという方も多いと思います。旗竿地は、住宅業界にて土地の形状を表すために用いられる専門用語で、道路に接した細い通路を通った先に家を建てるための敷地が存在するという土地のことを指しています。旗竿地と呼ばれているのは、土地の形状が「竿がついた旗の形状」に似ていることから、この名称で呼ばれるようになったとされます。
旗竿地は、正方形や長方形のように、形が整った整形地と比較すると、土地価格が安く設定される傾向にある点が魅力なのですが、実際にそこに家を建てることを考えると、さまざまな問題が生じやすいとされています。特に、旗竿地は「竿」の部分を駐車場にするケースが多いのですが、ここにカーポートを設置した場合、隣人との近隣トラブルに発展するリスクが高くなるとされているのです。
そこでこの記事では、旗竿地に家を建てる際のメリット・デメリットや、旗竿地にカーポートを設置した場合に苦情につながりやすい理由、また隣家に配慮するため旗竿地に適したカーポートの形状などについて解説したいと思います。
目次
旗竿地とは?旗竿地に家を建てるメリット・デメリット
冒頭でご紹介したように、旗竿地は「竿がついた旗のような形状の土地」のことを言います。都市部など、住宅が密集しやすいエリアでは、特殊な形状の宅地が多く出てくるのですが、その中でも、公道に接した細い通路(最低2m以上の幅員が必要)を通って奥に広い宅地が存在する形状の土地が旗竿地と呼ばれます。
一般的に、住宅を建てるための宅地は、正方形や長方形といった整形地に整えられるというイメージが強いのですが、相続などで複数の所有者が共有していた土地を分割する際に、旗竿地のような不整形地が生まれてしまうとされています。
ちなみに、建築基準法では、公道に接する敷地の幅員が2メートル以上なければ宅地として建物を建てられない決まりとなっているため、上述のように通路の幅は最低2m以上の幅員が必要とされます。
旗竿地のメリット
旗竿地のメリットは、整形地と比較した場合、土地を安く購入することができる点です。旗竿地は、宅地まで行くには細い通路を通らなければならないなど、公道からのアクセスが悪い点や特殊な形状なので扱いが難しい、宅地の周囲が全て隣地に囲まれるなどといった理由から、整形地よりも不人気とされているのです。土地の価格は、需要が大きく関係するため、整形地と比較すると地価水準が低くなるわけです。
なお、旗竿地に家を建てる場合のメリットについては、安く土地を購入できる以外にもあります。例えば、家そのものが公道からある程度離れた位置に建てられるため、交通騒音に悩まされにくく、静かで快適な住環境を作りやすくなるのです。また、通行人の視線を気にしなくても良くなるため、大きな窓を設置することができるなど、プライバシー性の高さもメリットの一つと言えます。
この他、竿の部分は駐車場や駐輪場、子供を遊ばせるためのスペースなどとして活用することも出来るなど、整形地にはない特殊なスペースを確保できる点を住んでからメリットに感じるという方も多いようです。
旗竿地のデメリット
旗竿地の土地価格が安いのは、整形地と比較すると不人気だからです。それでは、旗竿地の人気が低いのはなぜなのでしょうか?実は、旗竿地に家を建てる場合、決して見落とすことができない多くのデメリットが存在するのです。
メリット面では、公道から距離が離れるため交通騒音の被害が少ないと紹介しました。しかし、旗竿地に建てる家は、周囲全てを隣家に囲まれてしまうことになるため、交通騒音が届きにくいだけでなく、採光や通風も遮られてしまう可能性があるのです。さらに、隣家に騒音をだす住人がいれば、「旗竿地は静か!」というメリットまで打ち消されてしまいます。宅地の採光、通風が悪い場合、湿気がこもりやすくなりカビの繁殖を招いて、建物が早期劣化してしまうリスクが高くなります。また、屋根に太陽光発電などを設置しても、周囲の家に日射を遮られる場合、思うような発電量を確保することが難しくなります。
この他、旗竿地に建てる家は、奥まった位置に建物が存在するため、空き巣などの侵入犯罪のターゲットになりやすくなります。窓破りなどの手法で侵入する場合でも、犯行を通行人に見られるリスクが低くなりますし、窓を割る音なども外に聞こえにくくなります。したがって、旗竿地に建てる家は、空き巣などの被害を防ぐためにも、防犯ガラスやカメラシステム、警備会社との契約など、設備面にコストをかけなければならなくなるケースが多いのです。旗竿地の家は、土地は安く購入できるものの、建物は付属設備にコストがかかりやすいため、総合的に考えると家の建築費用はそこまで安くなりません。それどころか、奥まった場所に宅地があるので、建材を運ぶ手間がかかる、重機が入れないため全て人力での作業になるなど、家を建てるための建築コストが割高になり、整形地に家を建てるよりも高くなる…なんてこともあるようです。
旗竿地に駐車場を作る方法について

旗竿地に建てる家について、駐車場を作るための方法は大きく分けて二つ存在します。
一つ目の方法は、旗竿地の通路部分ではなく、奥の宅地スペース(旗の部分)まで車を乗り入れ、駐車するという方法です。そしてもう一つは、公道に接する細長い通路部分(竿の部分)を駐車場にするという方法ですね。どちらの方法でも、駐車場を作るだけのスペースを確保できるのであれば、問題なく車を停めることができるでしょう。
まず、奥の敷地に駐車場を作るパターンでは、大きな土地が必要になることに注意が必要です。また、細い通路から車を侵入させるため、方向転換などが難しくならないように、家そのものの向きを工夫しなければならないなど、家づくりに制限が生じてしまう可能性がある点も注意が必要です。ただ、一般的な旗竿地は、奥の敷地部分が大きいパターンがあまり見られないため、この方法で駐車場を用意するケースは少ないと思います。
一般的には、旗竿地の「竿」の部分を駐車場にするケースが多いのですが、この場合は、間口の幅員の広さが限られていることに加え、複数台の車を所有している場合は縦列駐車になり、車の出し入れが面倒に感じる可能性があるので注意しましょう。また、竿の部分を駐車場にして、そこにカーポートなどの構造物を設置する場合、隣家にさまざまな影響を与える可能性があり、場合によっては駐車場が原因となり隣人トラブルに発展することもあるようです。旗竿地にカーポートを設置する場合の注意点については後述します。
旗竿地に駐車場を作るための工夫について
旗竿地に家を建てる方で、駐車場スペースも用意したいと考えているのであれば、土地探しの段階からいくつかの注意点が存在します。ここでは、旗竿地に駐車場を作るための工夫についても簡単にご紹介します。
- 3メートル以上の間口が確保できるようにする
先程ご紹介したように、旗竿地の竿部分は公道と接する間口が最低2m以上という決まりがあります。しかし、竿部分の幅員が2mギリギリしかない場合、駐車場を作るのが難しくなるのです。通路の幅員が2mの場合、軽自動車が通るのがやっとといったスペースしかありません。この場合、車を停めていると人の通行も難しくなりますし、駐車場を作ったことを後悔する結果になるかもしれません。旗竿地で竿部分を駐車場にする場合、最低でも3mの路地幅が確保できる土地を探しましょう。可能であれば、3.3m程度あるのが望ましいです。 - 並列駐車が希望なら特殊な形状の旗竿地を探す
旗竿地の竿部分を駐車場にして、2台以上の車を駐車したいなら、縦列駐車が基本となります。ただ、この場合、車の出し入れが面倒になるため、可能なら並列で駐車できるようにしたい…と考えるものです。実は、旗竿地でも、公道と接する部分だけが広くて、通路が狭くなっているという特殊な形状をした土地も存在します。したがって、どうしても並列駐車が希望という場合は、そのような旗竿地を探しましょう。なお、並列駐車が可能な旗竿地を探すのは、なかなか難しいので、「絶対に並列駐車が譲れない」という方は素直に整形地を購入しましょう。 - 自転車や人の通行も考慮する
旗竿地に作る駐車場について、よくある失敗が人や自転車の通行を考慮できていないというパターンです。分かりやすく言うと、車を停めると自転車が通れなくなる、自転車が車に当たって傷が付く…なんて状態の駐車場が意外に多いのです。旗竿地は、竿部分が駐車場として最適のように感じますが、そこは人の通路としても利用されるということを忘れないようにしましょう。ここを考慮しておかなければ、駐車できる車の種類に制限が生じてしまう可能性もあります。
旗竿地にカーポートは設置できる?
ここまでの解説で、旗竿地がどのような形状の土地で、そこに駐車場を作ることができるのかがわかっていただけたと思います。上述のように、旗竿地は竿がついた旗の形状に似ていることから、この名前で呼ばれていて、駐車場は「竿」の部分に用意されるケースが多いです。
それでは、竿の部分に駐車場を作る場合、カーポートの設置も可能なのでしょうか?細長い通路を駐車場にするわけなので、雨などの悪天候時に濡れないようにするためにも、カーポートを設置したいと考える方が多いです。
ここでは、旗竿地にカーポートの設置が可能なのか、またどのようなカーポートを設置すれば良いのかについてご紹介します。
旗竿地にもカーポートは設置できる
結論から言ってしまいますが、旗竿地でもカーポートの設置は問題なく可能です。もちろん、通路の幅によってはカーポートなどを設置することが難しい場合もありますが、そのような狭い通路の場合、そもそも駐車場利用が難しいと言えるでしょう。
旗竿地は、公道と接する通路の幅が最低2m以上必要と紹介しました。ただ、竿部分を駐車場として利用する場合、車を駐車しても自転車や人の通行を妨げないレベルの幅を確保するケースがほとんどです。この場合、最低でも3m程度の幅を確保していると想像できますし、これだけの幅があればカーポートの設置も問題なくできると言えるでしょう。
なお、旗竿地にカーポートを設置する場合、車の駐車スペースと人が行き来するためのスペース以外に、柱を建てるためのスペースが必要になります。駐車場に普通車を停め、その横を問題なく人が行き来できるだけのスペースを確保したい場合、通路幅は最低3.3m程度確保するのが望ましいとされます。ただ、カーポートの設置も検討しているのであれば、車の幅「+1~1.5m」を目安にスペースの確保をすると良いでしょう。
旗竿地の通路部分を駐車場にする場合、これ以外にも「車庫勾配が確保できるのか?」など、他にも検討すべきポイントは多いです。この辺りは、土地の仲介を担当する不動産会社や建設会社と相談しながら、最適な土地を探すと良いでしょう。
旗竿地に適したカーポートとは?
一口にカーポートといっても、いくつかの種類が存在します。旗竿地は、整形地とは形状がかなり異なるので、設置するカーポートについても注意が必要です。
ここでは、旗竿地に設置するカーポートに適した代表的なタイプをご紹介します。
- 後方支持タイプのカーポート
一般的に、カーポートは左右どちらかに柱を設置して屋根を支える構造になっています。ただ、旗竿地の狭い通路にこのタイプのカーポートを設置する場合、柱を設置するために駐車スペースを圧迫してしまいます。実は、カーポートには後方に1本の柱を設置して屋根を支えるタイプが存在していて、このタイプの場合、左右に柱がない分、駐車スペースに余裕が生まれるのです。なお、一般的なカーポートよりもデザイン性が高いという扱いのため、本体価格は30~50万円程度と割高な設定となっています。 - 縦連棟タイプのカーポート
縦連棟タイプは、縦に2台駐車できる長いカーポートです。一般的なカーポートは、奥行が6m弱の物が多いのですが、縦連棟タイプは12mもの長さを誇ります。車を2台以上所有している方の場合、両方を保護することができますし、長い通路部分全体に屋根が設置されるので、悪天候時でも濡れずに玄関まで行ける点が大きなメリットです。 - 両支持タイプのカーポート
両支持タイプは、左右に4本の柱をたて、屋根を支えるタイプで、強風や積雪などに対して耐久性が高いカーポートとなります。旗竿地は、周囲を他の住宅に囲まれるという特性があり、カーポートが強風などで飛ばされたといった際には、隣家に大きな被害をおよぼしてしまうリスクがあるのです。そのため、強風の影響が大きい地域や積雪量が多い地域では、万一のことを考えると、高い耐久性を誇る両支持タイプを選ぶ方も多いです。なお、両支持タイプのカーポートは、オーソドックスな形状なので、本体価格は安価なものも多いです。安いものであれば、20万円程度から購入することができるでしょう。ただ、柱が4本となり、基礎の数が増えるので施工にかかる費用は高くなります。
旗竿地にカーポートを設置する場合、限られたスペースを有効活用できるようにするためにも、設置するカーポートの形状は慎重に検討しましょう。後方支持タイプなどは、デザイン性が重視された製品なので、本体価格がやや割高に設定されていますが、カーポートを設置した後に「駐車場が使いにくい…」と感じるよりは良いはずです。
なお、カーポートの設置に際しては、本体の購入費用以外に、設置工事の費用として5~10万円程度のコストがかかります。また、地面をコンクリートやアスファルトで舗装するという場合は、別途舗装工事に費用がかかるので、事前にしっかりと見積りをとりましょう。
旗竿地にカーポートを設置する場合の注意点

旗竿地にカーポートを設置する場合、土地の特徴から近隣トラブルの原因になる可能性があるので注意が必要です。
先程ご紹介したように、旗竿地で駐車場を用意する場合、横幅がそこまで広くない竿部分のスペースが活用されるケースが多いです。旗竿地は、周囲を他の建物に囲まれている場合が多く、駐車場となるスペースも両側に住宅が存在するといった立地になっている場合がほとんどです。
そのため、カーポートを設置したことで、隣家の人の生活に影響を与えてしまう可能性が生じ、それをもとにトラブルにまで発展する可能性があるのです。カーポートの設置が近隣トラブルの原因にならないようにするには、以下のような点に注意しましょう。
隣家の日当たりを遮らないように注意する
一つ目のポイントは、隣家の日当たりを妨げないようにするという点です。旗竿地は周囲を隣家に囲まれるという立地になるケースが多く、当然駐車場となる通路部分も隣家と接している可能性が高いです。
そのため、そこにカーポートを設置した場合、隣家の日当たりが悪くなってしまう可能性があるのです。お隣の方が日当たりの良さを気に入って土地を購入していたという場合、カーポートの設置で急に日当たりが悪くなれば、苦情につながる可能性が高いと考えられますよね。
対策として考えられるのは、カーポートの屋根に採用する素材について、採光性があるクリアマット系の屋根材を使用するという方法です。クリアマット系の素材でも、多少日当たりに影響を与えますが、日射を完全に防ぐ金属屋根などと比較すると、トラブルに発展する可能性はかなり低くなるはずです。なお、隣家と日当たりに関するトラブルを抱えないためには、土地探しの段階で隣家との位置関係などをしっかりと把握しておくことが大切です。
自然災害でカーポートが倒壊し隣家に被害を出す
台風や地震などの災害時には、カーポートが倒壊してしまうといった被害が珍しくありません。ただ、住宅が狭い地域内で密集する旗竿地の場合、カーポートが倒壊すると、自分達だけの問題で収まらず、隣家にまで被害が拡大する可能性が高いのです。実際に、カーポートの屋根が強風で飛ばされた…なんて場合、すぐ近くにある隣家に勢いよく衝突し、外壁や窓を破損させてしまう恐れがあるでしょう。さらに最悪の場合、住宅内にいた人に怪我をさせるリスクもあります。
旗竿地にカーポートを設置する場合、隣家との距離が非常に近いということを意識しておかなければいけません。特に、台風などの強風の影響が大きい地域などという場合、高耐久モデルのカーポートを設置したほうが良いでしょう。カーポートは、耐風圧強度が高いなど、高耐久モデルは本体価格が高くなるのですが、隣家に与える影響のことを考えると、その部分のコストは削減すべきではありません。
雨水や雪が隣家の敷地に落ちないようにする
旗竿地にカーポートを設置する場合、隣家との境界線ギリギリにカーポートを設置することになることから、屋根の角度によっては雨水や雪が隣家の敷地に落ちてしまうことになり、トラブルに発展することがあります。
当然、カーポートの屋根に落ちた雨水や雪が隣家側に落ちるようなことがあれば、「自分の敷地に落ちるように調整すべき!」と隣人は思うことでしょう。特に、積雪量が多い地域の場合、カーポートの屋根から落ちる雪のせいで、雪かきの回数が増える…なんて可能性もあり、大きなトラブルに発展するかもしれません。カーポートに落ちる雨水や雪は、可能な限り自宅側で処理できるよう、屋根の角度や雨樋の設置などによる対策を行いましょう。
カーポートによる騒音問題
旗竿地の竿部分を駐車場にする場合、隣家との距離の近さが原因に、騒音トラブルに発展する可能性があります。
例えば、カーポートを設置した場合、カーポートの屋根に雨が当たる音がうるさい…と苦情が出る場合があるようです。設置するカーポートの種類や雨の強さによっては、確かに大きな雨音が生じるケースがあり、隣家との近さからこの音が目立ってしまうことがあるのです。
また、仕事の関係などで深夜や早朝に車で出入りするという方の場合、エンジン音が騒音トラブルの原因になることもあるようです。この他、勢いよくドアを閉めた時のドンッという響く音もトラブル原因になるので注意しましょう。最近では、EV車など、エンジン音が静かな車種が増えているので、旗竿地のような住宅密集地に住む場合、購入する車の種類も検討するのがおすすめです。
ソーラーカーポートの場合、反射光に注意
旗竿地に設置するカーポートとしては、昨今、ソーラーカーポートが注目されています。というのも、旗竿地に家を建てた場合、周囲を建物に囲まれてしまうため、住宅屋根に太陽光パネルを設置したとしても、思うような発電量を確保することが難しい…という条件のお宅が多いのです。そこで、駐車場に設置するカーポートに太陽光パネルを設置するソーラーカーポートが注目されているわけです。
もちろん、旗竿地の通路部分に関しても、隣家の影響を受け日陰になってしまう場所もあるのですが、多くの場合、前面は開けている立地が多いため、駐車場となる竿部分なら十分な日射が確保できることが多いのです。
そのため、住宅屋根で発電量が不十分なお宅の場合、ソーラーカーポートを設置して希望の発電量の確保を目指すのですが、この場合、パネルで反射した光が隣家に影響を与え、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。太陽光発電の反射光問題は、近年取りざたされるケースが増えているのですが、隣家との距離が近い旗竿地の場合、その影響がさらに大きくなる可能性があります。
まとめ
今回は、家を建てるための土地としては、特殊な形状となる旗竿地について、ここにカーポートを設置する場合の注意点をご紹介しました。
記事内でご紹介したように、旗竿地とは公道と接する狭い通路の奥に宅地が存在するという形状の土地で、「竿がついた旗の形状」に似ていることからこのように呼ばれています。旗竿地は、いくつかのデメリットが存在するものの、整形地と比較すると安く土地を購入できるという非常に大きなメリットが存在するため、家に求める条件によっては非常におすすめできる土地と言えます。
ただ、旗竿地にカーポートを設置する場合は、整形地の駐車場とは異なり、隣家にも大きな影響を与えてしまう可能性がある点に注意しなければいけません。カーポートの設置が原因で、隣人トラブルに発展してしまうと、そこでの生活に影を落とす結果になってしまいます。
なお、旗竿地に建てる住宅で、竿の部分に駐車場を作る場合、通常のカーポートではなく、ソーラーカーポートの設置がおすすめです。旗竿地に建てる住宅は、屋根での太陽光発電が難しい場合があるのですが、ソーラーカーポートであれば、問題なく発電量を確保できる可能性が高いです。現在、旗竿地に家を所有している方で、屋根での発電が難しいと悩んでいる方がいれば、お気軽に『ソーラーカーポート専門店 とくとくショップ』にご相談ください。とくとくショップでは、経験豊富なスタッフが現地調査を行い、ソーラーカーポートの導入でどれぐらいの発電量が確保できるのか、事前に調査も行っています!