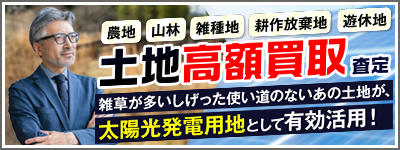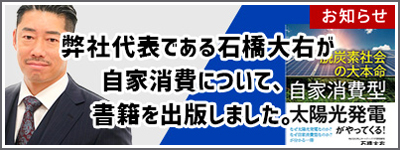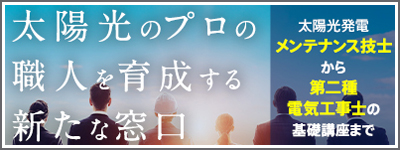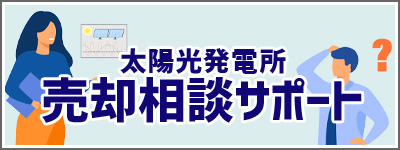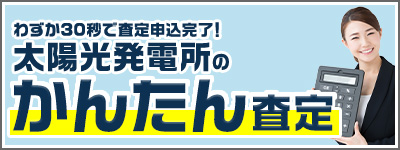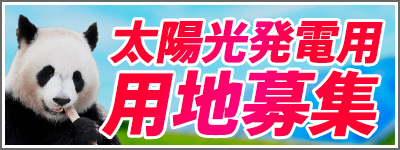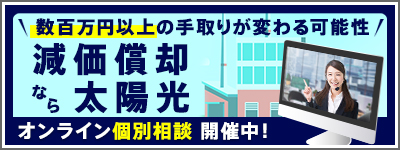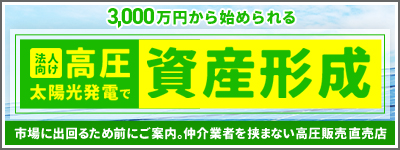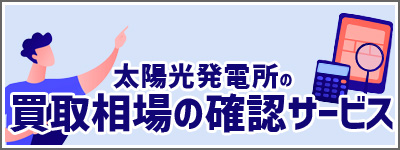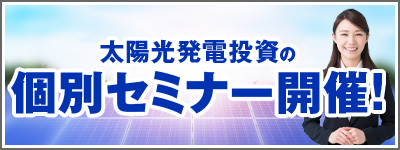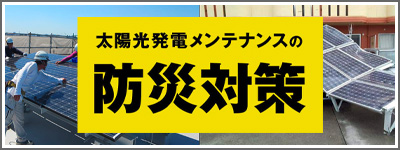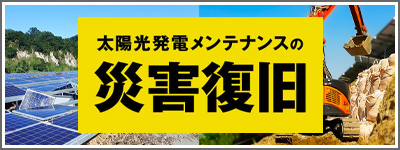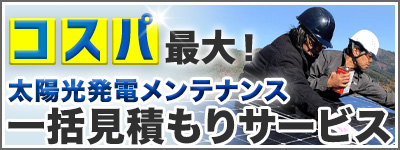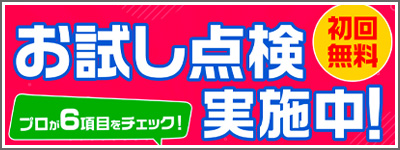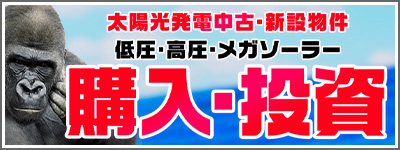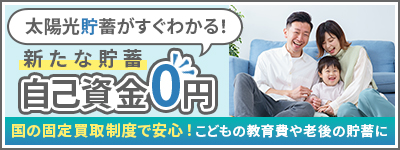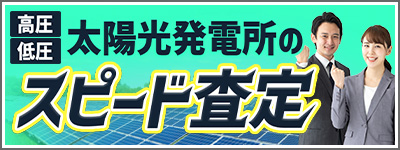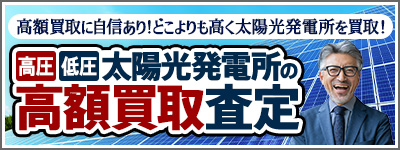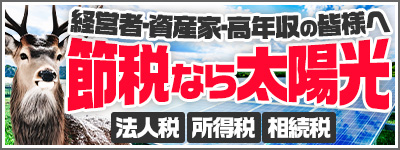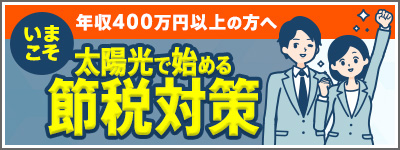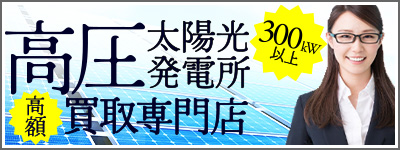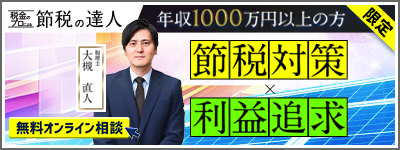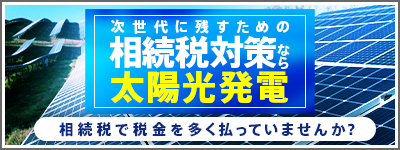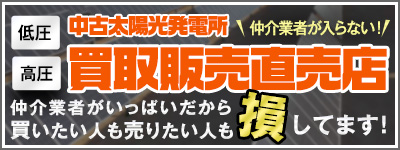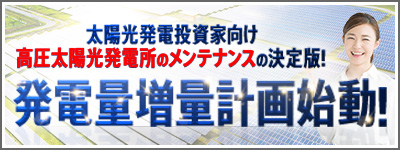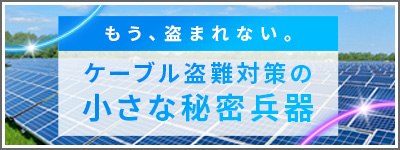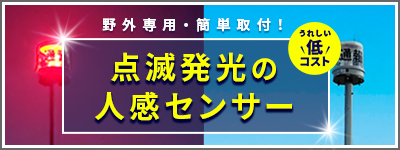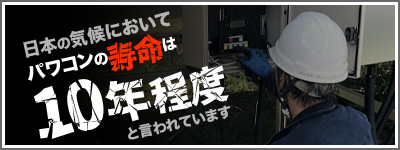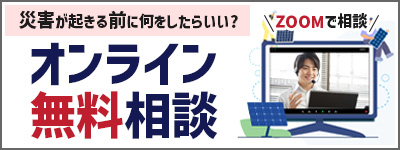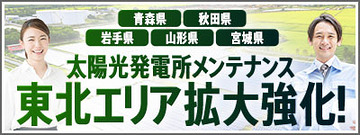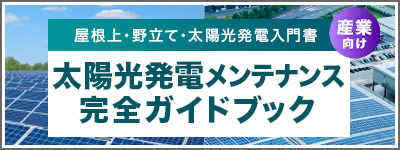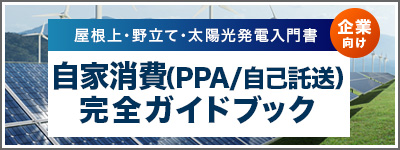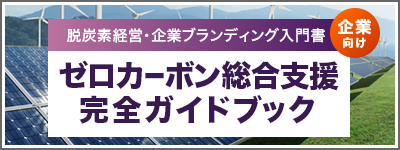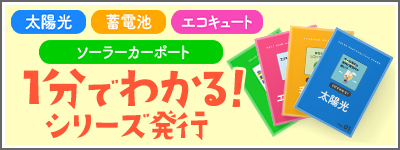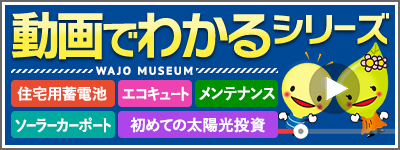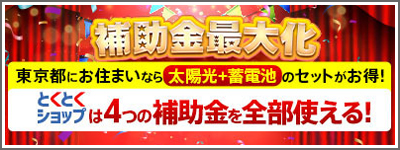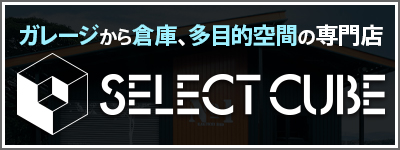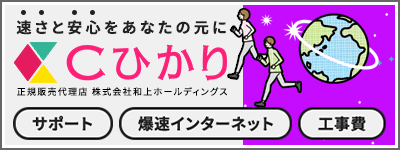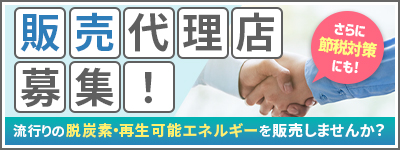こんにちは、石橋です。
今回は、最近大きな問題になっている物価高について、その原因や対策の遅さなどについて気になることがたくさんあるので、ここでひとつ大いに語ってみたいと思います。
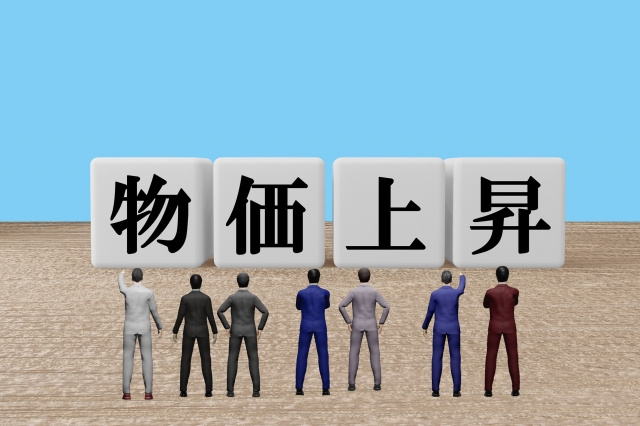
まず大前提として、この物価高の根本的な原因はコロナ禍です。少々意外に思うかもしれませんが、コロナ禍で世界のほとんどの国は財政出動を加速させ、その資金を調達するために貨幣量を増やしたり、国債を発行したりといった行動に出ました。その結果、コロナ対策の予算を確保することはできたのですが、世界中に膨大なお金がだぶつく事態となりました。
モノの供給量は変わっていないのに貨幣の流通量だけが増えると、インフレが発生します。インフレになると貨幣の相対的な価値が下がるので、物価が高くなります。最初にインフレは欧米(特にアメリカ)で大きく進行し、アメリカではCPI(消費者物価指数)が前年同月比で8%くらい高くなったという時期が長く続きました。よくアメリカやハワイに行くと「ラーメンが5,000円」なんて話が飛び交っていますが、これはあながち極端な数字ではなく日本円に換算するとラーメン1杯が5,000円を超えるといったことも現実に起きています。まず、これが現在問題になっている物価高の発端となった事実です。これを踏まえつつ、話を進めましょう。
そしてそのインフレの波は、日本にも押し寄せています。欧米ほどひどい数値ではありませんが、CPIが3%から4%台で推移しているので、これが続くとなかなか深刻です。日本もコロナ対策で10万円給付をはじめ、ゼロゼロ融資など金銭的なバラマキをかなりやったので、それが貨幣量の増大を招いて物価高につながっています。
しかも、日本の場合はそこに円安が加わります。モノの大半を外国からの輸入に依存している日本では、円の価値が下がると輸入コストが増大し、そのまま商品価格に転嫁されます。つまり、円安=物価高です。日本はコロナ禍由来のインフレと、円安よる輸入コスト増というダブルパンチによって物価高が進行しているわけです。
これに対して、国はどう対処するのが正解なのでしょうか。日本よりも強烈なインフレが進行した欧米では、各国が一斉に利上げをしました。政策金利を上げると市中のお金が銀行などの預金に向かうようになり、投機的なお金の動きが弱くなります。その傾向が続くとやがて景気の過熱感が弱まり、物価も収束していくというわけです。
それでは、日本はどうでしょうか。日本ではアベノミクスから始まった金融緩和が長く続いていて、日本円をジャブジャブ供給し続けてきました。欧米がコロナ禍によるインフレに苦しんでいる時期も日本は大量の通貨を供給し続けたので、金融引き締めを続けている欧米vs金融緩和を継続している日本という図式で円が売られる相場展開になりました。これらはいずれも、経済の教科書に書いてある常識の範囲で理解できることです。つまり、昨今の物価高はコロナ禍やアフターコロナでも金融緩和を続けてきたことで、すでに明白だったわけです。
それに対して、日本政府は何をしてきたでしょうか。ガソリンの卸売り会社に補助金を出してわずかばかり燃料代を下げて、あと電気やガスの料金にも補助金を出して引き下げた、あたりでしょうか。もちろん、これも無駄なことではありません。しかし、あまりにもショボいと言わざるを得ません。ようやく去年あたりから日銀が少しだけ利上げをしましたが、それでも日米金利差は3%以上あるので、引き続き円安トレンドは変わらず。つまり、何もやってないんです。
しかも最近、石破総理は「ガソリン価格を1リットルあたり10円引き下げる」と言い始めました。しかし、石破総理がこれを打ち出す少し前からトランプ関税や世界的な景気減速の影響を受けて原油価格は暴落中です。1バレル100ドルを超えていたWTI(世界の原油価格の指標となるアメリカの原油先物)も、5月5日の時点で56ドル台。石破総理が何もしなくても原油先物価格は半分近くにまで下がってるんです。しかもトランプ政権の意向も影響してかジワジワと円高が進んでいるので、今度は原油価格が下がる要因が揃い始めています。つまり、今から政府の対策としてガソリン価格を下げなくても、マーケットの動きで勝手に安くなるんです。もちろん良かれと思っての政策だとは思うんですが、どこか遅くて、ショボいんですよね。
政治には、スピード感がとても大切です。そのことは、トランプ政権を見ていると分かります。トランプ政権の場合は速いだけで朝令暮改も多いのであまりプラスに作用していないとは思いますが(笑)しかしながらこのスピード感で政治が進んでいるなかで、日本は相変わらずののんびりムードで本当にいいの?と不安になってしまいます。