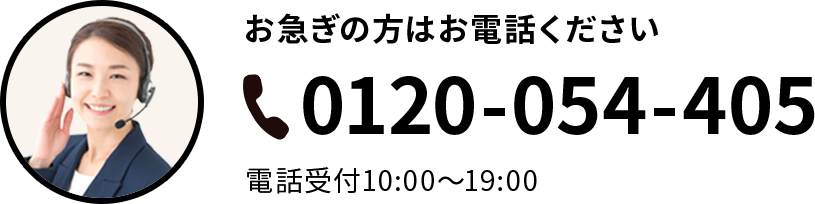今回は、家庭部門の脱炭素対策として注目されている新たな住宅の形について、低炭素住宅、ZEH(ゼッチ)、長期優良住宅の違いについて解説します。
昨今では、省エネや脱炭素、カーボンニュートラルと言った言葉を見聞きする機会が増えていると思います。省エネや脱炭素と聞くと、太陽光発電などの再エネ設備の導入をイメージする方が多いですが、住宅部門における脱炭素化では、住宅そのものの機能性を高めることでエネルギー消費量を削減するという対策が注目されるようになっています。
実際に、昨今の新築業界では、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅など、さまざまな住宅の形が登場していて、自分が家を建てる際にどのタイプの住宅を建てれば良いのかと悩んでしまう方が多くなっていると言われます。実は、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、それぞれ異なる特徴を持っていて、家を建てる際の建築コストが上下したり、活用できる補助金の種類や税制優遇に違いが生じるため、どのタイプの家にするのが自分にとって最適なのかが分かりにくいと言われているのです。
そこでこの記事では、住まいの脱炭素化に有効とされる、低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅について、それぞれの特徴や違いについて解説します。
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅と違いについて

近年では、住まい・建築物の脱炭素化のための取り組みが強く押し進められています。
例えば、自治体の中には新築住宅への太陽光発電の設置を義務化するという動きが強まっていますし、つい先日も、国が建築物の生涯CO2排出量の算出義務化に関する法律の制定を検討し始めたというニュースが出ていましたね。
そして、住宅部門における脱炭素化については、住宅そのものの機能性を高めることも重視されていて、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅の普及が強く推進されるようになっています。ちなみに、国の新築住宅に関わる今後の展望については、以下のように説明されています。
2021年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画等においては、現行の省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅・小規模建築物(新築)の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化することとしている。
2030年度以降に新築される住宅・建築物については、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されることを目指す。さらに、2050年には住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指すこととしている。
引用元:国土交通省サイトより
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅について、最も省エネ性能が高い住宅の形はZEHとされています。その次に低炭素住宅⇒長期優良住宅と続く感じなのですが、それぞれの住宅がどのような特徴を持っているのか理解したうえで、建築する家の種類を決めなければいけません。
ここでは、低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅の違いを理解するため、それぞれの特徴を分かりやすく解説します。
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅が共通して持っている機能
低炭素住宅とZEH、長期優良住宅は、全ての機能性が異なるわけではありません。住宅における省エネや脱炭素の取り組みでは、建物の断熱・気密性能を高めることや、省エネに役立つ設備を導入することが重要とされています。
つまり、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、高い断熱性能が求められる、省エネ性の高い設備の導入が求められるという点については同じなのです。建物の断熱性能と省エネ設備について、下でもう少し詳しく解説します。
断熱等性能等級5以上が必要
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は、どれも断熱等性能等級5以上が認定の条件となっています。皆さんも断熱性が高い住宅は省エネ性が高いと耳にしたことがあると思います。これは、断熱性が高い場合、エアコンなどの空調効率が向上するため、その部分のエネルギー消費を削減することができるからです。当然、空調のエネルギー効率が高くなれば、電気代の削減にも貢献してくれます。
なお、断熱等性能等級は、数字が大きくなるほど断熱性能が高いことを意味しており、2025年1月現在は「7」が最大となっています。
断熱等性能等級5は、通常の家と比べると断熱性能が少し高いといった感じで、2030年には、このレベルが最低の基準に設定されることになっています。
ちなみに、住宅の断熱性能は年々高まっていて、しっかりしたハウスメーカーが建てる家の場合、標準仕様でも断熱等性能等級5を満たしている場合が多いです。
設備の省エネ性能は一次エネルギー消費量等級6が必要
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は、どれも一次エネルギー消費量等級6が必要とされています。一次エネルギー消費量等級とは、住宅に導入する設備(照明、暖冷房、給湯、換気)の省エネ性能を示すレベルのようなものです。
当然、省エネ性能が高い設備を利用すれば、エネルギー消費量を少なくすることができ、環境に優しい生活を維持できます。また、電気代も削減できるので、住人さんにも大きなメリットになるでしょう。
なお、設備の省エネ性能に関しては、家の断熱性能が大きく関係します。例えば、断熱性能が高い家の場合、空調効率が高くなるので、勝手に設備の消費性能も向上しますよね。
実は、断熱等性能等級5を満たしている家の場合、給湯器としてエコキュートを導入し、照明をLEDにするだけで、一次エネルギー消費量等級6を実現できる場合が多いとされています。
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は、上記の二つの機能が共通して求められます。
ZEHの特徴
ZEHは、低炭素住宅や長期優良住宅と比較すると、省エネ性能が最も高い住宅の形です。なお「ZEH」とは、「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略で、使うエネルギーと作り出すエネルギーが差し引きゼロとなるような住宅のことを指しています。
ZEH住宅の場合、単に省エネ性を高めるだけでなく、太陽光発電設備などの再エネ設備を設置するなど、自宅でエネルギーを作りだす機能が必要となります。そしてそのうえで、高い断熱性能を持つ建物にすることでエネルギー収支をゼロにすることを目指すわけです。
ZEH住宅は、1年間で消費するエネルギーの合計より、太陽光発電などにより1年間で作り出すエネルギーの方が多い住宅です。もう少しわかりやすく言うと、1年間で消費するエネルギーを、ほぼすべて自家発電で確保できるようにする住宅がZEHと認められるのです。
なお、ZEHの認定は、BELS評価機関により受けることができます。
参考:経済産業省特設サイト
低炭素住宅の特徴
低炭素住宅は、行政に認定してもらう住宅の形で「二酸化炭素(CO2)の排出量を抑制する仕組みのある住宅」のことを指しています。一般的な住宅と比較すると、地球温暖化の原因となるCO2の排出量を抑えられるので、環境にやさしい住宅といえます。
ただ、低炭素住宅でも、ZEHと同様に、建物の断熱性能や設備の省エネ性能については、高いことが求められます。また、太陽光発電などの創エネ設備の設置も求められます。低炭素住宅の認定については、以下の条件を満たす必要があります。
- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となること。
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
- 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)。
- その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。
上記のうち1~3の条件が必須項目となります。「その他、低炭素化に資する措置」については、「節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、躯体の低炭素化、V2Hの設置」などからいずれかの措置を講ずる必要があるとされています。
上の条件から分かるように、低炭素住宅は1年間で消費するエネルギーの半分を創エネか省エネで賄えるようにすれば良いという条件なので、差し引きゼロにしなければならないZEHよりは認定ハードルが低いと言えます。
なお、低炭素住宅は、どこにでも建てられるのではなく、「用途地域が定められている地域」か「市街化区域」にある住宅でなければ認定を受けることができない点も注意が必要です。
参照:低炭素建築物認定制度より
長期優良住宅の特徴
長期優良住宅も、建物の断熱性能や省エネ設備の設置などが求められます。しかし、長期優良住宅は、ZEHや低炭素住宅とは、その目的が根本的に異なります。
と言うのも、長期優良住宅は「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のことを指していて、創エネや省エネにより脱炭素を目指す住宅とは少しズレがあるのです。
もちろん、先ほどご紹介したように、断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6と言ったエネルギー効率に関わる条件も設けられていますが、これ以外の認定条件は以下のように、どちらかと言うと建物の耐久性に関わる条件となっているのです。
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 居住環境
- 住戸面積
- 維持保全計画
長期優良住宅は、省エネ性を含めて、上記の各性能項目の基準を満たすように住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定し、所管行政庁の認定を受ける必要があります。
長期優良住宅は、同じ建物を長期的に使用することができるという点では、住宅部門の脱炭素化に役立つかもしれません。しかし、ZEHや低炭素住宅のように「1年間で消費するエネルギーをどれだけ削減できるのか?」と言った省エネ・創エネに関わる明確な条件は有りません。
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は建築コストに違いがある

低炭素住宅やZEH、長期優良住宅それぞれの特徴がわかったところで、実際に住宅を建てる場合のコストの違いについても解説していきます。
まずは、初期コストである建築費用に関する違いについてみていきます。
低炭素住宅、ZEHは初期コストがかかりやすい
低炭素住宅とZEH、長期優良住宅の初期コストについて、雑に解説すると以下のようになります。
- 低炭素住宅とZEHは、通常の住宅よりも建築コストが割高になる
- 長期優良住宅は、通常の住宅と同レベルの建築コストに収まる場合も多い
- 認定に関わる手数料については大きな違いがない
初期費用の違いについて、もう少し詳しく紹介していきます。
上述のように、低炭素住宅やZEHは、通常の住宅と比較すると、どうしても建築コストが高くなってしまいます。
建物の断熱性に関しては、通常の住宅もかなり高くなっていて、ハウスメーカーによっては低炭素住宅やZEHと同レベルの性能を目指す場合が多くなっているため、この部分の費用はそこまで大きな違いは生じません。しかし、上述したように、低炭素住宅とZEHは、太陽光発電などの創エネ設備を導入しなければいけません。
太陽光発電などの創エネ設備は、住宅に導入する設備の中でも特に高額な部類に入りますし、その分どうしても建築コストが高くなってしまうのです。
ZEHに関しては、これに加えて家庭用蓄電池の設置も必要不可欠となりますし、エネルギーマネジメントシステムなどを導入する場合、設備の導入にかかるコストはかなりなものになってしまいます。
ただ、これらの設備に関しては、初期費用は高くなるものの、設置したことで日々の生活にかかる電気代を大幅に削減することができるため、中長期的に見ると損になるわけではないと言えるでしょう。
なお、長期優良住宅に関しては、断熱性能や省エネ性能に関しては一定の条件を満たさなければいけません。しかし、太陽光発電などの創エネ設備の導入に関しては、認定条件となっていないため、特に設置する必要はないのです。
また、長期優良住宅の認定条件は、建築技術が向上している昨今では、標準仕様で条件を満たしているハウスメーカーも多く、長期優良住宅だからと言って通常の住宅よりも建築コストが大幅に高くなってしまう…なんてケースは少なくなっています。
なお、低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は、どれを選んだとしても認定を受けるための作業が必要になります。認定を受けるためには、申請書類の作成や審査が必要になるため、その部分にある程度の費用がかかってしまいます。
認定を受けなければ、下で紹介する補助金や税制優遇が受けられなくなるため、条件を満たす家を建てる場合は必ず認定を受けた方が良いでしょう。なお、低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅の認定にかかる手数料については、3つとも大きな金額の差はありません。
補助金や税制優遇に関わる違い

地球温暖化対策として、日本でもCO2排出量削減のため、さまざまな取り組みが行われています。住宅領域においては、省エネ性の高い設備の導入や太陽光発電などの再エネ設備の導入など、CO2排出量削減に寄与する設備の普及を、国や自治体が後押ししています。
さらに昨今では、設備の普及拡大だけでなく、住宅そのものの性能向上を目指す取り組みが始まっています。先ほどご紹介したように、国は「2030年度以降に新築される住宅・建築物については、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されることを目指し、さらに、2050年には住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指す」としており、省エネ性の高い建築物を増やすという方向の取り組みが推進されるようになっているのです。
ただ、低炭素住宅やZEHと言った脱炭素化に寄与する住宅については、通常の住宅よりも建築コストが高くなってしまうため、建てたくても建てられない…と言う方が少なくないのです。そこで国は、低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅など、住宅領域の脱炭素化に役立つ住宅を建築する場合、補助金や税制優遇制度により後押しするようになっています。
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は、日々の生活にかかる光熱費の削減が期待出来るため、初期負担をある程度軽減してあげることができれば、普及のスピードが上がると予想できます。なお、補助金や税制優遇の取り扱いについては、どのタイプの住宅を建てるのかによって違いが生じるため、以下で分かりやすくご紹介します。
補助金の取り扱いについて
脱炭素やカーボンニュートラルと言った言葉を耳にする機会が増えている昨今では、これらに寄与する取り組みに対して手厚い補助金が給付されるようになっています。例えば、住宅設備でも、エコキュートなどの環境負荷低減が期待できる製品の導入は、その初期費用を大幅に軽減するといった取り組みが行われています。
そして、新築住宅業界でも、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅の建築には、以下のような補助金が用意されています。
上記は、2024年度に運用されていた新築住宅に利用できる補助金です。2025年度も、同様の補助金が用意されるかはまだわかりませんが、カーボンニュートラルの実現のためには、住宅領域での脱炭素化が必要不可欠とされているため、補助金の拡充はあったとしても、無くなるということは当面ないのではないかと思います。
なお、補助金の金額については、建てる家の種類によって上限金額が変わるので注意してください。以下に、低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅について、それぞれの補助金の上限金額をご紹介します。
ZEH住宅の補助上限金額
- こどもエコすまい支援事業:最大100万円
- こどもみらい住宅支援事業:最大100万円
- 地域型住宅グリーン化事業:最大140万円
- ZEH補助金 最大55万円(ZEH+なら最大100万円)
低炭素住宅の補助上限金額
- こどもエコすまい支援事業:最大100万円
- こどもみらい住宅支援事業:最大80万円
- 地域型住宅グリーン化事業:最大90万円
長期優良住宅の補助上限金額
- こどもエコすまい支援事業:最大100万円
- こどもみらい住宅支援事業:最大80万円
- 地域型住宅グリーン化事業:最大140万円
なお、補助金の給付を受けるためにはさまざまな条件を満たさなければいけません。同じような住宅を建てる場合でも、補助金の金額が異なる場合や補助金を利用できない場合もあります。ちなみに、国の補助金については、基本的に併用することはできません。
税制優遇措置について
低炭素住宅、ZEH、長期優良住宅は、通常の住宅を建てたのでは受けられない税制優遇措置が用意されています。脱炭素化に寄与する住宅を建てた場合に受けられる税制優遇には、以下のような制度があります。
- 住宅ローン減税もしくは投資型減税の優遇(共通)
- 登録免許税の減税(低炭素住宅、長期優良住宅の場合)
- 不動産取得税の減税(長期優良住宅の場合)
- 固定資産税の減税(長期優良住宅の場合)
低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、住宅ローン控除の優遇措置が受けられることが有名です。また、低炭素住宅と長期優良住宅は、このほかにも登録免許税の減税措置などが設けられます。
注意が必要なのは、税制優遇措置については、補助金を受ける場合と比較すると、金銭的なメリットはそこまで大きくありません。フルに税制優遇が受けられた場合でも、申請時の手数料がチャラになるかどうかと言った程度の金額にしかなりません。
その他の金銭的なメリットについて
低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、上記のように補助金や税制優遇を受けられるというメリットがあります。低炭素住宅やZEHは、通常の住宅と比較すると、建築コストがどうしても高くなってしまうため、補助金によりその負担を軽減できるのは非常に大きなメリットになると言えるでしょう。
さらに、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、これ以外にも金銭的なメリットが存在します。どのタイプの住宅でも、建物の断熱性能が高い、省エネ設備が導入されているという特徴から、日々の生活にかかる電気代の削減を期待することができます。
このほかにも、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅であれば、住宅ローン(フラット35)の金利が安くなる、長期優良住宅の場合は地震保険の保険料割引を受けることができるといったメリットが得られます。
まとめ
今回は、カーボンニュートラルの実現が目指されている中、住宅領域での脱炭素化に寄与すると言われている住宅の形をご紹介しました。記事内で紹介したように、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、高い断熱性能や省エネ設備の導入が認定条件となっているため、通常の家と比較するとエネルギー消費によるCO2の排出量を削減することが期待できます。さらに、低炭素住宅やZEHに関しては、太陽光発電などの再エネ設備の導入も認定条件となっているので、より環境に優しい住宅の形と言えるでしょう。
注意が必要なのは、低炭素住宅やZEH、長期優良住宅は、通常の新築住宅と比較すると、コストの面で高くなってしまう可能性がある点です。特に低炭素住宅やZEHは、再エネ設備の導入が必須条件となるので、初期の設備導入にかかるコストはどうしても高くなります。
長期優良住宅に関しては、申請時に作成した維持保全計画に沿って家のメンテナンスを必ず行わなければならないため、家の状態に関わらずメンテナンスコストがかかってしまうのです。
ただ、エコキュートなどの省エネ性の高い設備や太陽光発電と言った再エネ設備の導入は、初期コストがかかるものの日々の生活にかかる光熱費を大幅に削減してくれるというメリットが存在します。そのため、家の建築コストが多少高くなったとしても、中長期的に見た場合には、通常の住宅よりもトータルコストを安くすることは不可能ではないと思います。