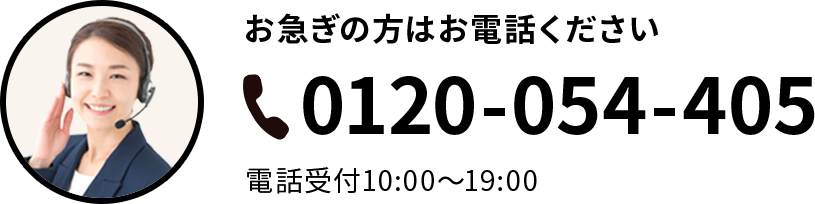小型風力発電は、一般的な風力発電よりも設備規模の小さなシステムを指します。設置環境によっては、家庭や小さな店舗などに導入することも可能です。
今回は、小型風力発電の仕組みやメリット・デメリット、風力発電との違いについて詳しくご紹介します。風力発電に関心を持っている方などは参考にしてみてください。
小型風力発電とは

出力20kW未満の風力発電を指す
小型風力発電は、出力20kW未満の風力発電を指しています。ただし、風力発電の定義については、日本と海外で異なる部分があります。
日本の場合は、出力20kW未満でかつ風車の直径16m以下などの条件を満たしたものが小型風力発電と区分されています。一方、国際電気標準会議(IEC)では、出力約50kW未満であれば小型風力発電として区分されます。
国内の運用を前提としているときは、出力20kWを基準に計画を立てていくことが大切です。
小型風力発電は手軽に導入可能
小型風力発電は小さなスペースにも導入でき、太陽光発電と同じく自宅や小規模なオフィスに設置されているケースもあります。
h3地上から15m以下の高さで設計され、一般用電気工作物に該当する小型風力発電は、基本的には認可を受けたり届け出を提出したりしなくとも設置できます。小型風力発電で一般用電気工作物に該当するのは、他の発電設備を併設せず合計発電量が20kW未満であり、その敷地内で自家消費(発電した電力を自宅やオフィスなど自分で使うこと)するケースです。
余った電気の売却(余剰電力の売電)を検討する場合は、次の項目で紹介するFIT制度の認可を受ける必要があります。
小型風力発電のメリット

続いては、小型風力発電によって得られるメリットを詳しく解説します。
電気料金の削減効果を得られる
電気料金を削減できる点は、小型風力発電を導入する大きなメリットです。
前段でも少し触れたように小型風力発電で発電した電気は、自宅や自社のオフィス・倉庫、工場などで自家消費することが可能です。また自家消費量が多くなれば、その分買電量(電力会社から供給され他電気を購入、使用した量)を抑えられるため、電気料金を削減できます。
FIT制度を活用した売電が始められる
小型風力発電を導入した場合は、自家消費だけでなくFIT制度を活用した売電も始められます。
FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)は、小型風力発電を含む再生可能エネルギー由来の電力を、一定期間固定の単価で買い取ってもらえる国の制度です。出力50kW未満の陸上風力発電については、1kWhあたり14円(2024年度)の単価で設定されています。固定買取の期間は20年間と長期で、費用回収のハードルを抑えられる可能性があります。
ただし、地域活用要件が適用されている設備であるため、発電した電気のうち30%以上を自家消費しなければなりません。100%売電できるわけではない点は注意しましょう。
太陽光発電より固定買取価格がやや高い
小型風力発電の固定買取価格は太陽光発電より高いです。FIT制度の固定買取価格は、毎年更新されますが、売電価格はFIT認定を受けた年度に定められた価格に固定され、10年間もしくは20年間変わりません。
各再生可能エネルギーの固定買取価格は、さまざまな理由から下落傾向で推移しており、以前に比べると売電収入を伸ばしにくいです。小型風力発電の固定買取価格は、1kWhあたり14円(2024年度)と、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電と比較して、1kWhあたり4円高い設定です。
コンパクトで家庭や小さな事務所にも設置可能
比較的コンパクトなサイズ感でもあるため、家庭や小さな事務所など、さまざまな場所に設置できるのがメリットのひとつです。
再生可能エネルギー発電設備の施設規模は、種類や出力などによって大きく異なります。たとえば、水力発電所を設置するためには大規模なダムの建設が必要なため、導入ハードルの高い再生可能エネルギーです。
一方、小型風力発電の場合は、家庭のベランダや屋根に設置可能なタイプもあり、住宅用太陽光発電と同じく比較的導入しやすい規模感といえます。設置スペースで悩んでいる企業にとっても検討しやすく、他の再生可能エネルギーより導入しやすいのが強みです。
小型風力発電のデメリット

次に、小型風力発電の主なデメリットを解説します。
初期費用負担が高い
小型風力発電の初期費用は高く、メーカーや施工内容によって変わるものの、初期費用は一般的に2,000~3,000万円台とされています。
一方で太陽光発電の初期費用は、経済産業省の「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」によると出力10~50kW未満で1kWあたり25.1万円(出力10kW以上の場合)です。出力20kWと仮定した場合、約502万円前後の初期費用で導入できます。
費用負担をなるべく抑えたいときは、小型風力発電以外の方法も検討しておきましょう。
出典:「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」(経済産業省)
一定の風速が確保できる場所でなければいけない
小型風力発電で発電するためには、一定の風速を確保できる場所へ設置しなければいけません。具体的には、風速5.5m/s以上の場所へ設置する必要があります。
設置場所の面積やその他条件をクリアしたとしても、風速に関する条件を満たせなければ十分な発電量を得られません。
風が強く吹けばよいというわけでもないのが、風力発電の難しいところです。強風・暴風の多い場所では、小型風力発電を設置できない可能性もあります。風速25m/s〜30m/sを超える環境では破損・事故のリスクがあるため、発電できません。
安定した風速を確保できる場所がない場合は、別の方法で脱炭素経営を始めたり、再生可能エネルギー発電設備をあらためて比較検討したりすることをおすすめします。
天候による影響を受ける
小型風力発電の発電量は、天候によって左右されてしまうことがあります。
台風などで発電停止の基準を超える風速を記録した場合は、風が吹いていたとしても発電を停止しなければいけません。発電を停止している間は自家消費による電気料金削減、売電ができないため、経済的損失が生じます。
日本の場合は、台風などの災害が多く、風の強い日も珍しくありません。小型風力発電には一定の耐久性があるものの、大きな揺れや飛来物の衝突などで破損してしまう可能性もあります。
小型風力発電を検討している場合は、まず設置予定場所の気候や年間の天候などを調査し、発電停止、損傷のリスクについて把握しておきましょう。
定期的な点検が必要
定期的な点検が必要な点は、費用負担を抑えたい方にとってデメリットと感じるポイントといえます。
小型風力発電は、他の再生可能エネルギー発電設備と同様にメンテナンスフリーではありません。固定用の部品や内部の回路などは徐々に劣化したり汚れたりするため、定期点検を欠かさないようにする必要があります。また、点検には国家資格や専門技術が必須で、専門業者へ依頼しなければ対処できません。
あらかじめ年間の維持管理費用を算出し、年間収支のバランスを確認も必要です。
小型風力発電が適しているケース
結局、小型風力発電は導入すべきなのでしょうか。ここからは、小型風力発電が適しているケースを2つ紹介します。一つの目安として参考にしてください。
一定の風速を確保できる場所がある
一定の風速を確保でき、かつ暴風や強風の少ない場所があれば、小型風力発電を検討するメリットはあります。前半で解説したように小型風力発電を稼働させるためには、少なくとも風速5.5m/s以上の安定した風が確保できる環境が必要です。この条件がクリアできるのであれば、設置メリットも大きくなるでしょう。
発電効率の高い再生可能エネルギーを求めている
発電効率の高い再生可能エネルギーを求めている場合、小型風力発電を含めて検討した方がいい場合もあります。小型風力発電を含む風力発電の発電効率は、約30〜40%とされており、再生可能エネルギーの中でも高い水準です。
とはいえ、再生可能エネルギーの経済的メリットやその他メリットは、発電効率だけで判断できない点には注意が必要です。再生可能エネルギーは自然の力を利用しているため、発電量も天候などに大きく左右されます。無風の日が続けば発電量も小さくなることは覚えておきましょう。
小型風力発電より太陽光発電がおすすめの理由

これまでにお伝えしてきた内容で、小型風力発電の設置メリットが少ないと感じる方もいるかもしれません。他の再生可能エネルギーが気になる場合は、太陽光発電を検討してみることをおすすめします。ここからは小型風力発電より太陽光発電がおすすめの理由を詳しく解説します。
風力発電より設置可能な場所が多い
太陽光発電は、小型風力発電よりもさまざまな場所へ設置できます。太陽光発電に必要なエネルギーは太陽光のみです。日光の差し込む場所であれば、発電できます。
たとえば、ビルの屋上、倉庫や工場などの屋根のほか、地上設置やカーポートの屋根、水上設置などで設置および発電を始められます。さらに、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)なら、農業と太陽光発電を両立することが可能です。ソーラーシェアリングとは、農地の上に専用の支柱などを設置し、支柱の上に太陽光パネルを固定させる設備および運用方法のことです。
このように設置場所の制約が少ない点は、太陽光発電の強みといえます。
1kWあたりの初期費用が小型風力発電より安い
1kWあたりの初期費用が小型風力発電よりも安いため、費用負担を抑えながら導入できます。
前半でも解説したように太陽光発電の初期費用は、経済産業省の「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」によると出力10~50kW未満で1kWあたり25.1万円(出力10kW以上の場合)とされています。出力20kW前後あれば、約502万円前後の初期費用で導入できます。小型風力発電と比較して1,000万円以上安く、メリットも大きいです。
初期費用の負担で悩んでいる場合は、太陽光発電を検討してみるのがおすすめです。
出典:「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」(経済産業省)
製品の種類が多い
製品の種類という点でも太陽光発電は、メリットの多い発電設備といえます。
各メーカーでは、さまざまな種類の太陽光パネルやパワーコンディショナ、その他周辺機器を開発・製造し続けています。国内メーカーの京セラや長州産業などは、太陽光発電メーカーとしても代表的です。さらに、海外メーカーもさまざまな製品を製造・販売しており、国内で購入することが可能です。
発電設備は発電量や効率に大きな影響を与えるため、しっかりと比較して検討したい製品のひとつです。また、製品の種類が多ければ多いほど、自社に合った太陽光パネルや周辺機器を見つけやすいといえます。
蓄電池を活用すれば夜間でも自家消費可能
太陽光発電の電気は、蓄電池を活用すれば夜間や発電量の少ない場面でも活用することが可能です。
小型風力発電の強みは、日中・夜間にかかわらず発電を続けられるところです。そのため、小型風力発電の方が電力を継続的に取り出しやすいと感じる方もいるでしょう。しかし、蓄電池を導入すれば太陽光発電も同様に日中・夜間問わず電力を使用できます。
日中に余った電力を蓄電池へ貯めておけば、夜間や消費電力量の多い時間帯、発電量の少ない日などに放電し、自家消費したり、売電したりすることも可能です。
非FIT型の事例が多く運用しやすい
非FIT型とは、FIT認定を受けない状態で再生可能エネルギーを運用していく方式のことです。太陽光発電にかぎらず再生可能エネルギーの固定買取期間は、10年もしくは20年間と定められています。
そのため、売電収入を目的として導入する場合も、卒FIT後の運用方法を考慮しなければなりません。
非FIT型太陽光発電事業に関する事例は多岐にわたり、関連サービスのHPや非FIT型太陽光発電関連のコラム記事などから簡単に確認することが可能です。小型風力発電と比較して運用方法に関する情報を得やすいでしょう。
小型風力発電は家庭でも導入可能なコンパクトな設備!
小型風力発電は、出力20kW未満の風力発電を指しており、小さな事務所だけでなく家庭でも導入を検討できます。また、発電効率という点では太陽光発電より高く、効率的に電気を取り出すことも可能です。
ただし、初期費用や事業としての運用しやすさなどといった点では、太陽光発電の方がおすすめといえます。再生可能エネルギー事業を検討している方や脱炭素経営を始める方などは、今回の記事を参考にしながら太陽光発電を検討してみてはいかがでしょうか。
とくとくファーム0では、非FIT型太陽光発電に関するご提案をはじめ、物件のご紹介、設計・施工・保守管理などを一括でサポートしております。さらに無料の個別セミナーでは、脱炭素経営や非FIT型太陽光発電の基本やメリット、デメリットなど、太陽光発電に関するさまざまな疑問にお答えします。
非FIT型太陽光発電について詳しく知りたい方や太陽光発電事業の基本を知りたい方も、この機会にぜひお電話やメール、個別セミナーよりお気軽にご相談ください。