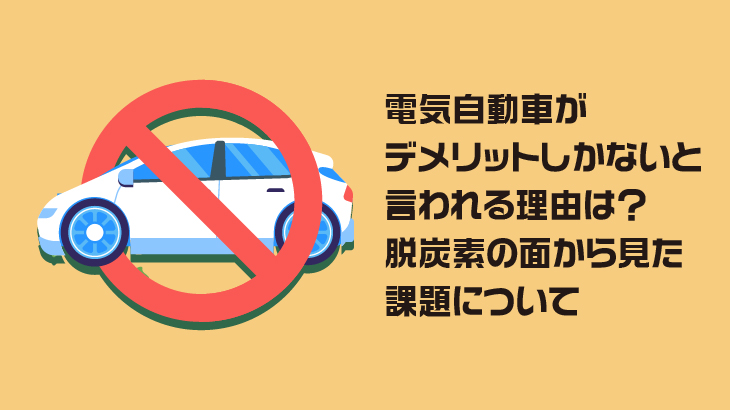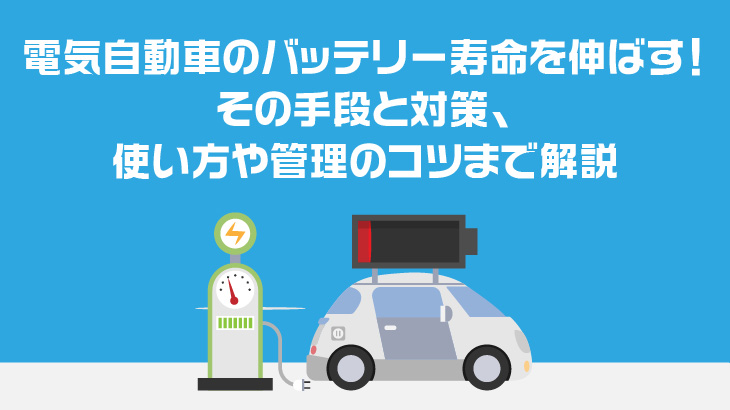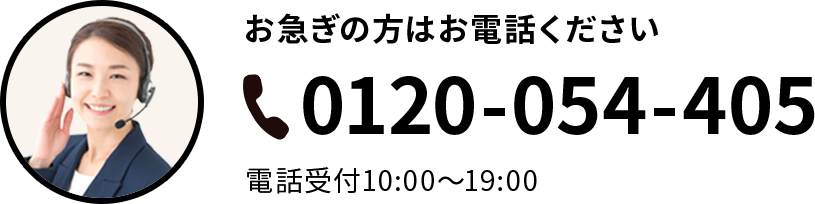この記事では、地球温暖化対策の取り組みとして大きな役割を果たすのではないかと言われている電気自動車(EV)について解説します。
電気自動車とは、その名の通り「バッテリーに貯蓄している電力を使用して走行する」自動車のことを指しています。従来の自動車は、ガソリンや軽油を燃料として走行していたのですが、電気自動車の場合、電力でモーターを動かすことで、駆動力を生むという仕組みになっているため、走行時にCO2を排出せずに済み、脱炭素社会実現に大きく貢献する技術として世界中で注目されています。実際に、EUの行政執行機関である欧州委員会は、2021年7月に2035年にハイブリッド車を含むエンジン搭載車の新車販売を禁止する「草案」を提出し話題になりました。
電気自動車は、地球温暖化などの環境問題解決に向けた一つの手段として有効とみなされ、日本でも電気自動車の普及を後押しするための取り組みが推し進められています。ただ、電気自動車に対しては、「発電する時にCO2を出しているのでは?」「国民全員が電気自動車に切り替えると電気が足りないのでは?」といった否定的な意見が少なくないのも事実です。実際に、有識者の中には「電気自動車はデメリットしかない!」と断言するような方もいて、車の買い替えを検討した時には、本当に電気自動車にして良いのか…と迷ってしまう方も多いようです。そこでこの記事では、電気自動車の普及が強く後押しされる理由と、今後の課題について解説したいと思います。
電気自動車(EV)がここまでもてはやされているのはなぜ?

それではまず、電気自動車がこれほどまでにもてはやされている理由から簡単にご紹介します。昨今の電気自動車は、バッテリーの性能も向上し、数百キロメートルの航続距離を実現していることから、走行時の静かさや滑らかさに注目して電気自動車を購入したいと考える人も増えています。
さらに、電気自動車に関しては、ハイブリット車など、その他の技術を採用した自動車と比較して、かなり優遇されているのではないかと感じる場面も少なくありません。例えば、日本国内においては、新車購入時に「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」というものが用意されていて、電気自動車はPHV(プラグインハイブリット)などと比較しても高額な補助金が交付されます。さらに、自動車購入後も、さまざまな減税措置が用意されているなど、一般的なガソリン車と比較すると、電気自動車の普及を国が強く押し進めていることがよくわかります。
そしてEU諸国では、電気自動車の普及がさらに強く後押しされていて、僅か11年後の2035年にはハイブリッド車を含むエンジン搭載車の新車販売を禁止する草案が出されているのです。この取り組みは、次に購入する自動車はエンジン付きが許されるものの、その次に購入する自動車はEVかFCEV(水素燃料電池で発電した電力で走る電気自動車)か合成燃料に限定されるというタイムスケジュールと言われています。(※1)なお、欧州はFCEVの開発で後れを取っているとされるため、実質的には電気自動車に絞った一本化政策とみなして良いという指摘もあります。
それでは、世界各国で電気自動車がこれほどまでにもてはやされているのはなぜなのでしょうか?
※1 2023年3月に合成燃料であればエンジン車の新車販売を一部認める内容で合意しています。また、日本においては、2035年までにガソリン車(ハイブリット車含む)の新車販売が禁止される予定となっています。
電気自動車の普及推進の背景には地球温暖化対策がある
ここまでの解説で分かるように、電気自動車は少し異常と感じられるほど強く普及が推進されています。それでは、これほどまでに電気自動車がもてはやされているのはなぜなのでしょうか?
これについては、地球温暖化対策の枠組みであるパリ協定の長期目標が背景にあると言われています。地球温暖化は私たち人間の生活にさまざまなリスクをもたらすとされているため、2050年の気温上昇を産業革命前に対して「できれば1.5℃、少なくとも2℃に抑える必要がある」とされています。そして、これを実現するためには、温室効果ガスである二酸化炭素の排出量を大幅に削減する必要があるとされているのです。
これにより、昨今では「カーボンニュートラル」あるいは「脱炭素」というキーワードのもと、さまざまな取り組みが始まっていて、電気自動車の普及推進もその一つとなっているのです。例えば、従来の自動車のように走行時にガソリンや軽油を燃やして駆動力を得る仕組みの場合、大量の二酸化炭素を排出します。ハイブリット車に関しても、燃費低減効果はあるものの、エンジンを組み込み、ガソリンを燃やす以上は、CO2の排出量は減らせてもゼロにすることはできないのです。一方、電気自動車の場合、バッテリーに蓄えた電力でモーターを回すことで駆動力を得る仕組みのため、走行時には一切のCO2を排出させなくて済むのです。電気自動車の普及推進は、このシンプルな考えから、「人が移動する際に排出するCO2を削減できる」と考えられ、EVバブルとよばれる現在の状況が作られているわけです。
ただ電気自動車のこの議論については、重要な視点が欠けているとされ、有識者の中には「電気自動車はデメリットしかない!」と指摘する方が増えているのです。その辺りを次項で見ていきましょう。
電気自動車(EV)のデメリットや課題とは?

日本をはじめとして、世界各国で電気自動車の普及が強く後押しされている理由は分かっていただけたと思います。日本では、テレビなどで電気自動車のCMが流れる機会が多いですし、興味を持っている方は少なくないはずです。
しかし、電気自動車は、補助金や税制優遇など、普及を後押しする取り組みが数多くある中でも、購入者が急速に増加しているとまでは言えないのが実情です。それどころか、「一度EVを経験したら二度と購入したくなくなる」「EVはデメリットばかり…」など、ネガティブな意見を見聞きすることの方が多いのではないかと感じるほどの状況になっています。
それでは、電気自動車の普及を阻害する足かせになっているデメリットや課題とはどのような物があるのでしょうか?ここでは、電気自動車に対して否定的な意見を持つ方が指摘するデメリット面についてご紹介します。
1. 車両価格が高い
一つ目のデメリットは非常にわかりやすく、電気自動車は、ガソリン車やハイブリット車など、その他の仕組みの自動車と比較すると、車両価格がかなり高くなってしまう点です。電気自動車が高くなるのは、バッテリーを生産するコストが高いからです。
分かりやすい事例として、国産電気自動車の日産「リーフ(40kWhモデル)」と同等レベルのガソリン・ハイブリット車の車体価格で比較してみます。
- 日産「リーフ」(40kWhモデル)の価格:370~420万円
- 同レベルのガソリン車・ハイブリット車の価格:210~290万円
自動車の価格は、オプションの有無などによって変わりますが、車体のみで比較すると、上記のような感じになります。これからも分かるように、電気自動車は、従来のガソリン車やハイブリット車と比較すると、圧倒的に高くなるのです。
2. 燃料の補給に時間がかかる(充電時間が長い)
電気自動車は、バッテリーに蓄えた電力をエネルギーとします。当然、走行で電力を使用すれば、どこかで充電しなければいけません。ガソリンや軽油を燃料とする自動車は、燃料が少なくなった時にガソリンスタンドに寄り補給することで走行を続けることが可能です。
電気自動車に関しては、自宅などで充電することができるのですが、充電率が20%程度から満充電にするためには、最低でも5時間程度、長い場合は1晩や丸一日かかる場合もあるとされています。
ちなみに、電気自動車に関しても、ガソリンスタンドのようなEV充電スポットが街中に用意されるようになっていますが、この場合、充電の出力や残りの充電量などによって充電時間が変わります。ただ、急速充電を使用する場合でも、30分程度はかかるとされていて、この充電時間の長さが電気自動車の大きなデメリットとみなされているのです。
ガソリン車であれば、ものの数分で燃料を満タンにできますが、電気自動車の場合は数十分~数時間待たなければならないとなると、自動車の運用を考えると大きな課題といえるでしょう。
3. 充電に苦労する可能性がある
3つ目のデメリットも充電に関するポイントです。実は、電気自動車を普段使いしようと考えた時には、街中にEV充電スポットが少ないことが課題となっています。
自動車が走行するためには燃料が必要になります。ガソリン車の場合は、ガソリンスタンドでガソリンを補給しなければいずれ止まってしまいます。これと同様に、電気自動車の場合は、バッテリーの充電が少なくなったら、電気を充電する必要があるのです。
国が電気自動車の普及を後押しするようになった昨今では、高速道路のサービスエリアや大型商業施設、コンビニエンスストアや自治体の役所などにEV充電スポットが設置されるようになっています。しかし、ガソリンスタンドの数と比較すると、まだまだ十分な数とは言えず、電気自動車で遠くまで移動するのは怖い…と感じる方が多いように思えます。電気自動車は、本体そのものは急速に進化していますが、インフラ整備が追いついていない点が課題といえるでしょう。
4. 航続距離が短い
「航続距離」は、1回の燃料補給で走行可能な距離のことを言います。実は、電気自動車は、ガソリン車やハイブリット車と比較すると、この航続距離がまだ短い点が大きなデメリットとみなされています。
冒頭でもご紹介したように、電気自動車の航続距離は年々伸びていて、2024年現在では1回の充電で400~500km程度走行可能な車種も登場しています。EUで販売されている電気自動車の中には700kmもの航続距離を実現しているモデルも存在しているそうです。ただ、航続距離が長いのはあくまでもグレードの高いモデルで、バッテリーの性能が高いことが要因となるため車体価格は非常に高くなります。
一方、ガソリンと電気を併用するハイブリット車については、1回の満タン給油で平均900kmの航続距離があり、4WDになると1000kmを超える物もあるとされています。つまり、航続距離に関しては、電気自動車の方がかなり短いと言え、今後の大きな課題となっています。ちなみに、販売開始当初の電気自動車は、1回のフル充電で180km程度の航続距離しかなく、さらに充電に8時間以上かかっていたとされています。それを考えると、電気自動車は急速に進化しているとも言えるでしょう。
5. バッテリーの劣化リスク
電気自動車は、バッテリーとしてリチウムイオン電池が採用されています。リチウムイオン電池は、携帯電話の電池としても利用されているなど、わたしたちの日常生活にも密接な関係にあります。そして、携帯電話の電池のことを考えればわかると思うのですが、リチウムイオン電池は充放電を繰り返すことで徐々に劣化が進行し、充電容量が減っていくという特徴があるのです。当然、充電容量が少なくなれば、航続距離も短くなってしまいます。
一般的にですが、電気自動車に搭載されるリチウムイオン電池の寿命は「8年または16万キロ」と言われています。しかし、使用方法、時間経過、充電方法、走行方法などによって、劣化速度が変わるという点は注意が必要です。電気自動車のバッテリーは、ガソリン車のエンジンのようなもので、まさに自動車の心臓部分といえる重要部品となります。そのため、バッテリーの劣化で交換が必要になった際には、莫大なコストがかかります。電気自動車のバッテリーを交換するための費用は、少なく見積もっても数十万円以上とされていて、車種によっては100万円を超える場合もあるとされています。
充電のための電力創出で大量のCO2を排出する
先程ご紹介したように、電気自動車がこれほどまでにもてはやされているのは、走行時にCO2を排出しなくなるため、地球温暖化対策として有効と考えられているからです。しかし、「電気自動車はデメリットしかない」と指摘する方の多くは、この考え方は重要な視点が欠けているとしています。
それは「発電の際のCO2排出が想定されていない!」という点です。電気自動車を動かすための電気は、いったいどこから来ているのでしょうか?自宅の屋根やカーポートに太陽光発電を設置し、それにより充電しているという方は別にして、多くの場合、電力会社の発電所から送られてくる電気で充電しているはずですよね。
この場合、その発電所が火力発電の場合、CO2の排出口が自動車の排気管から発電所の煙突に変わるだけといえるのです。特に、発電構成は国によって異なるのですが、中国やインドでは石炭火力発電の割合が多いとされているため、従来の自動車を電気自動車に入れ替えていくと、排出されるCO2は逆に増加してしまうという計算もあるのです。
もちろん、太陽光や風力発電の電力のみを利用して電気自動車に充電できるようになれば、CO2の排出量は大幅に削減することができると思います。しかし、現状で太陽光発電容量がダントツ世界一とされる日本には、太陽光パネルの設置場所が既に残っていないという指摘もなされていて、森林を伐採してまでメガソーラーを建設するといった本末転倒な行いも増えている状況です。
電気自動車が走行時にCO2を排出しないという点は確かに優れた特徴と考えられますが、本当に地球温暖化対策のことまで考えると、発電構成の改善もセットで考えなければならず、この部分が大きな課題となっていると言えます。
車種が少ない
これは、ガソリン車などと比較するまだまだ「新参者」と呼ばれる状態なので致し方ないのですが、自動車の購入を検討している方にとっては、車種のバリエーションが非常に少ない点が大きなデメリットとなっています。
現状の電気自動車は、セダンやコンパクトカー、SUVタイプなどの商品展開はあるものの、人気のミニバンタイプなどが販売されていません。中古車市場では、日産のリーフが寡占状態となっていると言われ、商品展開の少なさが普及を妨げているとも言われています。
ただ、この点に関しては、メーカー側も新ラインナップをどんどん出していくと予想されていますので、電気自動車の車種問題は早晩解決すると思われます。
電欠のリスクが非常に大きい
この問題は、豪雪などによる立ち往生問題が増えている昨今、電気自動車の大きなデメリットとして指摘されるようになっています。実は、電気自動車は充電が切れてしまった場合、モーターと連結している駆動輪がロックされてしまうのです。
ガソリン車は、ガス欠したとしても、ギアをニュートラルに入れれば、人力で動かすことが可能です。しかし、電気自動車の場合は駆動輪がロックされることから、僅かな距離でも移動させることができなくなるのです。
もちろん、電気自動車の電欠もガソリン車のガス欠でも、最終的にロードサービスを呼ぶという点は同じですが、電気自動車の場合、それを待つ間に安全な場所に移動させることができない点が大きなリスクとなるのです。
豪雪による立ち往生が発生した場合、電気自動車が邪魔で緊急車両が入れなくなる…などのリスクも指摘されていますし、大きなデメリット面といえるでしょう。
電気自動車に対する誤解について

ここまでは、どちらかというと電気自動車に対するネガティブな情報ばかりを紹介してきました。この記事を読んでいただいた方であれば、「電気自動車は止めたほうが良いな…」と感じたことでしょう。
ただ、電気自動車は走行時にCO2を排出しなくなるという非常に優れた特徴を持つのも事実です。日本をはじめとして、さまざまな国が電気自動車の普及を推進しているということは、それだけのメリットがあるのも事実だと思います。
そこでここでは、電気自動車にまつわる勘違いや誤解についても解説します。
「電気自動車は高い!」について
電気自動車の普及がなかなか進まない大きな要因として、ガソリン車と比較すると、車体価格が高すぎる…という問題があります。これは、電気自動車に搭載されるリチウムイオン電池が要因となっているのですが、先ほどご紹介したように、同グレードのガソリン・ハイブリット車と比較すると、1.5~1.8倍程度の販売価格になっています。
ただ、この点に関しては、補助金や税制優遇のことを考えると、価格差はそこまで大きいとも言えなくなっています。電気自動車の場合、一定の条件を満たしていれば、上限額が85万円の国の補助金を活用することができます。軽EV・PHEVの場合でも、上限55万円の補助金が交付される可能性があるため、車体価格が高いという問題はそこまで気にする必要はありません。
充電スポットについて
自動車の購入時に「本当に電気自動車で良いのか…?」と迷う方の多くは、充電スポットが少ない点を気にしているケースが多いです。中には、電気自動車は、インフラ整備が全く進んでいないとまで考えている方もいるようですね。
電気自動車周りのインフラ整備については、ガソリン車と比較した時には確かに心もとない…といえるでしょう。しかし、インフラ整備が全く進んでいないというのは大きな誤解で、実はEV充電スポットは、既に全国に2万カ所以上設置されているのです。
さらに、ガソリンスタンドと異なり、EV充電スポットは「無料」で利用できる場所も多く存在します。例えば、高速道路のサービスエリアやショッピングモールなどの大型商業施設の場合、無料で自動車の燃料補給が可能なのです。
電気自動車のEV充電スポットは、「どこにあるか?」を検索できるサービスなども登場していますし、場所さえ押さえておけばそこまで充電に困らなくて済むようなインフラが整備されています。
航続距離の問題について
電気自動車は、ガソリン車やハイブリット車と比較すると、航続距離が短すぎるというイメージを強く持っている方が多いです。実際に、販売開始当初の電気自動車は、1回のフル充電で180km程度しか走れなかったとされているので、このイメージが現在でも根強く残っているのだと思います。
しかし、上でもご紹介したように、電気自動車の航続距離は年々伸びていて、国産の主要な電気自動車で400~500kmの航続距離を実現しています。さらに、EUなどで販売されている電気自動車の中には、700km以上の航続距離を実現している車種があるとされており、航続距離の問題はそこまで気にしなくても良いという状況になっています。
まとめ
今回は、日本をはじめとして世界各国で強く普及が後押しされている電気自動車について解説しました。電気自動車に関しては、なぜこれほどまでもてはやされているのか疑問に感じたことがある人も多いのではないでしょうか?電気自動車の普及が推し進められているのは、走行時にCO2を排出しなくなるため、地球温暖化などの環境問題解決に大きく貢献できると考えられているからです。
ただ、電気自動車の環境面への影響については、全く逆の意見を持つ方も多くいます。記事内でご紹介したように、電気自動車のエネルギーとなる電気は、石炭火力を用いた発電所で作られているわけで、その電気を使用して電気自動車が走行した場合、CO2の排出口が発電所の煙突になるだけという意見もあるのです。実際に、発電方式として石炭火力の割合が多い中国やインドで電気自動車が普及した場合、走行時のCO2排出量削減効果を考慮したとしても、全体のCO2排出量は増加するという予測もあるのです。
地球温暖化対策の面で電気自動車の効果を考えた時には、自動車単体で見るのではなく、発電構成の改善もセットで考えなければいけません。例えば、電気自動車を購入する際は、自宅の屋根やカーポートに太陽光発電を設置し、再生可能エネルギーで充電できる体制を整えるなどとすれば、環境問題への貢献度はかなり高くなると言えるでしょう。