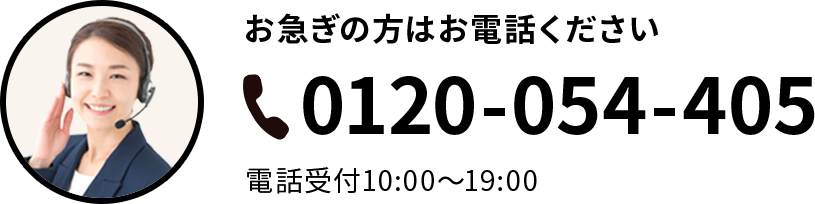系統用蓄電池をご存知でしょうか?太陽光発電や風力発電などの「再生可能エネルギー」が注目される昨今、新しいビジネスモデルでの参入を促す一端として、系統用蓄電池についての法整備が行なわれました。
そこで今回の記事では、系統用蓄電池の特徴や課題、ビジネスモデル、補助金制度について詳しく解説していきます。蓄電池を用いた事業を検討している方や、脱炭素経営に向けて産業用蓄電池について目を向け始めた方などは、ぜひ参考にしてください。
系統用蓄電池とは?

系統用蓄電池とは、電力ネットワーク(発電所や送電線、変電所、配電設備などの電力系統)や太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー発電所などに直接接続されている蓄電池のことです。
主な運用目的は電力の安定供給で、電力需要と供給のバランスを調整する役割があります。
国では2050年のカーボンニュートラル達成を目指し、再生可能エネルギーの導入数増加に向けた取り組みを進めています。
しかし、電力ネットワークや再生可能エネルギーは電気を貯めることができず、発電量を増やしても電力需要を超える電気を有効活用できません。また、電気は需要と供給を一致させなければ、大規模停電などのリスクを高めてしまう可能性があります。
さらに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは天候によって発電量が変動するため、安定的な電力供給が難しい側面もあります。
系統用蓄電池があれば余った電気を貯めておくことができるので、電力需要の急増時に活用できるようになります。
系統用蓄電池とその他蓄電池の違い

系統用蓄電池と比較されるのが、定置用蓄電池と携帯用蓄電池の2つです。
定置用蓄電池は基礎の上に本体を固定するタイプの蓄電池で、建物内の機器やコンセントなどへ電力を供給できるのが特徴です。家庭で使用する電化製品にも放電が可能な小型の家庭用蓄電池と、工場やビルなどに電力供給可能な大型の産業用蓄電池があります。
一般的には太陽光発電などの発電設備と接続することで、効率的に自家消費を進められます。また、電力系統と接続して買電(充電)と売電を行なう方式があり、系統用蓄電池と似た側面もあります。
一方の携帯用蓄電池(ポータブル蓄電池)は、コンセントで充電を行なう持ち運び可能な容量の小さい蓄電池で、系統用蓄電池よりも小型です。
これまでの主流は蓄電池ではなく揚水発電
これまで電力会社は、揚水発電で安定的な電力供給を維持してきました。
水力発電の揚水発電は、上部にある貯水池から放水し、下部の貯水池にある水車を回転させて発電を行なう仕組みです。また電力需要の少ない時は、発電時に下部の貯水池に流れた水を再びくみ上げ、上部の貯水池へ戻します。
つまり、電力需要が急増した場合は揚水発電で発電を行ない、電気の余る時間帯は外部から供給された電気で水をくみ上げるという、蓄電池のような働きを担っています。
系統用蓄電池が注目されている背景

新しい蓄電池の運用方法である「系統用蓄電池」は、主に2つの理由から利益を高められる設備としてみなされています。そのため、近年注目され始めています。
それでは、系統用蓄電池が注目されている理由についてわかりやすく解説します。
初期費用負担が軽減されつつある
蓄電池の初期費用は下落傾向で推移しているので、導入時の負担を抑えられる状況に変わりつつあります。また安い初期費用で導入できれば、系統用蓄電池の収益で早期に費用回収が見込めます。
そのため、系統用蓄電池が注目され始めているというわけです。
蓄電池の初期費用は、これまで1kWhあたり10~20万円程度でした。近年では1kWhあたり6万円程度の価格帯に下落しているので、過去の費用相場と比較して半額ほどになっています。
出典:経済産業省ウェブサイト
電力市場の単価が変動しやすく利益幅が大きい
電力市場の単価が変動しやすい環境へ変化したのも、系統用蓄電池が注目を集めている理由のひとつです。
電力市場の単価は、時間帯によって大きく変動しています。主な要因は、電気料金の値上げや出力制御の増加です。つまり電力需要の低い時間帯は単価が低く、夕方や夜間・朝など電力需要の高い時間帯は単価が高い傾向があります。
そのため、電力需要の低い時間帯に系統用蓄電池へ充電すれば、買電コストを抑えられます。反対に電力需要の高い時間帯に充電しておいた電気を売電すれば、高い収益を期待することが可能です。
このように、充電コストの軽減や売電収益の向上を図れる環境に変化したのは、注目される要因のひとつと言えます。
系統用蓄電池の活用メリット

続いては、系統用蓄電池の導入・活用メリットについて紹介します。
電力市場で収益を得られる
系統用蓄電池の主なメリットは、電力市場(JEPX)を活用して利益を得られるという点です。
これまで蓄電池は太陽光発電や風力発電に併設され、余剰電力の充電および自家消費を目的とした運用方法でした。しかし自家消費のみでは収益を得られないため、利益を確保したい企業にとって課題でもあります。
系統用蓄電池として導入すれば、充電しておいた電気を電力市場で売電をすることが可能です。また、電力需要の低い時間帯に安く電気を購入し、単価の高い時間帯に売電すれば、収益の向上を図れます。
例えば、1kWhあたり1円の状況で電気を購入・充電し、1kWhあたり10円の状況で売電すれば、「10円-1円=1kWh9円」の利益を得られることになります。
そのため、電力市場に沿って系統用蓄電池を制御できるかどうかが、事業を展開させる上で重要なポイントと言えます。
ピークカットによる電気料金削減効果
系統用蓄電池を自社の施設へ接続しておくと、ピークカットによる電気料金削減効果を期待できます。
高圧・特別高圧電力の実量制プランは、当月を含めた過去12ヵ月間の電気使用量を基準に基本料金が算出されます。各時間帯の平均的な電気使用量は、30分単位で計測・計算されています。30分単位の電気使用量はデマンドという単位で、過去12ヵ月間で最も高いデマンドは、最大デマンドと呼ばれています。
万が一最大デマンドを超えてしまうと基本料金が値上げされてしまうので、注意が必要なポイントです。
そこで系統用蓄電池を導入した場合、これまでの平均電気料金を超えそうな場面で自家消費できるため、基本料金の削減効果につながります。
非常用電源としても役立つ
系統用蓄電池を自社の建物や設備に接続しておけば、非常用電源としても活用することが可能です。
日本は台風や地震といった災害の多い環境なので、非常時における事業の復旧方法や従業員の安全対策などについて日々対策を進める必要があります。
系統用蓄電池の場合、ガソリンやガス式の発電設備と異なり燃料の保管スペースが不要です。そのため、燃料の保管方法に悩んでいる企業にも導入しやすい設備です。
系統用蓄電池の注意点
系統用蓄電池にはどのような課題があるのでしょうか。ここでは、系統用蓄電池の3つの課題について、それぞれ解説します。
導入費用やメンテナンス費用の負担がかかる
系統用蓄電池は、価格が高止まりしてコストが削減されないという課題も残されています。
前段で解説したように少しずつ初期費用は下がっているものの、それでも開発費や製造設備費は高い傾向にあり、なかなか新規導入に踏み切れない企業も多いでしょう。また、いざ導入しようと思っても、数に限りがあるため設備の施工実績を積める事業者は限定的で、価格競争にもならず技術の向上につながりません。
さらに、コスト削減を狙った車載用のリユース電池においては、実運用するための評価方法がまだ確立されていないのが現状です。
ほかにも蓄電池は、専門業者へ定期的なメンテナンスに加え、劣化した部品や機器の修理交換を依頼しなければ長期的に稼働できないため、保守管理の費用や保険料などの負担もかかります。
系統用蓄電池を検討する際は、自社の予算でカバーできるか、導入後に維持管理費用を上乗せしても費用回収できるかなどを確認する必要があります。
運用時に専門的な知識と技術が必要
系統用蓄電池で収益を得るためには、電力市場の変動に沿った柔軟かつ専門的な運用が求められます。自家消費用の蓄電池よりも運用ハードルが高く、自社単体での事業展開の難しい側面もあります。
そこで系統用蓄電池を検討する際は、アグリゲーターサービスへ運用代行を依頼するのがおすすめです。
アグリゲーターは、需要家(電力を使用している個人や企業)の代わりに中小規模のエネルギーをまとめて管理し、効率的な供給・取引を行ないます。さらに、系統用蓄電池を用いた電力の売買・供給に関するサービスがあるので、蓄電池を活用した事業展開においても重要な役割を担っています。
継続的な保守管理が必要
系統用蓄電池に限らず、蓄電池を導入する場合は保守管理を継続しなければなりません。
専門業者でなければ定期点検や部品の修理交換などに対応できないため、O&M業者(メンテナンス専門サービス)への依頼コストや、保険料といった維持管理費用の予算確保が必要とされます。
つまり、系統用蓄電池には初期費用だけでなく維持管理費用もかかるということです。これから導入する場合は、収益を伸ばすために実績豊富で、なおかつ相場より安いO&M業者への依頼や、保険・保証サービスの慎重な選定も大切です。
経済産業省は系統用蓄電池事業というビジネスモデルを推進
電力ネットワークの安定化を目的とする系統用蓄電池は、新たな事業として市場が拡大しています。
経済産業省によると、2021年10月に策定された第6次エネルギー基本計画において、系統用蓄電池のエネルギーリソースを有効活用していくことが明記されています。
ここでは系統用蓄電池事業の概要や、世界市場やメーカーについて詳しく解説します。
電気事業法改正で系統用蓄電池が事業へ位置づけ
2022年5月に改正された電気事業法では、電力を安定して供給し、調整する役割を持つ系統用蓄電池を事業として位置づけることが決定しました。これまでの電気事業法にならって、揚水発電と同様に10,000kW以上の系統用蓄電池を発電事業として、2023年4月より施行されます。
また、トラブルが発生した際に電力系統に大きな影響が出ないように、設備容量などを把握するだけでなく、保安規制などの検討も進められています。
このように系統用発電地は、脱炭素電源との併用によりますます電力が安定供給できることが期待されています。コストダウンとも相まって、大幅な導入が実現するでしょう。
アグリゲーターとメーカー、運用企業の3者で構成
系統用蓄電池事業のビジネスモデルは、系統蓄電池の導入・運用企業と管理サポートを担うアグリゲーター、蓄電池の開発製造を行なうメーカーの3者で成り立っています。
メーカーは、低コスト・高性能な蓄電池を作ることで系統用蓄電池事業の普及に貢献できますし、ビジネスモデルを支える重要な立ち位置と言えます。
運用企業は、メーカーから販売されている産業用蓄電池の購入や用地の確保、施工業者の選定・手続きなどを進めます。そして、設置後に電力の売買やシステムの管理を行なうのが、アグリゲーターです。
系統用蓄電池事業の市場規模

電気事業法の改正により、系統用蓄電池は発電事業として市場規模を拡大しています。ここでは、詳しい蓄電池の市場規模について解説します。
蓄電池の市場規模は年々拡大
太陽光発電や蓄電池の導入が増えることにより、脱炭素社会が実現しつつあります。2035年には、定置用蓄電池の市場規模が3兆4460億円になると予測されていて、中でも系統用蓄電池に関しては、2020年と比較して5倍も拡大される見込みです。
なお、定置用蓄電池の種類には以下のようなものが挙げられます。
- 鉛蓄電池
- ニッケル水素電池
- リチウムイオン電池
- ナトリウム硫黄電池
- レドックスフロー電池
中でも、ナトリウム硫黄電池や鉛蓄電池はコストが低いというメリットがあります。またレドックスフロー電池は、充放電サイクルの寿命が長く、大型の設備に向いているという特徴があります。
現在、導入拡大に向けて、各メーカーが設計を見直すなどして価格を下げる努力を行なっているので、価格競争も進展することでしょう。
海外における系統用蓄電池市場
系統用蓄電池の世界市場は、2027年に281億ドルとなることが見込まれていて、続々と導入が進められています。
また、2030年には再生可能エネルギーでの発電電力が80%と見込まれるドイツでは、蓄電池の導入も進んでいます。ドイツ貿易・投資振興機関によると、2018年時点では家庭用電気料金よりも太陽光発電・蓄電池システムのコストの方が低くなっているので、導入が加速している状況です。
導入の進んでいる主な理由は、蓄電パリティが起こっているためです。
蓄電パリティとは、太陽光発電装備と蓄電池を導入した方が電気料金を支払うより経済的メリットを得られる状態のことです。海外の蓄電池は日本の価格の半値以下で購入できるため、蓄電パリティの起こりやすい状況だと言えます。
またカーボンニュートラルの実現に向けて、中国や北アメリカ、ヨーロッパでも系統用蓄電池の導入が本格化しており、2031年の蓄電池出荷容量は457,880MWhと予測されています。
このように系統用蓄電池は、世界的に注目されている製品・事業です。
国内では特に北海道での導入が増加している
世界中で蓄電池の市場規模が拡大する中、国内では北海道での導入が急増しています。
北海道電力ネットワーク株式会社によると、2021年頃から系統用蓄電池の接続申し込みが増加している状況です。2022年7月時点では全61件もの申し込み件数で、北海道内の平均需要の半数近くにまで増えています。
なお、系統用蓄電池の系統連系(送配電網と蓄電池を接続して買電・売電を行なう)には、順潮流(充電)と逆潮流(放電)の両方の容量が必要です。
しかし、現状では変動所などの系統設備が不足しており、系統増強のための工事を長期間行なわなければいけません。これにより、すぐに系統用蓄電池事業を始められないのが主な課題と言えます。さらに工事費用については、設置事業者が多額の費用を負担するおそれもあります。
現時点では、順潮流の充電抑制(系統設備の不足および容量に合わせた充電を行なうこと)を条件として、接続の準備が進められています。
系統用蓄電池向けの補助金事業

電力供給の安定や調整の役割がある系統用蓄電池は、企業に新規参入を促す目的で助成金制度が充実してきました。
続いては、政府や東京都での補助金や、2024年(令和6年度)最新の情報についても詳しく解説します。
政府や東京都で補助金制度を導入
経済産業省は2022年春に、「2030年までに国内の企業の蓄電池生産能力を600GWhまで上げる」という目標を掲げました。
2023年度のエネルギー対策特別会計の予算額の中でも、「エネルギー受給構造の高度化対策」は3,824億円で、去年と比較して741億円増えています。特に系統用蓄電池に関する導入支援は100億円、太陽光発電導入の補助金に165億円と要求額が多くなっています。
2022年9月には東京都でも系統用蓄電池の助成金制度を導入し、最大25億円の支援を受けられることになりました。
「電力需給ひっ迫時には東京電力管内へ電気の供給を努める」「定格出力1000kW以上」などの要件を提示し、各メーカーの生産設備投資を促進させる狙いがあります。
【2024年】最新の補助金に関する情報
「令和5年度 系統用蓄電池等導入支援および実証支援事業」は、約31億円もの予算が用意された系統用蓄電池の補助金制度です。
2024年1月時点で公募は既に終了しています。ただし、令和6年度分も実施される可能性があるので、令和5年度の情報から同事業の概要について覚えておきましょう。
「令和5年度 系統用蓄電池等導入支援および実証支援事業」は、以下2種類のうちいずれかの設備を新設する場合に補助対象事業としてみなされます。
| 蓄電システム |
以下の条件を満たした場合に補助対象事業とされる ・電力系統に直接接続されている ・電力市場の取引などを通じて再生可能エネルギーの有効活用、電力バランスに貢献できるシステムであること |
|---|---|
| 水電解装置 |
以下の条件を満たした場合に補助対象事業とされる ・電力系統で余剰電力が発生する際、ディマンドリスポンス(DR:電力供給量に合わせて需要を調整する)として水素製造に電力を活用などで再生可能エネルギーの有効活用、電力バランスに貢献できるシステムであること |
補助対象の蓄電システムは、新規技術開発蓄電システムなどの新型蓄電システムの設計費と設備費、工事費です。また、対象経費への補助率は2分の1以内で、補助上限額20億円とされています。
新規技術開発蓄電システム以外の蓄電システムは、電力系統側への定格出力に応じて補助率や補助上限額なども異なります。
| 電力系統側への定格出力が1,000kW以上10,000kW未満 |
・補助率3分の1以内 ・補助上限額10億円 |
|---|---|
| 電力系統側への定格出力が10,000kW以上 |
・補助率2分の1以内 ・補助上限額20億円 |
今後同様の補助金事業が実施された場合は、申請手続きの流れや補助金の上限額・補助率、対象設備の詳細についても確認しておきましょう。
系統用蓄電池は送配電に接続された蓄電設備!
系統用蓄電池とは、電力ネットワークや再生可能エネルギー発電設備と接続し、充電した電気を家庭や工場などに送電可能な蓄電池を指しています。
また、発電事業として位置づけられたことや費用の低価格化などによって、国内でも導入が進んでいます。しかしその一方で、拡大のための課題も多く残されています。
現在、品質評価方法やライフサイクル全体を考慮したコスト評価など議論が進められています。今後は補助金制度の導入など、蓄電池の導入促進に向けて環境整備されていくことでしょう。
今、最も注目されている系統用蓄電池は、気象条件などによる再生可能エネルギーの発電出力の変動に対応するために優れた情報商材です。
2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、2030年までのエネルギー政策の方針が示されています。
企業投資向けサービス、高利回りで収益性が高い『系統用蓄電池』でさらに企業の節税対策にも!
系統用蓄電池のことは、和上ホールディングスにぜひご用命を!詳しくは下記バナーから特設ページをご覧ください。