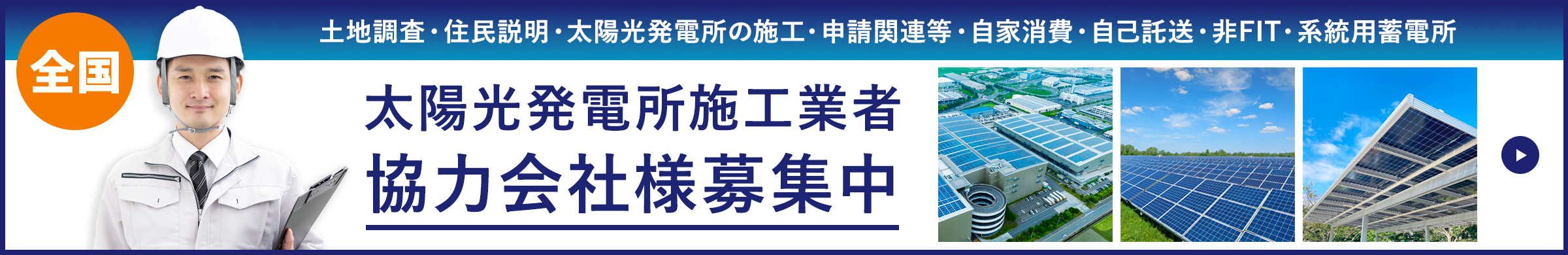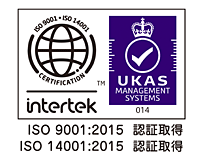COPとは締約国会議の略称で、気候変動対策と密接な関係があります。しかし、COPの意味や意義などは普段目にする機会の少ない内容で、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、COPとは何か、意味や事例、脱炭素経営との関連などについて詳しくご紹介します。脱炭素経営に向けて関連情報を調べている方は、参考にしてみてください。
COPとは?

COP(Conference of the Parties)とは、日本語では締約国会議と言い、条約を結んだ国同士が行なう会議のことです。
198ヵ国の政府や学者、企業などがCOPに参加し、情報交換や議論を交わしています。またCOPの中で条約が定められるケースもあり、中には気候変動に関する条約も存在します。
提示されるテーマは今回紹介する気候変動をはじめ、生物多様性や干ばつによる砂漠化を防ぐための国際条約など多岐にわたっているのが大きな特徴です。
ちなみにCOPの後に記載されている数字は、COPの開催回数を指しています。例えばCOP10は、10回目の会議という意味です。
COPの歴史

1992年6月3日~14日、ブラジルのリオデジャネイロで開催された環境と開発に関する国連会議では、環境問題をテーマにした議論が交わされたほか、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)という条約も採択され、1994年に発効されました。
(採択:条約の調印のみで発効されていない状態、発効:法的な効力を持っている状態)
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)は気候変動問題の解決を目的として、大気中の温室効果ガス安定化、締約国に対して温室効果ガスの削減計画や実績といったデータの公開義務など、多くのルールや取り組みについて決められています。
また、その内容に沿って対策の提示や議論、温室効果ガス削減効果や排出量の公開なども必要なため、1995年から毎年COPが開催されています。
COPで採択、合意された主な内容
気候変動問題に関するCOPでは、条約や気候変動に関する取り組みや目標などが決められています。政府で対応しなければいけないケースもあれば、企業や個人レベルにも影響のある内容も含まれているため、事業者も把握しておくことをおすすめします。
それでは、COPで採択された主な合意内容についてわかりやすく紹介します。
国連気候変動枠組条約
前段でも紹介した国連気候変動枠組条約(UNFCCC)は、COPで採択された条約ではないものの、気候変動に関するCOPの始まりだと言えます。
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)は全ての国連加盟国が締結・参加している大規模な条約で、気候変動の対策に関する大きな方針や目的について定められています。
以下に主な概要を紹介します。
- 大気中にある温室効果ガスの濃度を安定化させるのが同条約の目的
- 温室効果ガスの削減計画策定や実施、排出量に関する実績公表の義務化
- 先進国は発展新興国に気候変動対策に関する資金や技術を用いた支援を行なう
つまり、気候変動問題の原因とされている温室効果ガスの増加を抑えるのが、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)および気候変動に関するCOPの目的と言えます。
京都議定書
1997年に京都で開催されたCOP3では、京都議定書が採択されました。
先進国に対して法的拘束力のある温室効果ガス排出削減目標が定められており、日本の温室効果ガス削減目標は、2012年までに5%削減という内容です。
ほかには、日本で2026年から始まる排出権取引に関する仕組みの構築、国家間で協調しながら環境問題の対策へ取り組める制度や仕組みの導入などが行なわれています。
ただし、新興国に対する温室効果ガス削減目標やその他の規制については定められていないという問題点もあります。またアメリカは、この問題点などから2001年に京都議定書から離脱してしまうなど、足並みの揃わない状況でした。
コペンハーゲン合意
2009年、デンマークのコペンハーゲンで開催されたCOP15では、京都議定書で問題とされた新興国への規制に関する内容を中心に、さまざまな議論が交わされました。
その結果、コペンハーゲン合意という新興国を含む気候変動問題への対策が、いくつか盛り込まれています。
例えば新興国に対しては、温室効果ガス削減に関する行動を2年に1回報告する義務が課されました。また先進国には、2010年1月までの温室効果ガス削減目標提出に関する義務も定められています。
そのほかには、産業革命以前から起きている地球の平均気温上昇について、2℃以内に抑えるための削減目標が決められました。
ただし、COP15の時点でもアメリカは復帰しておらず、中国も参加していないため、温室効果ガス排出削減に関する国際的な協調という点で大きな問題を抱えています。
パリ協定
2015年にフランスのパリで開催されたCOP21では、2020年以降の気候変動問題対策に関する枠組みが作られました。
京都議定書でも気候変動問題対策に関する取り組みや枠組みが作られたものの、対象が先進国のみ、アメリカの離脱などといった問題によって上手く機能していない状態でした。
そこでパリ協定では新たに採択・発効され、地球の気温上昇2℃未満および1.5℃に抑える努力を行なうという目標に加え、以下のような内容が盛り込まれています。
- 全ての締約国が5年ごとに温室効果ガス削減目標と実績を報告
- 全ての締約国が柔軟に対策と実施状況の報告を行ない、レビューを受ける
- 先進国だけでなく新興国も資金を提供する
ほかにも、国内でも既に実施されているカーボンクレジットに関する活用などが盛り込まれ、より具体的かつ国際的な協調を重視した内容へ変わっています。
出典:外務省ホームページ
最新のCOPでは何が話し合われた?

2024年2月時点で、最新のCOP28では再生可能エネルギーに関する内容についても触れられています。
ここでは、COP28のテーマや主な内容についてわかりやすく解説します。
世界の再生可能エネルギーを拡大させる
COP28では、2030年までに再生可能エネルギーの設備容量を3倍に拡大させるという内容が示され、なおかつ130ヵ国で合意されました。
日本もこれに同意し、法改正や補助金制度などさまざまな方向から再生可能エネルギーの普及へ向けた政策を進めている状況です。
企業から見ると再生可能エネルギーの導入拡大に関する動きは、脱炭素経営を進める上でメリットの大きなポイントと言えます。再生可能エネルギーは温室効果ガスの削減につながるだけでなく、自社の光熱費削減など点でも役立つのがその理由です。
化石燃料からの脱却
COP28では再生可能エネルギーの導入拡大だけでなく、2030年までに化石燃料からの脱却という内容も示されました。
今後は、化石燃料由来の電力から再生可能エネルギーや次世代エネルギーを活用した社会や事業の仕組みが構築されていくと言えます。また、化石燃料を活用した事業展開については規制を受けやすい環境へ変わるリスクがあるため、自社の事業方針を見直してみるのも大切です。
ロス&ダメージ支援パッケージの合意
COP27では、日本主導でロス&ダメージ支援パッケージという新たな支援方法について合意されています。
ロス&ダメージは、気候変動によって避けられない災害による損害を指します。例えば、干ばつによる農業へのダメージ、海面上昇による国土の減少リスクなどといった問題が該当します。
しかし、このような損害を受けやすい国は主に新興国であるため、技術や資金面の関係から自国では対策・対処できない状況です。
ロス&ダメージ支援パッケージは、防災や災害支援、災害保険といった総合的な支援、官民連携による気候関連サービスや技術支援といった、日本の持つ技術や知見を活かした支援を指しています。
また日本政府は、国際社会と協力しながらロス&パッケージの支援を進めていく方針です。
COPの合意や議題から見た企業への影響
気候変動に関するCOPで定められた条約や取り決めなどは、政府や自治体だけでなく企業にとっても大きな影響があります。
例えば温室効果ガスの削減は、気候変動に関するCOPで重要視されています。また日本を含む締約国は、COPで定められた条約や合意内容に沿って温室効果ガスや環境に関する規制を年々厳しい内容に変えています。
企業は、環境負荷の少ない事業活動へシフトしなければ、規制による事業の縮小や方針転換を余儀なくされる可能性があります。
そのため、COPで合意された内容や議題を確認しておくことは、自社の事業活動を継続させる上で重要です。
気候変動対策へ対応するには脱炭素経営へシフトするべき

気候変動に関するCOPでは、温室効果ガスの排出削減に関する取り決め、再生可能エネルギーの導入拡大など、環境負荷低減に向けた規制や目標などが示されています。
さらに、日本政府はカーボンニュートラル2050年達成という目標を設定し、企業に脱炭素化へ向けた取り組みを求めています。そのため、企業はCOPの動きを見ながら脱炭素経営へシフトするのがおすすめです。
ここからは、脱炭素経営の概要や特徴について解説します。
気候変動対策を取り入れた経営のこと
脱炭素経営とは、脱炭素をベースにした経営や事業方針のことです。脱炭素(カーボンニュートラル)は、二酸化炭素排出量実質ゼロの状態もしくは取り組みを指しています。
例えば、二酸化炭素排出量の少ない生産設備や機器を導入することは、脱炭素経営の視点で事業活動を進めていると言えます。また、自社の事業活動で排出された二酸化炭素を含む温室効果ガスの計測や計算、排出削減目標の策定なども脱炭素経営で求められる活動です。
このように、事業活動の方針を定める際に環境への負荷についても考慮する考え方が、脱炭素経営の大きな特徴です。
脱炭素経営には事業の見直しや省エネや創エネが必要
脱炭素経営を取り入れるためには、二酸化炭素排出量の測定だけでなく省エネ・創エネ設備の活用、事業の見直しも必要です。
事業の脱炭素化に関しては、環境負荷の少ない部材を活用したり二酸化炭素排出量の少ない物流サービスを利用したりするなど、自社の製品やサービスの提供にかかる環境負荷、取引先を見直すことで、二酸化炭素排出量を減らすのがポイントです。
ほかにも自社設備に取り付けられている空調設備を最新式に交換する、照明をLEDライトや人感センサー式に切り替えるといった省エネ対策が、脱炭素経営につながります。
一方、創エネによる対策は、省エネとは異なり自社でエネルギーを作り、環境負荷を低減させる取り組みです。代表的な方法としては、再生可能エネルギーが挙げられます。
再生可能エネルギーを設置すれば化石燃料由来の電力消費量を削減できるため、自社の二酸化炭素排出量の削減にもつながります。
非FIT型太陽光発電の導入が脱炭素経営におすすめ

脱炭素経営のポイントでもある創エネを実行するには、再生可能エネルギーの非FIT型太陽光発電を導入するのがおすすめです。
最後は、脱炭素経営におすすめの非FIT型太陽光発電の特徴を紹介します。
二酸化炭素の排出量を大幅に削減可能
非FIT型太陽光発電は、屋根や地上への設置でも発電時に二酸化炭素を排出しません。そのため、設置スペースに悩んでいる企業もスムーズに設置運用を始めることができ、また自社の二酸化炭素排出削減実績を伸ばすことも可能です。
電力会社のベースロード電源は火力発電なので、買電量を増やしてしまうと間接的に二酸化炭素を排出してしまいます。
非FIT型太陽光発電は火力発電と異なり光エネルギーを電気へ変換するため、化石燃料を使用しません。また水力発電や風力発電などほかの再生可能エネルギーと比較した場合、設置場所に左右されることなくエネルギーを取り出しやすく、地熱発電のような大規模な開発工事などの負担もありません。
発電した電気についてはFIT制度の認定を受けていないため、売電だけでなく自社の建物や設備へ供給することができるのも特長です。
そのため、発電すればするほど自家消費率を高められるだけでなく、その分電力会社から供給され電気の使用量(買電量)を減らし、なおかつ二酸化炭素排出量を削減することが可能です。
自家消費すれば光熱費削減効果を得られる
非FIT型太陽光発電で全量自家消費した場合は、二酸化炭素排出量の削減効果だけでなく、光熱費の削減を目指すことができます。
通常、光熱費を抑えるためには、節電や省エネ機器の導入によって消費電力量を削減する必要があります。しかし節電や省エネ機器の導入には限界があり、消費電力量を削減できない事業も存在します。
非FIT型太陽光発電を自社の屋根や駐車場、空地などの空いたスペースに設置して発電すれば、消費電力量を過度に制限することなく自社の光熱費を削減できます。
自社の企業価値向上
非FIT型太陽光発電は、FIT認定を受けた太陽光発電より自社の企業価値を向上させる上でもメリットのある再生可能エネルギーです。
FIT制度は、再生可能エネルギーを一定期間固定買取価格で売電できる国の支援制度です。買取単価が一定で、なおかつ10年間もしくは20年間電力を買い取ってもらえるため費用回収しやすく、収支を予測しやすいと言えます。
ただし、FIT型太陽光発電の電力は火力発電や原子力発電などが含まれている電力市場で取引されるため、100%再生可能エネルギーではありません。
その点、非FIT型太陽光発電による自家消費であれば100%再生可能エネルギーとして活用でき、二酸化炭素排出量も削減できます。
より環境負荷の低い運用を行なえるのが、非FIT型太陽光発電の強みです。さらに、環境価値の高い電力を活用していけば、脱炭素経営という点で企業価値を向上させることもできるでしょう。
COPの動向を見ながら脱炭素経営を進めていくのが大切
気候変動に関するCOPでは、温室効果ガス削減目標の達成に向けた条約が定められています。また、脱炭素化や環境負荷低減の流れが強まっていて、企業も脱炭素経営に向けた事業方針へ切り替える必要性も出てきています。
脱炭素経営に向けて何をすべきかわからない方などは、今回の記事を参考にしながら非FIT型太陽光発電の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
とくとくファーム0では、脱炭素経営につながる非FIT型太陽光発電物件のご提案から設計・施工、設置後の電力供給に関するサポートまで総合的に対応しております。
また、無料の個別セミナーでは、非FIT型太陽光発電事業から脱炭素経営の基本まで丁寧にご説明いたします。お電話やWebフォーム、無料の個別セミナーにてお気軽にご相談ください。