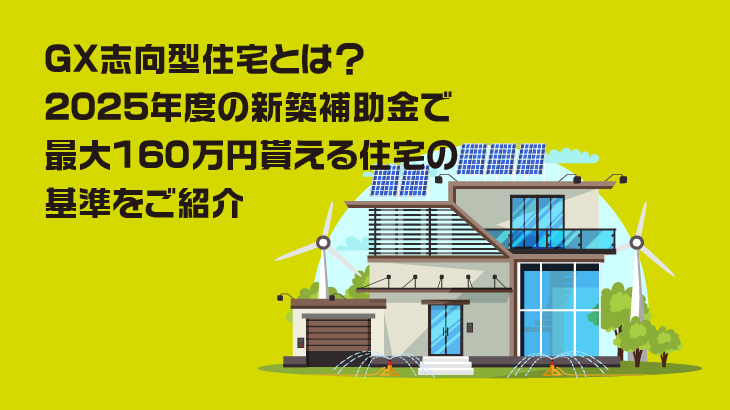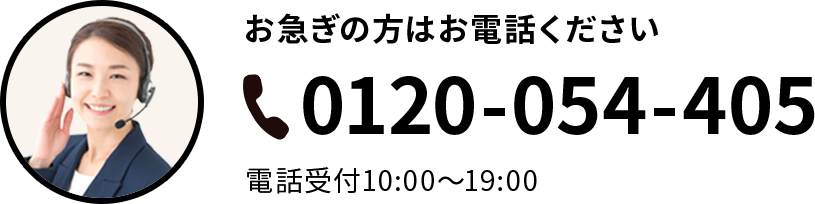今回は、建物の省エネ性能をさらに向上させることを目的として、政府が新たに設けた住宅の基準「GX志向型住宅」がどのような性能を持つ住宅なのかを解説します。
2050年カーボンニュートラルの実現が宣言されている日本では、住宅領域の脱炭素化が急務とされていて、新築時に省エネ性の高い建物を建てる場合には、手厚い補助金を受け取ることができるようになっています。一般的に、省エネ住宅と聞いた時には、ZEHや低炭素住宅、長期優良住宅を思い浮かべる方が多いと思いますが、新たな省エネ住宅の形として「GX志向型住宅」なるものが登場したのです。
GX志向型住宅については、まだ登場して間もない住宅の基準であることから、ZEHや長期優良住宅と何が違うのか、またどのような性能を確保しなければならないのかが分からないという方が多いです。ただ、2025年度中に新築住宅の購入を検討している方であれば、GX志向型住宅がどのような住宅なのかは知っておいた方が良いです。なぜなら、2025年度の新築住宅に対する補助金は、ZEHや長期優良住宅よりもGX志向型住宅を建てる方が手厚い条件になっています。2025年度の新築補助金は、子育てエコホーム支援事業が名称を変え、子育てグリーン住宅支援事業として運用されることとなっています。そして、この補助金は、GX志向型住宅の普及推進がメインとも言える作りになっているのです。
そこでこの記事では、政府が新たに設けた省エネ住宅の基準であるGX志向型住宅について、その概要やZEHなど、他の省エネ住宅と何が違うのかを解説します。
GX志向型住宅とは?認定基準などをご紹介

それではまず、GX志向型住宅がどのような住宅を指すのかについて、その概要を解説します。
GX志向型住宅は、国が新たに設けた新しい基準の省エネ住宅のことで、「脱炭素志向型住宅」とも呼ばれています。環境省などでは、GX志向型住宅のことを「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する住宅」と説明しているなど、従来の省エネ住宅と比較して、さらに高い省エネ性能を実現した住宅がGX志向型住宅とされています。
日本では、2050年カーボンニュートラルの実現が宣言されているのですが、これを実現するためには、住宅領域でのさらなる脱炭素化がカギになると考えられています。実際に、今までも省エネ性の高いZEHや長期優良住宅の普及を国が後押ししていたのですが、さらなる省エネ・脱炭素化の実現を目指すため、「GX志向型住宅」と言う非常に高い省エネ基準を満たす住宅の形が設けられたわけです。
なお、GX志向型住宅の『GX』は、「Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)」の頭文字をとった略語で、温室効果ガスの排出量削減と経済成長の両立を目指す社会変革の取り組みを指しているとされます。GX志向型住宅は、一次エネルギー消費量ゼロを実現する次世代型の省エネ住宅とされていて、脱炭素社会の実現が目指されている中、非常に重要な存在になると考えられています。
それでは、ZEHをも上回る省エネ基準が設けられているGX志向型住宅は、どのような性能を確保しなければならないのでしょうか?以下で、GX志向型住宅と認められるための基準をご紹介します。
GX志向型住宅の認定基準
GX志向型住宅は、以下の二つの基準を満たしていることが条件となります。
- 断熱等性能等級「6以上」を満たしていること
- 一次エネルギー消費量の削減率が以下の条件を満たしていること
| 一般 | 寒冷地等 | 都市部狭小地等 | |
|---|---|---|---|
| 再エネを除く | - | 35%以上 | - |
| 再エネを含む | 100%以上 | 75%以上 | - |
まず一つ目の条件は、断熱等性能等級についてです。ZEHについては「5以上」が条件となるのですが、GX志向型住宅は「6以上」と言う条件が求められます。ちなみに、断熱等性能等級は、2025年現在「7」が最高等級となっています。断熱等性能等級は、数字が大きくなればなるほど性能が高いことを示すのですが、GX志向型住宅に関しては、上から2番目の「6」が求められるなど、非常に高い断熱性能を実現しなければいけません。
次に、一次エネルギー消費量の削減率に関する条件についてですが、これについては、太陽光発電などの再生可能エネルギーや家を建てる地域特性などが関わってきます。一次エネルギー消費量の削減率は、太陽光発電などの再エネ設備を除いた状態で地域特性に関係なく「35%以上」の削減が求められ、再エネ設備も含めた時には一般地域で「100%以上」、寒冷地の場合で「75%以上」と言う非常に高い基準が設けられています。
それでは次項で、従来の省エネ住宅との違いについても見ていきましょう。
ZEH、長期優良住宅など、他の省エネ住宅との違い
冒頭でもご紹介しましたが、省エネ住宅と聞いた時、多くの方が思い浮かべるのはZEHや長期優良住宅、低炭素住宅なのではないでしょうか?特に、ZEHは、従来の省エネ住宅の中では最も高い性能を誇るとされていて、国も住宅領域での脱炭素化については、ZEH水準を基準に物事を進めているといった印象が強いと思います。実際に、2021年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画などにおいては、2030年度以降新築される住宅は、ZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指すといった目標がたてられています。
それでは、GX志向型住宅については、これらの従来型省エネ住宅と何が異なるのでしょうか?2025年度の新築住宅を対象とした補助金は、GX志向型住宅の普及を強く後押しする内容となっているため、皆さんもその他の省エネ住宅との違いはおさえておいた方が良いはずです。
なお、ZEH、長期優良住宅、低炭素住宅の特徴については、以前別の記事で解説しているので、以下の記事を確認してみてください。
ZEHとGX志向型住宅の違い
まずは、従来の省エネ住宅の中でも、最も省エネ性能が高いとされているZEHとの違いです。そもそもGX志向型住宅は「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する」ことが基準の住宅であるため、この二つの省エネ住宅に違いが存在するということは明白です。
ZEHは、「住宅で使う年間の一次エネルギー消費量が実質ゼロ以下になる」住宅と解説されることが多く、以下の基準を満たしている必要があるとされています。
- 断熱等性能等級「5以上」(ZEH強化外皮基準を満たす)
- 一次エネルギー消費量の削減率:20%以上(再エネ除く)
上記の条件を満たした住宅がZEHと認定されることとなっており、従来の基準ではこれが省エネ住宅の中でも最も厳しい基準となっていました。
しかし、GX志向型住宅の基準は、先ほどご紹介したように「断熱等性能等級6以上」、さらに「再エネを除く一次エネルギー消費量の削減率35%以上」に設定されていて、ZEHと比較してもさらに高い性能が要求されています。これが、ZEHとGX志向型住宅の大きな違いと言えます。
低炭素住宅との違い
次は低炭素住宅とGX志向型住宅の違いです。低炭素住宅は、「二酸化炭素(CO2)の排出量を抑制する仕組みのある住宅」のことを指していて、行政に認定してもらう仕組みとなっています。
低炭素住宅についても、ZEHと同様に、建物の断熱性能や設備の省エネ性能の高さが要求され、さらに太陽光発電などの再エネ設備の設置が求められます。低炭素住宅に求められる要件については、以下の通りです。
- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となる
- 再エネ設備が設置されている
- 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一 次エネルギー消費量の50%以上である
上記の内容が必須要件で、この他に「低炭素化に資する措置」を併せて講じる必要があります。
低炭素住宅については、「1年間で消費するエネルギーの半分を創エネか省エネで賄えるようにすれば良い」と言う条件から分かるように、ZEHと比較してもその認定ハードルは低く設定されています。GX志向型住宅は、ZEHの水準を上回る省エネ性を持つことが基準であるため、両者は省エネ性能に大きな違いがあると言えるでしょう。
長期優良住宅との違い
最後は、長期優良住宅とGX志向型住宅の違いについてです。なお、長期優良住宅については、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」が定義となっており、ZEHやGX志向型住宅などの省エネ住宅とは根本的に考え方が異なる部分があります。長期優良住宅についても、断熱性能に関する基準や省エネ設備の設置など、建物の省エネ性能に関わる基準が設けられているのは確かです。しかし、日常生活における省エネを目指すというよりも、同じ建物を長期にわたって使用するという面から、建物を解体するまでの生涯CO2排出量の削減を目指すという考えのもと、脱炭素化に寄与することを目的としていると言えます。
長期優良住宅は、ZEHなどと同等レベルの断熱等性能等級5以上が求められる他、一次エネルギー消費量等級6と言ったエネルギー効率に関わる条件が設定されています。しかし、省エネに関する基準以外にも、以下のような認定条件が存在するのです。
- 耐震性:耐震等級3とするなど
- 維持管理・更新の容易性:耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
- 住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有する
- 居住環境:所管行政庁毎に基準が異なる
- 維持保全管理:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている
上記以外にも、バリアフリー性や可変性、住宅履歴情報の整備などと言った基準が設けられているなど、ZEHやGX志向型住宅など、省エネ性能に特化した住宅とはかなりの違いが存在します。太陽光発電設備など、再エネ設備の設置も必須ではありませんし、GX志向型住宅などの省エネ住宅と比較すること自体が間違っているとも言えるでしょう。
ちなみに、長期優良住宅については、一般的な住宅よりも高性能な住宅と考えられていますが、そうでもなくなっているという意見も多いです。と言うのも、昨今では、建築技術や建材の性能向上などもあり、ハウスメーカーの中には、標準仕様の建築プランで長期優良住宅の条件を満たしている場合も多くなっているとされています。長期優良住宅は、太陽光発電などの再エネ設備の設置も必須条件ではありませんし、建築コストに関しては、ZEHやGX志向型住宅と比較すると、かなり抑えられると言われています。
2025年の新築補助金はGX志向型住宅が優遇?

ここまでの解説で、政府が新たに設けた省エネ住宅の基準であるGX志向型住宅と、ZEHなど従来型の省エネ住宅との違いが分かっていただけたと思います。日本政府は、カーボンニュートラルの実現のため、より省エネ性の高い新築住宅の普及拡大を目指しています。
実際に、2023年から経済産業省・国土交通省・環境省の3省が連携し、住宅省エネキャンペーンと言う取り組みを行っています。そして、この取り組みの中で、住宅の断熱化、省エネ性能向上を後押しするための事業が運営されているのです。2024年度の新築補助金は、子育てエコホーム支援事業と言う名称で運営されていて、ZEHや長期優良住宅などの高性能住宅を建てる際、非常に手厚い補助金が給付されることとなっていました。しかし、2025年度については、冒頭で紹介したように、子育てグリーン住宅支援事業に名称が変更され、より省エネ性能が高いGX志向型住宅を手厚く保護するという内容となっているのです。
以下に、2025年度の新築補助金となる、子育てグリーン住宅支援事業の補助金内容について簡単にご紹介します。
省エネ住宅ごとの子育てグリーン住宅支援事業の補助金額
子育てグリーン住宅支援事業は、経済産業省・国土交通省・環境省の3省が連携して運営する住宅省エネキャンペーンを構成する一つの事業です。一般住宅に対する補助金としては、高効率な給湯器の導入を促す給湯省エネ事業、窓の断熱化リフォームを推進する先進的窓リノベ事業が有名ですが、新築住宅の建築・購入を補助する事業として子育てグリーン住宅支援事業があるのです。
2050年カーボンニュートラルの実現のためには、一般住宅領域での脱炭素化が急務と考えられていて、それに寄与する高性能な省エネ住宅の普及を後押しする目的で、この補助金が運用されています。実際に、子育てグリーン住宅支援事業では、ZEH、長期優良住宅、GX志向住宅と言う省エネ住宅を対象として、これらの省エネ住宅を建築する人に対しては、以下のような手厚い補助金を給付するとしています。
- GX志向型住宅:補助金額 160万円
- 長期優良住宅:補助金額 80万円(解体を含む場合100万円)
- ZEH水準住宅:補助金額 40万円(解体を含む場合60万円)
上記のように、子育てグリーン住宅支援事業の補助金は、GX志向型住宅が圧倒的に高額で、長期優良住宅と比較しても2倍の補助金額が設定されています。また、長期優良住宅とZEHに対する補助金額については、2024年度の子育てエコホーム支援事業と比較して、減額対応がなされていることからも国がGX志向型住宅の普及を目指していることが推測されます。
さらに、補助金の対象となる世帯についても、長期優良住宅やZEHは「子育て世帯など」と対象世帯が限定されているのにもかかわらず、GX志向型住宅は「全世帯」が対象となっています。現状は、国も省エネ住宅の基準を「ZEH水準」に指定していますが、今後はより性能が高いGX志向型住宅の水準を目指していくのではないかと予想できます。
子育てグリーン住宅支援事業の申請概要について
2025年度中に、ZEHや長期優良住宅、GX志向型住宅など、省エネ性の高い家を建築もしくは購入しようと考えているのであれば、子育てグリーン住宅支援事業の利用を検討するのがおすすめです。
【補助金を受け取るための条件】
- 2024年11月22日以降に、基礎工事より後の工程の工事に着手したもの
- 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 家づくりを依頼する会社が「交付申請までに事業者登録していること」
- 長期優良住宅およびZEH水準住宅に該当する新築は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限る
なお、ここで言う子育て世帯と若者夫婦世帯は、以下のように定義されています。
・子育て世帯とは
申請時点において、子を有する世帯。
※子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。
・若者夫婦世帯とは
申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。
※若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。
補助金の申請受付について、最終期限が「遅くとも2025年12月31日まで」となっています。しかし、予算上限に達した場合は早期に申請受付が終了することとなるので、補助金の利用を考えている方は早めに動いた方が良いでしょう。
GX志向型住宅に関するよくある疑問

それでは最後に、GX志向型住宅に関するよくある疑問とその答えをまとめてみます。GX志向型住宅は、政府が新たに創設した省エネ住宅の基準なので、まだまだ分からないことだらけだ…と言う方が多いです。
そこでここでは、GX志向型住宅について、多くの方が疑問に感じるであろうポイントについて代表的なものをご紹介します。
建築コストは高くなるの?
新築住宅の建築を考えている方が、GX志向型住宅に対して最も気になるのは「一般的な住宅と比較して、建築費用は高いの?」と言うことだと思います。
結論から言ってしまいますが、一般的な注文住宅を建てる場合と比較すると、GX志向型住宅の基準を満たした建物を建てる場合、建築費用は高くなる可能性があると言えます。
これについては、GX志向型住宅の基準を満たすためには、高断熱な建物にしなくてはいけませんし、住宅設備についても省エネ性の高い高性能なものを選ぶ必要があるからです。さらに、GX志向型住宅は、太陽光発電などの再エネ設備を導入するのが一般的であるため、この部分にも多額のコストがかかってしまいます。
ただ、各住宅会社の標準仕様と比較して「どれだけ高くなるのか?」については施工を依頼する会社によって変わります。例えば、近年では標準仕様として長期優良住宅の認定レベルを設定しているような会社もあります。この場合、もともとの標準仕様が高い省エネ性を確保できているため、ここからGX志向型住宅の基準を満たすための対策にはそこまでの費用がかからないわけです。しかし、安価に家を建てられることを重視している建築会社の場合、標準仕様の性能からの格差が大きく、GX志向型住宅の基準を満たすためには、かなりの費用アップが求められるケースもあります。
どちらにせよ、断熱対策や高性能な設備の導入が必要になるため、一般的な住宅よりもコストはかかると考えておいた方が良いです。
立地や住宅の形状に制限がつく可能性があると聞いたけど本当?
GX志向型住宅は、一般地域の場合は再生可能エネルギーを含めて100%以上、寒冷地等においては75%以上の一次エネルギー消費量削減という条件を満たす必要があります。
したがって、GX志向型住宅を採用する場合には、太陽光発電システムを導入するのが一般的なのです。さらに、一次エネルギー消費量削減率100%以上を実現するためには、日常生活において家で使用するエネルギー以上の量を発電しなければいけません。そのため、設置する太陽光発電については、大容量の物を搭載するケースが多いとされているのです。
太陽光発電は、日光を電気に変換する設備なので、周囲を高い建物に囲まれているといった立地の場合、効率的に発電することができません。そのため、十分な発電量を確保するには立地条件を無視することができないでしょう。さらに、住宅用太陽光発電は、屋根の上に設置するのが一般的で、大容量の太陽光発電システムを搭載するには、広い屋根面積が求められます。そのため、住宅に屋上を設けて洗濯物を干したり子供を遊ばせたいと思っても、太陽光発電の発電容量を確保するため、諦めなければならない…なんてケースも考えられます。つまり、GX志向型住宅は、立地や建物形状(屋根形状)に何らかの制限が生じてしまうこともあると考えてください。
なお、住宅の省エネ性能を高めてあげることで、再エネ設備に求められる発電容量を少なくすることも可能です。また、駐車場スペースを活用して発電可能なソーラーカーポートなど、住宅屋根以外のスペースを利用して発電容量を確保するという方法も登場しているので、工夫次第で立地や建物形状の制限を受けずに済むようになるはずです。
家庭用蓄電池の設置も必須?
GX志向型住宅は、一次エネルギー消費量の削減率について、非常に高い条件が設定されています。そのため、これを実現するためには家庭用蓄電池の設置も必須条件なのではないかと考える人も多いです。
ただ、GX志向型住宅の条件に、家庭用蓄電池の設置は含まれていません。したがって、蓄電池を設置していなくても、断熱等性能等級や一次エネルギー消費量削減率の条件を満たしているなら、認定を受けることが可能です。
なお、GX志向型住宅の認定条件に入っていないものの、政府は家庭用蓄電池の設置を推奨していると考えられます。実は、GX志向型住宅の補助金を受ける際、家庭用蓄電池も同時に設置するのであれば、蓄電池導入に対する補助金も併用できることが可能となっているのです。通常、国の補助金は併用できないようになっているのですが、蓄電池の設置については、GX志向型住宅の補助金に加算する形で導入費の負担を軽減してくれる形となっています。
家庭用蓄電池は、太陽光発電と連携させることで、より省エネ効果を高めることができますし、災害による停電の際も普段通りの生活を維持できるなど、災害対策用の設備としても非常に有用です。
まとめ
今回は、住宅領域の脱炭素化が目指されている中、政府が新たに創設した省エネ基準住宅である「GX志向型住宅」の概要について解説しました。
記事内でご紹介したように、GX志向型住宅は、ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する住宅のことを指しています。具体的には、断熱等性能等級が6以上、再エネ設備を含む一次エネルギー消費量の削減率が100%以上(一般地の場合)と言う非常に高い性能を持つことが認定基準となっています。
なお、GX志向型住宅など、高性能住宅を建築する際には、やはり初期の建築コストは高くなってしまいます。しかし、住宅完成後、そこでの生活を考えた時には、日々の生活にかかる光熱費を大幅に削減することができ、中長期的に見た場合には住宅にかかるコストを安く抑えることも可能だと言えるでしょう。特に、昨今では世界情勢の不安定化から、電気代の急激な高騰などの問題もありますし、日々の光熱費削減幅はかなり大きくなると言えるでしょう。
2025年度に関しては、GX志向型住宅の普及促進のため、非常に手厚い補助金が用意されています。したがって、省エネ性の高い住宅の建築、購入をお考えであれば、GX志向型住宅の選択も検討してみてはいかがでしょう。