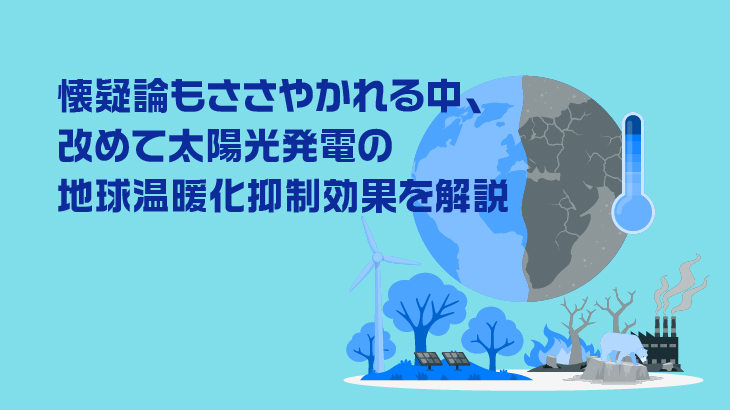太陽光パネルは地球温暖化を食い止めるどころか、環境破壊をしているという「懐疑論」を見聞きしたことはないでしょうか。本来、太陽光発電は発電時に二酸化炭素を排出しないため、火力発電などの既存の発電技術と比べると圧倒的に環境性能が高いとされています。しかも、太陽光エネルギーは無尽蔵の再生可能エネルギーです。その太陽光発電に対して懐疑論があるのは、なぜでしょうか。そして、その懐疑論は本当なのでしょうか?
当記事では、太陽光パネルの地球温暖化抑制効果に対する懐疑論を紹介し、その上で真実をお伝えしたいと思います。
最近ささやかれている太陽光発電の温暖化抑制懐疑論とは

最初に、最近見聞きすることが多くなった、太陽光発電の懐疑論について、どんな議論・主張なのかを見てみましょう。さまざまな主張や言い分があるので、ここでは主なものを紹介します。
そもそも地球は温暖化していない?
地球温暖化が気候変動や生態系の破壊などをもたらしているというのは半ば常識になっていますが、「そもそも地球は温暖化などしていない」という意見があります。超長期の気温変化を見ると、日本は江戸時代から平均気温が1度程度しか上昇しておらず、これだけ気候変動が起きるのは考えにくい、というわけです。
確かにこれはフェイクではなく、事実です。世界の平均気温を見ても、確かにこの100年間で上昇したのは0.76度なので、「江戸時代から1度しか上昇していない」というのもあながち嘘ではないということになります。
ただし、「1度しか」と表現できるほど、1度の気温上昇の影響が軽微であるかどうかは、まだ明確な答えが出ていません。
自然災害の増加と温暖化は無関係?
近年被害が大きくなっている集中豪雨や台風、線状降水帯などは、地球温暖化が原因だとする説があります。確かにこれまでなかったような現象だけに、最近起きている気象変動の原因らしきものを探すと、地球温暖化に行き当たるのは理解できます。しかしながら、地球温暖化が直接の原因であるかどうかは確定していない部分があるため、これもグレーな部分が大きいといえます。
今の時代の人たちにとっては歴史上の災害になっていると思いますが、かつて「室戸台風」「ジェーン台風」といった巨大台風が甚大な被害をもたらしたことがありました。近年ではこれほどまでに被害の大きな台風は起きておらず、台風に対する脅威だけを見ると今のほうが低くなっているようにも感じます。
これは何も台風が弱くなったのではなく、治水や土木工事などによって減災をする技術が向上したというのが最大の理由です。台風自体が弱くなった、強くなったということよりも人間の努力による対策が功を奏していると考えるべきでしょう。
地球温暖化は太陽の活動による影響が大きい?
地球温暖化の懐疑派においても、地球の気温が上昇していることは共通の認識です。「江戸時代から1度しか上昇していない」という人であっても1度上昇していることは認めているのですから。確かに地球が100年以上前よりも温暖化していることは事実です。ただし、その原因が二酸化炭素などの温室効果ガスとは限らないというのが、懐疑論のひとつの根拠になっています。
というのも、地球は太陽の活動によって過去に何度も気候変動が起きており、その典型例が氷河期です。古代の地球に二酸化炭素を大量に排出するような存在はありませんでしたが、それでも地球は何度も氷河期と温暖化を繰り返してきました。そんな長期的な気象変動の動きに対して、人類が排出した二酸化炭素の影響はそれほど大きくない、というわけです。
これは2025年から就任するトランプ次期大統領も同様の主張をしています。
日本の二酸化炭素排出量は世界の3%に過ぎない?
日本には「もったいない精神」があるので、本質的にモノを大切にしますし、ゴミのポイ捨てをあまりしない国民性なので、そもそも環境意識が高い国です。その日本が排出している二酸化炭素の量は、世界の約3%にしか過ぎません。上位を占めているのはアメリカと中国で、これらの国が本腰を入れないことには脱炭素は実現しませんし、二酸化炭素が原因であるならば地球温暖化を止めることもできないでしょう。そんな一角であるアメリカはトランプ氏の意向によってパリ協定からの再離脱が現実味を帯びていますし、石油やシェールガスなどの開発を積極的に進めると明言しています。
日本がどれだけ頑張っても、すでに努力できる余地はあまりなく、これらの二酸化炭素大量排出国が本気にならない限り、結果としてあまり意味がないというのは、2024年に開催されたCOP29でも指摘されました。
もちろん日本が率先して努力することで世界をその気運に導くことは可能だと思いますが、少なくともトランプ氏が大統領を務めている期間、アメリカはその気運にならないだろうなとも思います。
太陽光パネルの製造過程で環境負荷が掛かる?
太陽光パネルは発電時に二酸化炭素を排出することはありませんが、製造過程では一定の二酸化炭素を排出します。この点に対して「エコではない」との指摘があります。
これについては、すべての工業製品を製造する過程で二酸化炭素が排出されるわけで、太陽光パネルだけのことではありません。しかも太陽光パネルは完成して設置されてからは脱炭素エネルギーとして活躍するのですから、この指摘はあまり当てはまらないように感じます。
しかも近年では太陽光パネルの長寿命化やリサイクルの技術革新が進んでいるので、ますます太陽光パネルが環境負荷を増大させているという指摘は的外れになっていくことでしょう。
太陽光パネルの大量廃棄が有害物質の排出を伴う?
太陽光パネルには、寿命があります。寿命を過ぎた太陽光パネルは発電能力が弱くなり、やがて発電しなくなってしまいます。寿命を迎えた太陽光パネルは処分する必要があるわけですが、その際にパネルに含まれる鉛やカドミウムといった物質が自然界に流出することが環境汚染につながると懸念されています。
鉛やカドミウムはかつて日本の各地で公害病を引き起こした物質でもあるので、それが土壌や地下水などに混ざってしまうと新たな公害病の原因になりかねません。
また、普及が始まった頃の太陽光パネルが一斉に寿命を迎えることで適切に処理する能力を超えてしまい、一部の悪質な業者などが不法投棄をしたりすることで自然界に有害物質が排出されてしまうのでは、との懸念もあります。
悪質な業者による不法投棄は太陽光パネルに限らずさまざまな工業製品に共通する環境問題です。そのため太陽光パネルだけを標的に指摘するべきものではないと思いますが、やはり業者のモラルや順法意識に依存する部分が大きいため、太陽光パネルの長寿命化やリサイクルの推進は必須であると考えます。
メガソーラーの建設に伴う自然破壊が懸念されている
全国各地でメガソーラーの開発が進んでいます。もともと森林だったところをメガソーラーとして開発すると、かえって自然破壊になってしまっているとの指摘があります。
これについては、その指摘が当てはまるようなメガソーラーが残念ながら存在しています。乱開発によって森林を伐採し、そこに太陽光パネルが敷き詰められた光景に違和感や反感を覚える人も多く、「太陽光発電はけしからん」と考える人もいます。
メガソーラー自体は決して有害なものではなく、むしろ休耕地や遊休地の活用方法として高い評価を得ています。そもそも太陽光発電に適していないような場所に無茶な開発をすることが「悪」なので、メガソーラー自体を悪者にしてしまうのは早計でしょう。
今後もこうした問題は続くと思われるため、太陽光発電への懐疑論を加速させてしまう恐れがあります。
ここで改めて太陽光発電の地球温暖化抑制効果を解説

前章では太陽光発電への懐疑論について、さまざまな言い分や主張について紹介しました。なかには「トンデモ理論」もありますが、誤解によって真実が伝わっていないばかりに拡散してしまっている懐疑論もあるように思います。
さて、ここからは太陽光発電がもつ地球温暖化抑制効果について、改めて真実をお伝えしたいと思います。ここで解説する内容はすでに科学的根拠があり、エヴィデンスも整っているものばかりなので、太陽光発電を理解するのに値するものだと思います。
地球温暖化の仕組みと現状
地球温暖化とは、文字通り地球の平均気温が上昇することです。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが大気中に排出されて濃度が高まると太陽によって温められた地球の熱が宇宙空間に排出されにくくなり、地球にたまり続けます。それが積み重ねると平均気温が上昇し、温暖化を進めています。
温室効果ガスには二酸化炭素以外にもメタンなどがありますが、これらの物質は人間の活動によって排出されたものが大半で、この傾向が進行すると地球はますます温暖化してしまい、気象変動や人の住めない地域を生み出してしまうなどの問題につながっています。
二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスのせいで地球温暖化が進んでいる、との指摘を目の当たりにすると、これらの物質がまるで悪者のように感じるかもしれません。しかし実際は人類にとって温室効果ガスはとても重要なもので、もしこれらの温室効果ガスがなければ地球の気温はマイナス19度になるといわれており、到底今の豊かな自然が生まれるとは考えにくい星になってしまいます。問題なのは、温室効果ガスの濃度が高すぎることであり、その適切なバランスに戻そうというのが脱炭素や環境保護の取り組みです。
このまま地球温暖化が進むと、どうなる?
このまま地球温暖化が進行すると、地球の気温はますます上昇します。気温だけでなく海水温も上昇するため、台風が強くなり、頻発する恐れがあります。また、地球上の生態系に変化が生じるため、農林水産業への影響が生じます。すでに一部の魚が激減しているといった現象が起きていますし、農業への影響から野菜の高騰が頻繁に起きているのはご存知だと思います。
南極などの氷が溶けることによって海面上昇も起きています。このまま海面上昇が進むと海抜の低い地域が水没する恐れがあるため、ツバルやモルディブといった国々が存亡の危機に瀕してしまいます。海抜が低い国以外でも海岸線の後退が起きており、筆者は以前にベトナムの海岸で「以前はここまで陸地だった」というところが海になっている風景を目にしたことがあります。そのまま海岸線の後退が進むと現在の海岸沿いの集落が水没し、陸地ではなくなってしまう可能性があるとのことでした。
これらの影響はいずれも人類に甚大なダメージをもたらします。すべてが温室効果ガスのせいではないと考えますが、その原因の一端である温室効果ガスの排出は食い止める努力をするべきでしょう。
二酸化炭素を排出しない脱炭素が持つ効果
二酸化炭素を排出しない社会モデルを構築すると、そこにやってくるのは持続可能性のある循環型の社会です。本来、自然には持続可能な循環システムがあります。だからこそ何億年にもわたって地球では命が栄えてきたわけで、今もそのシステムは成り立ち続けています。
大自然のスケールから見ると、現在起きている環境問題はその一部にすぎません。今なら脱炭素社会を実現することで自然へのダメージを最小限に食い止めることができるでしょうし、自然にはそれを修復する力があります。全世界が脱炭素社会への歩みを進めることができれば自然は豊かさを取り戻し、人類に多大なメリットをもたらしてくれるようになります。
現段階で太陽光発電は脱炭素の切り札
とても重要な脱炭素社会への歩みを進めるために、人類は何をするべきなのでしょうか。二酸化炭素を排出しないエネルギーとして、やはり本命となるのは再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーは自然から生まれるエネルギーであり、それを利用するだけなので資源量は無限です。自然がバランスを保ち続ける限り、無尽蔵に利用できます。しかも、化石燃料を使用するわけではないので二酸化炭素も排出しません。
再生可能エネルギーにはさまざまな種類がありますが、現時点で最も有力なのはやはり太陽光発電でしょう。太陽光パネルに太陽光を当てて発電するというシンプルなエネルギーだけに太陽光パネルの生産も容易ですし、遊休地の有効活用法としてもメリットがあります。
冒頭では懐疑論を紹介しましたが、懐疑論で指摘されるようなデメリットもありつつ、太陽光発電は現時点での最適解だといえます。
太陽光発電が温暖化抑制に活躍するための課題
再生可能エネルギーの大本命として普及が進んでいる太陽光発電。地球温暖化抑制の切り札としても期待されているわけですが、もちろん太陽光発電も万能ではありません。さらなる温暖化対策の本命として活躍するためには、解決するべき課題もあります。
蓄電技術の発展と普及
太陽光発電の最大の弱点は、夜間や晴れていない日に発電ができないことです。天候は季節やその日によって異なるため不確定要素といえますが、夜間は毎日必ずやってきます。どんなにコンディションに恵まれた日であっても夜はやってくるので、太陽光パネルを設置しても1日のうち3分の1から半分程度は発電ができないことになります。
家庭用の太陽光発電を導入している場合、夜間は電力会社からの供給に依存しなければならず、「100%の電力自給」は達成できません。
そこで役立つのが、蓄電池です。近年では家庭用の蓄電池が普及してきているので、そこに余った電力を貯めておいて夜間や悪天候の日に使うといったことが可能になりました。蓄電池の容量や日照量によっては「100%の電力自給」も可能になったわけです。
このモデルが多くの家庭に普及し、また同時に大規模な蓄電設備が整備されていけば、社会全体で太陽光発電の弱点を克服することができます。
太陽光パネルの価格低下
太陽光発電が普及し始めた当時は、太陽光パネルは今よりも高価でした。それゆえに導入できる人が限られてしまっていたのですが、国の補助金が付いたことによって太陽光発電は急速に普及し、今に至っています。
その後、太陽光パネルの価格低下によって補助金の制度は終了しました。しかしながら太陽光パネルの価格低下が進んだとはいえ、ポケットマネーで買えるような価格になったわけではありません。
ここまで太陽光パネルの価格が安くなったのは、世界的な普及によってスケールメリットをいかしやすくなり、生産の効率化が進んだからです。今後もこの傾向が進み、太陽光パネルの価格が安くなることによって普及が進みやすくなることを期待します。
太陽光パネルの寿命延長
発電のコストダウンや環境負荷の軽減という観点から、太陽光パネルの長寿命化は急務です。現在設置されている太陽光パネルの寿命は、おおむね20年程度といわれています。とはいえ、20年が経過したら突然発電しなくなるというわけではなく、徐々に発電能力が低下していってやがて発電しなくなるようになります。太陽光パネルの機種や性能にもよりますが、実際には30年使用できるとの説もあり、まだ太陽光パネルの寿命については本格的に寿命を迎えた製品が少ないため、確定的なことはいえません。
そこで現在、多くのメーカーで研究が進められているのが、太陽光パネルの長寿命化技術です。すでに設置されている太陽光パネルの寿命を延ばす技術や、最初から長寿命の太陽光パネルを開発するなど方向性はさまざまですが、今後は太陽光パネルの寿命が30年以上になっていくことは間違いないでしょう。
この技術革新が進むことによって、太陽光パネルが温暖化抑制どころか環境破壊をしているとの指摘は昔話になっていくことでしょう。
太陽光パネルのリサイクル
太陽光パネルが一斉に寿命を迎えて廃棄されると環境負荷が高くなるとの指摘は、以前からあります。それを受けて太陽光パネルのリサイクル技術も開発が進められてきました。
国もこの問題を認識しており、経済産業省と環境省が太陽光パネルのリサイクルを義務化するべく準備を進めている状況です。
主にリサイクルされるのは、太陽光パネルの表面やモジュール部分に使用されているガラスやシリコンで、これらをリサイクルするとまた太陽光パネルの製造に使うことができます。環境保護に最も関心が高いEUではすでに太陽光パネルのリサイクルは義務化されており、アメリカでも州によっては義務化が始まっています。日本でも大量の太陽光パネルが寿命を迎えるため、リサイクルを推進することは太陽光発電のさらなる発展に寄与するでしょう。
家庭でできる地球温暖化抑制

太陽光発電当初、家庭用で普及が進みました。環境に優しい自家発電技術であることが受け入れられたわけですが、それよりも光熱費を削減できることが魅力に見えた部分もあると思います。それを補助金が後押しして今も普及が進みつづけています。
家庭でできる地球温暖化抑制ということで、まずは家庭用太陽光発電のあるべき方向性について解説したいと思います。
屋根の上を太陽光発電所に
ほとんどの住宅にとって、屋根の上はデッドスペースです。屋根の上を物置にしたりといった活用法はほとんど見かけません。しかも屋根には太陽光が直接当たるので、太陽光発電には好適です。
以前と比べると屋根に太陽光パネルがついた家を見ることは多くなりましたが、まだまだ半数にも満たない状況です。このデッドスペースをいかして太陽光発電が普及すれば、発電能力が増していくことでしょう。
蓄電池でさらなる省エネ、脱炭素
家庭用の太陽光発電は蓄電池との相性が良く、電力の完全自給自足も可能です。あくまでも理論的な話ではありますが、日本中の家庭が電力の完全自給自足を実現すれば、現在海外から大量に輸入している天然ガスなどの輸入量を大幅に抑えることができるため、日本がエネルギー大国になることも可能です。
蓄電池にはその可能性が秘められているので、これから太陽光発電を導入する方は蓄電池とセットで導入することをおすすめします。
EVとの併用でも脱炭素は実現できる
先ほど紹介した太陽光発電と蓄電池のモデルですが、この蓄電池の代わりにEV(電気自動車)を用いることもできます。EVには大きなバッテリーが搭載されているので、それを家庭用の蓄電池代わりに利用できるわけです。
このモデルはV2H(Vehicle to Home)と呼ばれるもので、EVだけでなくPHEV(プラグインハイブリッド車)でも導入可能です。近年では電気代だけでなくガソリン代が高騰しており、さらに2024年12月に国の補助金が期限切れとなるため、2025年はさらなるガソリン価格の高騰が懸念されています。
V2Hではクルマを走らせるための電力を太陽光発電からも供給できるため、クルマを維持するためのコストも削減できます。しかも脱炭素に大きく前進できるモデルなので、V2Hも今後普及が期待されています。
自家消費による持続可能な太陽光発電モデル
家庭でできる持続可能な太陽光発電モデルとして期待されているのが、自家消費モデルです。太陽光パネルで発電をして家庭内ですべて消費するモデルで、そのためには太陽光発電と蓄電池の組み合わせが必要です。
自家消費型の太陽光発電で得られるメリットは、主に3つあります。
①持続可能である
太陽光が降り注ぎ続ける限り、自家消費モデルには持続可能性があります。もちろん太陽光パネルやパワーコンディショナー、蓄電池などが寿命を迎えるため機器の更新といったメンテナンスは必要になりますが、このシステム全体が稼働し続ける限り電力会社にほとんど依存しない電力供給モデルを維持することができます。
②電気代高騰への生活防衛
エネルギー価格の高騰や円安のせいで、電気代の高騰が止まりません。関西地区など原発の再稼働が進んでいる地域では高騰が止まりつつありますが、まだまだそれが全国的な動きにはなっていないのが現状です。
太陽光発電はシステムの導入時に費用が発生するものの、その後のエネルギー源である太陽光は無料です。これが大きなポイントで、無料で手に入るエネルギーで電力をまかなうことができるので、電気代高騰への生活防衛策になります。
すでに解説した自家消費モデルを構築すれば電力会社から購入する電力量は大幅に少なくなる、もしくはゼロにできるため、今後さらに電気代が高騰しても受ける影響は軽微です。
③災害時の自立運転
近年では太陽光発電の普及が進んでいるおかげで、災害の被災地で太陽光発電が活躍しているニュースを見聞きすることが多くなりました。蓄電池が普及していなかった東日本大震災の当時であっても自立運転モードで昼間に携帯電話の充電をしたり最低限の家電を使えたといったことが話題になりましたが、蓄電池が普及し始めている今ではさらに太陽光発電が災害被災地で活躍することでしょう。
企業が取り組める地球温暖化抑制

企業にとっても、太陽光発電を導入することが大きなメリットになります。このメリットをいかして多くの企業が太陽光発電を導入していけば、さらなる地球温暖化抑制効果が期待できます。
屋上や遊休地を太陽光発電所に
家庭では屋根の上がデッドスペースになっていたため、そこに太陽光パネルを設置することにメリットがあるわけですが、企業にもデッドスペースはたくさんあります。
社屋や工場などの屋上は同じくデッドスペースですし、企業の敷地内や所有地に活用できていないスペースはまだまだあります。こうしたスペースに太陽光パネルを設置すれば、「何も生み出さないスペース」が発電所になります。
家庭用の場合は屋根に設置することが大半ですが、地面に直接設置できる「野立て」も可能なので、工場の跡地や郊外にある活用の難しい所有地などを発電所として利益を生み出すスペースに変えることができます。
自家消費モデルで電気料金高騰に備える
電気代による影響は、企業にとっても同じです。工場などがあって電力消費量の多い企業だと、なおさらでしょう。先ほど自家消費型の太陽光発電は電気代高騰に強いと述べましたが、企業にとっては電気代の問題がより大きいため、自家消費モデルを導入する事例が急速に増えています。
また、自家消費モデルを導入すると「うちの会社は再生可能エネルギーで製品を作っています」とアナウンスすることができるため、企業イメージの向上や後で解説する投資適格を得られることにもつながります。
今後、企業にとっての太陽光発電は自家消費モデルが主流になっていくことが確実です。
自己託送でも自家消費モデルを実現可能
企業が太陽光発電に取り組む場合、電力消費地(社屋や工場など)と同じ敷地内に太陽光パネルを設置する必要がありました。そうでないと太陽光パネルからの送電ができないからです。これだと遠隔地にある所有地などを有効利用しにくいため、現在では自己託送というモデルが確立しています。
自己託送とは、発電地と消費地が離れている場合であっても同じ企業であれば公共の送電網を使って送電が可能で、それを自家消費と見なすことができる仕組みです。この自己託送があるおかげで、遠隔地にある発電施設を自社の発電施設と見なすことができるため、企業にとっての太陽光発電導入の選択肢がぐっと広がりました。
PPAモデルなら初期費用不要
企業にとってとてもメリットが大きい太陽光発電ですが、やはりネックになるのが導入費用です。太陽光パネルの価格が安くなったとはいえ、企業が導入する場合は規模が大きいため、初期費用だけでも相当な金額になります。中小企業こそ太陽光発電導入のメリットが大きいのに、これだと導入できる企業が限られてしまいます。
そこで知っておきたいのが、PPAモデルです。PPA事業者と呼ばれる太陽光発電の設置業者が費用を負担し、活用したいスペースがある中小企業などに対して機器を設置し、保守や運用をする仕組みです。
この仕組みを利用すればデッドスペースを発電所にしたい企業は費用負担の必要がなく、無料で太陽光発電を導入できます。PPA事業者にとっては発電事業をするためのスペースが得られるため、双方にメリットがあります。
ESG投資、SDGsの時代にふさわしい企業価値を創出
SDGsは広く一般にも知られるようになった第三者評価基準です。「持続可能であること」が評価基準となり、SDGsに資する取り組みをしている企業は企業価値が高いと評価される時代になりました。
これをさらに掘り下げたのが、ESG投資の概念です。E(環境)、S(社会貢献)、G(企業統治)の3要素を組み合わせたもので、1つめにあるEの環境への取り組みにはもちろん太陽光発電の活用も含まれています。欧米ではこのESGそれぞれの取り組みに積極的ではない企業は投資不適格であると見なされ株主が離れてしまうといったことが起きています。つまり、太陽光発電の導入は企業の生き残りにも不可欠になってきているということです。
「企業のイメージアップになる」という漠然とした価値ではなく、生き残りに直接的なメリットをもたらす太陽光発電は、今後企業にとって必須の事業となっていくかもしれません。
税制優遇メリットも活かせる
太陽光発電の導入には税金面でのメリットもあります。太陽光発電に関連する設備は減価償却の対象なので、減価償却費を経費として計上可能です。利益を生むための機器を購入して、その費用は節税に資するのですから、企業にとっては一石二鳥のメリットがあります。
しかも、一般的には数年もしくは十数年をかけて減価償却費を計上できるのですが、条件を満たせば即時償却といって全額を1年で計上できる可能性があるため、利益が上がりすぎた中小企業が年末に太陽光発電を導入して課税所得を大幅に圧縮するといったことも可能です。
まとめ
太陽光パネルは地球温暖化の抑制に効果があるのか?というテーマに対して、懐疑論から真実まで解説してきました。以前であればそこまで懐疑論が拡散することはなかったのですが、これも太陽光発電の普及が進んで「社会の一員」になったことの証左かもしれません。
今後も懐疑論はトンデモ理論も含めて登場してくることと思いますが、太陽光発電を含む再生可能エネルギーが脱炭素や環境保護に資することは間違いありません。正しい情報と知識をもって判断し、地球温暖化を食い止めるために何ができるかを考えていきたいものです。