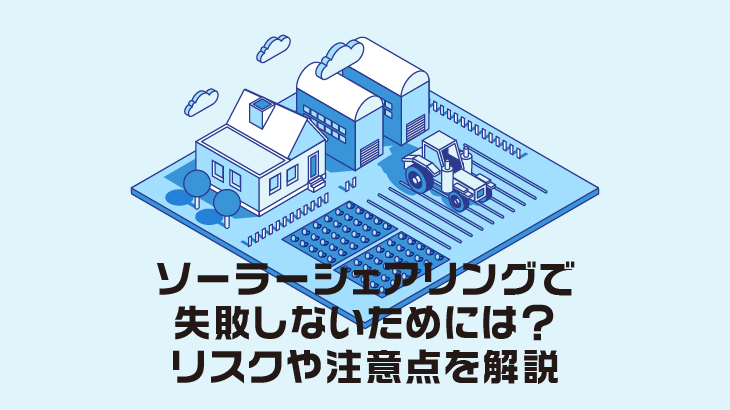ソーラーシェアリングは、農業設備の電気料金削減効果などメリットに注目の集まる制度ですが、失敗するリスクやデメリットもあります。これから始める場合は、失敗事例をしっかりと把握した上で準備することが大切です。
今回は、ソーラーシェアリングで失敗しないためのポイントやリスク、注意点について詳しくご紹介します。
ソーラーシェアリングで失敗するケースとは?

ソーラーシェアリングは、耕作放棄地の有効活用につなげることなどを目的として始まった制度で、農地転用ができない土地でも太陽光発電事業を導入できます。光熱費の負担軽減や、売電収入によって収入軸を増やすなどメリットが期待できる運用方法です。しかし安易な導入は失敗しかねません。まずは、ソーラーシェアリングで失敗するケースを紹介します。
一時転用が認められないことによる事業の停止
ソーラーシェアリングの一時転用が認められない場合、事業を停止しなければいけません。
一時転用は、農地を一定期間別の用途で活用するための許可制度のことを指します。農地の上にソーラーシェアリング用の太陽光発電設備を設置するには、一時転用の手続きを行い、許可を得る必要があるのです。
万が一、許可が取り消されてしまうと事業を継続できないため、ソーラーシェアリングの費用を回収できず大きな損失が生じてしまうことになります。ソーラーシェアリングを始める際は、想定しているケースで一時転用が可能か確認しましょう。
農地転用については関連記事でも解説しています。
農作物の価格変動による事業リスク
農業を営んでいる方ではなく、太陽光発電事業の一環としてソーラーシェアリングを検討しており、農業が初めてだという方は注意が必要です。農業には、農作物の価格変動にリスクがあります。
太陽光発電事業は、FIT制度やFIP制度を活用し、売電収入を得ることが可能です。とくにFIT制度の買取単価は固定のため、収支の見通しが立ちやすいことに魅力を感じている方も多いでしょう。
一方、ソーラーシェアリングは農業を主体とした事業で、農作物の売上も重要です。天候や市場での競争などといった要因から、農作物の価格が変動する可能性があります。輸入品との価格競争が生じることもあり、事業としての脅威は決して少なくありません。
農作物の収量や品質低下リスク
農作物の収量や品質が、ソーラーシェアリングの設置によって低下してしまう可能性もあります。農業に影響が出るだけでなく、収量が少なすぎると一次転用許可が取り消される恐れもあり、事前の対策や分析が重要です。
ソーラーシェアリングは農地の上に支柱を立てて、支柱に固定された架台の上にソーラーパネルを設置します。作物への影響は限定的とはいえ、日光が部分的に遮られるため収量や品質の低下を招く可能性があるのです。
あらかじめソーラーシェアリングに適した作物を選定したり、対策を施したりする必要があります。
黒字化できず撤退するリスク
ソーラーシェアリング用の太陽光発電設備は、出力50kW程度で1,500万円前後の費用がかかります。通常は融資を受けて購入し、毎月返済する必要があります。
初期費用の回収は、通常10年~15年程度で完了できるといわれています。また営農と太陽光発電の売電で得た収益のほか、電気料金の削減によって余った予算を、初期費用の回収に充てるのが一般的です。
しかし、前段で触れたような農作物の価格変動、収量・品質低下による売上減少、発電量の低下といったリスクがあるため、想定通りに費用回収ができない可能性もあります。
撤退した場合の出口が少ない点もデメリットの一つです。通常の太陽光発電事業であれば、太陽光発電を撤去して土地を売ったり、中古の太陽光発電所として売りに出したりすることができます。しかし、ソーラーシェアリングは農地で行うため、用途の限られた土地を活用するのが難しかったり、中古の太陽光発電所としても運営が難しかったりして買い手が付かない可能性が高いです。
黒字化を目指すためには、事業計画の作成、太陽光発電の発電量に関するシミュレーションなどを丁寧に進める必要があるでしょう。
周辺農家からの理解が得られないことによるトラブル
周辺農家への配慮が不足していたり、理解を得られていなかったりすると、トラブルに発展する恐れもあります。
自身の農地と他の農家が所有している土地が、隣接していることは珍しくありません。事前の説明などを行わずにソーラーシェアリングを導入した場合、太陽光パネルによって発生する影で作物に影響が出たり、不信感を持たれたりします。
このような誤解や不信感などを解決せずにソーラーシェアリングを続ければ、のちのち大きなトラブルに発展し、事業を継続できない状態に追い込まれてしまう可能性もあります。ソーラーシェアリングのための一次転用の条件には、隣接する農地の所有者の理解が必要だとされているからです。
ソーラーシェアリングを導入する場合は、事前の説明を行うほか、隣地に迷惑をかけないための対策を施すことが重要です。
後継者・労働者不足による廃業リスク
後継者不足による廃業リスクは、ソーラーシェアリングにおいても存在します。先述のとおり、ソーラーシェアリングの初期費用回収までには15年程度かかります。
農業を営む方によっては、体力的な理由などから15年以上ソーラーシェアリングを運用させられないケースもあり得ます。農業が主体の事業であるため、後継者を見つけるのも、そのノウハウを継承するのも一苦労です。費用回収を完了させる前に廃業せざるを得なくなれば、ソーラーシェアリングの失敗につながります。
また農業における雇用問題はそのままソーラーシェアリングでも当てはまります。農業が主体の事業である以上、初めて農業に参入数する方は労働者の確保に苦労する可能性がゼロではありません。
ソーラーシェアリングを始める際は、15年以上継続できるかどうか、継続できなくなった場合の対策についても検討しておくことが大切です。
ソーラーシェアリングにメリットはある?

ここまで紹介したリスクを考慮すると、導入すべきなのかどうか悩んでいる方も多いことでしょう。続いては、ソーラーシェアリングにどのようなメリットがあるのか、わかりやすく解説します。
電気代の削減効果を得られる
ソーラーシェアリングで発電した電気は農業用設備などへ供給できるため、電気料金削減効果を得られます。
ソーラーシェアリングでは、他の太陽光発電設備と同様に太陽光パネルから日光を吸収し、電気へ変換できます。発電した電気は、あらかじめ配線接続しておいた機器や設備で自家消費することが可能です。
自家消費率を高めれば買電量(電力会社から供給された電気の購入量)を削減できるため、電気料金の削減につながります。
近年、電気料金は値上げ傾向にあり、節電のみではコスト削減が苦しくなってきているケースもあります。光熱費の負担で悩んでいる農家の方は、電気料金削減を目的としてソーラーシェアリングを検討してみるのもおすすめです。
売電収入による経営の安定化を目指せる
ソーラーシェアリングで売電収入を得られる点は、経営の安定化を目指す上でメリットの大きいポイントです。ソーラーシェアリングは自家消費を基本として想定されていますが、FIT認定を受けていれば、もちろん余った電力を売電することもできます。
農業は天候などの影響を受けやすく、経営を安定させるのが難しい側面もあります。そこでソーラーシェアリングを導入しておけば、収益源を2つに増やせるため、天候等によって農業の収益に影響が出た場合も、太陽光発電の収入で事業をカバーできます。
別途土地を購入せずに始められる
現在所有している農地の上で太陽光発電事業を始められるのは、ソーラーシェアリングならではのメリットです。
通常、太陽光発電事業を始める際は、発電に適した土地を取得し、造成工事などを行って設備を導入していきます。土地の取得費用は大きな負担となるでしょう。ソーラーシェアリングは農地の上に設備を設置できるため、農家の方にとっては導入検討しやすい運用方法といえます。
ソーラーシェアリングで失敗しないためには

ここからは、ソーラーシェアリングで失敗しないために押さえおくべきポイントを解説します。
作物の種類や特性を調べた上で選ぶ
ソーラーシェアリングに適した作物の種類を調べ、特性に適した形でパネルを設置しましょう。
ソーラーシェアリングは、農地の上に太陽光パネルを設置するため、部分的に影ができてしまいます。とくに日当たりのいい場所で育つ陽生植物は、ソーラーシェアリングの影響を受けやすく、収量低下のリスクが大きいです。
一方、半陰生植物や陰生植物(日陰の多い場所でも育ちやすい植物)は、ソーラーシェアリングの設置されている場所でも育ちやすいため、相性がよいといえるでしょう。たとえば、半陰生植物のほうれん草や小松菜、陰生植物のふきやにら、せりなどは、日射量の少ない場所でも育つため、安心してソーラーシェアリングを導入できます。
農業をおろそかにしない
ソーラーシェアリングの主体はあくまでも農業です。農業をおろそかにすると、一次転用の許可が取り消される可能性があります。
ソーラーシェアリングで一時転用の許可を受るとき、許可を得られれば終わりではありません。3年ごとに再申請を行わなければならず、毎年収穫状況の報告も求められます。
地域の平均単収の8割を下回ってしまうと、一時転用を取り消される可能性があります。農業の経営安定化へ力を入れることも欠かせません。(地域平均単収:10aあたりの予想される収量)
ソーラーシェアリングの専門業者へ相談する
ソーラーシェアリング事業を始める際は、専門業者へ相談すると安心です。
ソーラーシェアリングは、一般的な太陽光発電設備と異なる構造が必要で、農作物の成長が第一優先となる関係から運用方法にも差が生じます。一般的な地上設置型太陽光発電と同じイメージで準備してしまうと、うまくいきません。
太陽光発電の中でもソーラーシェアリングに特化したサービスへ相談すれば、営農を前提としてサポートしてもらえます。作物との相性を考慮した設置方法や自家消費で削減できる電気代のイメージなど、幅広い視点から助言を受けられるでしょう。
株式会社和上の郷では、ソーラーシェアリングの提案から設計・施工、維持管理まで総合的にサポートしております。ソーラーシェアリング事業を検討している方や少しでも気になった方は、ぜひお気軽にご相談ください。
補助金制度が活用できないか確認する
ソーラーシェアリング事業の初期費用負担で悩んでいる場合は、補助金制度を活用できないかどうか調べてみるのもおすすめです。
国は、事業者向けに再生可能エネルギー関連の補助金事業を実施しています。中には、ソーラーシェアリング関連の補助金制度があり、初期費用負担を軽減できる可能性があるのです。
たとえば、令和6年度予算で実施された「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」は、ソーラーシェアリングも補助対象設備でした。要件を満たした場合は、対象経費に対して2分の1まで補助金を交付してもらえます。補助金制度は同じようなものが翌年度も実施されることがあるので、申込期日を逃さないよう調べておきましょう。
出典:「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」(環境省)
ソーラーシェアリングの施工販売業者を選ぶポイント
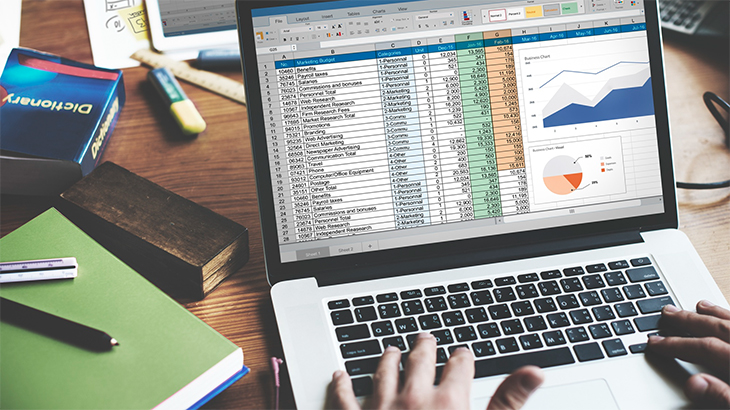
ソーラーシェアリングの導入時には、専門の施工販売業者へ相談することが大切です。ここでは、ソーラーシェアリングの施工販売業者を選ぶポイントを解説します。
ソーラーシェアリングの実績を調べる
施工販売業者を比較検討する際は、ソーラーシェアリングの施工実績を確認してみましょう。前半でも解説したようにソーラーシェアリング事業における太陽光パネルの設置は、事業が成功に大きくかかわります。設置の仕方によってパネルによる遮光率も変わってしまうため、作物の成長に必要な光を考慮しなければならないのです。
ソーラーシェアリングの施工および営農に関する実績豊富な施工販売業者へ相談できれば、こうした事情をよく理解した提案を受けられます。
見積もり内容を確認する
ソーラーシェアリングを含む太陽光発電の初期費用は、施工販売業者によっても変わります。複数の施工業者に見積もりを依頼して比較することで、安いところを見つけやすくなるでしょう。
一括サポートしてもらえるかどうか確認する
施工販売業者のサービス内容を比較する際は、メンテナンスなども含めて一括サポートしてもらえるかどうか確認しておきましょう。
太陽光発電設備は劣化します。故障すれば交換や修理が必要ですし、メンテナンスや定期点検も欠かせません。初期費用だけでなくランニングコストも考慮しなければならないのが、太陽光発電事業の悩ましい点です。
サービス内容の充実した業者であれば、太陽光発電設備の設計から部材の調達、施工、さらに点検やメンテナンス、修理交換などといった保守管理に関するサポートも提供してくれます。都度調べて依頼するのはかなりの労力が必要です。一括サポートしてくれる業者を探しましょう。
ソーラーシェアリングの失敗を避けるには施工販売業者選びも重要!
ソーラーシェアリングの失敗を避けるためには、ソーラーシェアリングと作物の相性をしっかりと調査し、綿密な事業計画を立てる必要があります。また太陽光発電設備を導入する際は、ソーラーシェアリングの実績が豊富な施工販売業者へ依頼することも大切です。
ソーラーシェアリングが失敗しないか不安な方や、ソーラーシェアリング事業について関心を持ち始めた方は、今回の記事を参考にしながら和上の郷の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
農地所有適格法人 株式会社和上の郷では、ソーラーシェアリングを実施しており、太陽光発電および営農に関するノウハウや専門知識・経験を持っております。ソーラーシェアリングの提案から設計、施工、保守管理まで一括サポートが可能です。
また作物の販売先を確保しているため、初めて農業に参入することで販路開拓に悩んでいる方にもおすすめです。少しでも気になった方は、まずお電話やメールからお気軽にご相談ください。