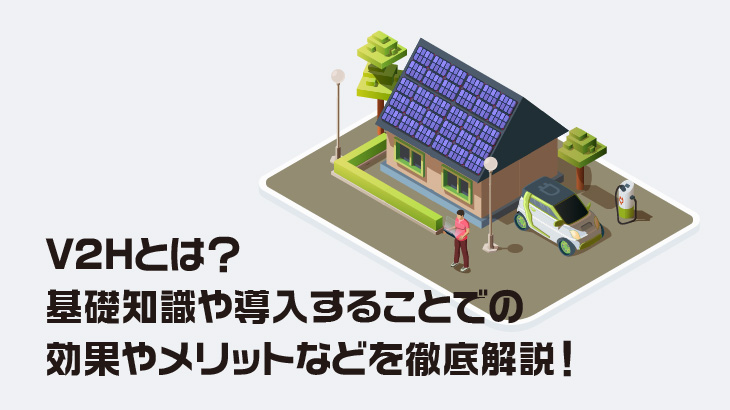EV(電気自動車)と太陽光発電が設置された住宅を組み合わせることにより、V2Hという理想的なエネルギーシステムが出来上がることは、すでにV2Zを理解している人の間では半ば常識になっています。しかし、理想的なエネルギーシステムである一方でネックとなるのが高額になりがちな導入費用です。
V2Hの良さは分かっているものの、費用の問題でなかなか踏み出せない。そんな人にお伝えしたいのが、V2Hの補助金に関する情報です。補助金をうまく活用すれば導入費用を抑えてオトクに設置することができ、設置後はそのメリットを長く享受できます。
それでは、V2Hの補助金に関する情報や注意点、漏れなく補助金を受け取るために必要な知識などを網羅していきましょう。
V2Hについてのおさらい

V2Hの補助金に関する解説をする前に、V2Hについての基本をおさらいしておきましょう。なぜここまでメリットがクローズアップされているのか、どんなメリットがあるのかといった点を簡単に押さえておきたいと思います。
V2Hってなに?
V2Hは、「Vehicle to Home」の略です。Vehicleとはクルマのことで、Homeは家です。「クルマから家へ」という意味ですが、これは電力をクルマから家へという意味合いです。近年、太陽光発電を導入している家庭で蓄電池を導入する事例が増えています。夜間や悪天候の日など太陽光からの電力が得られない時間帯を補うために蓄電池を設置し、電力の自給自足を目指す仕組みです。
EV(電気自動車)には、大容量のバッテリーが搭載されています。そして、EVを使っていない時は自宅の駐車場に停めてあるのが普通です。このEVのバッテリーを蓄電池として活用して、電力の自給自足や災害時の非常用電源などに役立てるというのが、V2Hの基本的な考え方です。
しかもEVを常に充電している状態になるため、日常の移動にも使えるためメリットはとても大きいです。
V2HはEVのメリットを最大化する
先ほども少し述べたように、V2HはEVを充電しつつ蓄電池としても使用するため、いつでも満充電に近い状態です。そのため移動に使いたい時はスムーズに使えますし、夜間などの時間帯を活用して安い電力を選んで充電します。
EVは充電する時間帯によってエネルギーコストが変動します。V2Hでは安い夜間の電力を優先的に利用するため、EVのトータルコストが大幅に安くなる仕組みになっています。
また、電力需要のピークシフトも見逃せません。家庭内の電力需要がピークになる時間帯は買電量が多くなります。しかし、多くの場合電力需要がピークになる時間帯は昼間や夕方などでしょう。その時間帯は電気代の単価が高い時間帯なので、蓄電池に安い夜間の電力を蓄えておき、電気代が高い時間帯に使うわけです。
これにより、自宅に蓄電池を導入したのと同じメリットが実現します。
V2Hは太陽光発電とも相性抜群
もうひとつ、V2Hは太陽光発電とも相性がとても良く、EVと太陽光発電を組み合わせないと真のメリットは発揮されないとまで言われています。
太陽光発電は無料で得られる電力です。昼間にEVを使わない場合は太陽光発電からの充電ができるため、とても安いコストでEVを走らせることができます。
また、V2Hには倍速充電機能といってEVの充電スピードを速められる機能があります。これによって電力会社からの供給電力と太陽光発電による電力の「W充電」で、充電スピードを最大で2倍にできます。
すぐにEVを使いたい時にバッテリー残量が少ないのはとても不便ですが、V2Hはそういった場面にもしっかり対応しています。
メリットいっぱいのV2H、最大のネックは導入費用
とてもメリットの多いV2Hですが、やはり最大のネックになるのはお金の問題です。そもそも太陽光発電やEVも決して安いモノではありませんし、その上V2H機器を取り付けるとなると、さらに100万円前後の費用が発生します。
内訳は、V2Hの充放電設備の本体価格として70~80万円、そしてそれを設置するための工賃が30万円程度です。これらを合わせると、100万円から110万円程度となります。
この費用負担を何とかしたいという人にとって朗報なのが、補助金の存在です。それでは次章からはV2Hの補助金について解説を進めていきましょう。
国によるV2Hの補助金を活用して導入費用問題を解決

国が設けているV2H補助金について、制度の概要や主旨、要件などについて解説します。地方自治体のよってはV2H補助金を設けているところもあるので、それについては次章で解説します。
V2Hの導入には補助金制度がある
V2Hを導入するにはV2H充放電設備を設置する必要があります。国の補助金制度では、この設備の設置に対して補助金制度が設けられています。
予算の規模は50億円程度、申請期間は2024年5月からを予定しています(当記事は2024年4月に作成)。詳しくは後述しますが、この50億円の予算を使い切った時点で令和6年度のV2H補助金は終了となります。
V2H補助金の概要
国によるV2H補助金には、それぞれ上限が定められています。設備費(本体価格)と工事費に分けられています。それぞれの上限金額は、以下のとおりです。
| 補助の対象 | 上限金額 |
|---|---|
| 設備費(本体価格) | 75万円(補助率:2分の1) |
| 工事費(個人の場合) | 40万円 |
| 工事費(法人の場合) | 95万円 |
また、外部給電器も補助金の対象となっています。外部給電器とは、EVなどバッテリーのあるクルマから電力を取り出す装置のことです。
令和6年度のV2H補助金では、外部給電器に対しても上限50万円の補助金が設けられています。
V2H補助金の必要条件
V2Hの補助金には、一定の要件があります。国としてもV2Hを今後広めていくために情報収集をしたい意向を持っており、また災害時にはV2Hを導入している家庭に協力してもらうことを想定しています。V2Hの補助金にはこうした目的に関わりのある要件が定められています。
1つめの要件は、設置に関する情報提供です。補助金を受給した場合、V2Hの設置に関する情報提供の要請があったらそれに応じる必要があります。といってもそこまで重いものではなく、アンケートのようなものに回答するだけで良いようです。
2つめの要件は、災害時の協力です。これはV2Hのメリットを設置している家庭だけでなく、広く社会にも還元してもらう条件です。災害時などに要請があったら、可能な範囲で電力供給に協力することが求められます。この要件を満たすため、原則として補助金を受けて設置したV2H機器は最低5年間は許可なく撤去できないこととなっています。
V2H補助金は地方自治体にもある
前章で紹介したのは、国によるV2Hの補助金制度です。次に、ここでは地方自治体によるV2H補助金にも言及したいと思います。地方自治体の中にはV2Hに対する補助金を設けているところがあるので、一度調べてみる価値はあると思います。
東京都の手厚いV2H補助金の事例
新築住宅の屋根に太陽光パネルの設置を義務付ける条例で知られる東京都は、V2Hについても手厚い補助金制度を設けています。V2Hと太陽光発電、EVが揃っている場合は補助金の上限が100万円になります。
組み合わせによっては実質的にほとんど無料でV2H機器を取り付けられることになるため、これはかなり手厚いといえます。
東京都は小池知事の強い意向によって太陽光発電や環境設備に対する補助金を手厚くしているため、今後も同知事の任期が続く限りはこうした制度が拡充されていくと思われます。
都道府県、市区町村のV2Hはどうやって探す?
前述の東京都のように、お住まいの地方自治体でV2Hの補助金制度が設けられているかどうかは、ネットで簡単に調べることができます。
最も簡単な方法は、「V2H 補助金 〇〇(お住まいの自治体)」という検索ワードで調べてみると、何らかの情報がヒットすると思います。この場合、自治体名は都道府県と市町村の両方を試してみると良いでしょう。
例えば、東京都と並ぶ大規模な自治体として大阪府の情報を調べてみると、令和6年度の補助金制度はありませんでした。しかし令和4年度までは補助金があった模様で、V2Hの充放電設備に対して最大75万円の補助が受けられたようです。
このように自治体の補助金制度は年によって変化するので、該当するかどうか最新の情報で調べることが重要です。
国の補助金との併用が可能か要確認
国とお住まいの自治体の両方にV2H補助金の制度がある場合、併用することは可能です。ただし、同じ設備に対して重複して補助金を受けることはできないので、書類上でも明確に分かれている必要があります。
補助金が複数ある場合は併用不可という自治体もあるので、自治体の補助金制度を利用する場合は、併用の可否についても要確認です。
V2H補助金の注意点

V2H補助金を滞りなく受給するために、知っておくべき注意点について解説します。補助金の申請は相手が「お役所」だけに融通が利かない部分もあるため、これらの注意点をしっかり留意しておきましょう。
同じ補助金制度であっても毎年内容が変わる
これはV2Hの補助金に限ったことではありませんが、行政が設けている補助金制度は年単位内容が変わります。前年のうちに予算を確保し、その予算を執行する形で実施されるため、前年に政治的な理由で予算を確保できなければ、補助金制度そのものがなくなることもあります。そして、再び政治的な理由によって復活するといったこともあります。
補助金制度が継続したとしても、その内容は予算次第です。国が示している方向性と合致する分野であれば補助金の内容が手厚くなり、徐々にその内容が薄くなっていくというのがよくあるパターンです。
毎年同じとは限らず、翌年もあるとは限らないというのが補助金制度です。それだけに、手厚い制度があるうちに受給しておくのが最も得策です。
申請受付には有効期間がある
これもV2H補助金に限った話ではありませんが、補助金の申請には受付期間があります。その受付期間を過ぎると、たとえそれが1日だけであっても受け付けてはくれません。このあたりも民間企業との違いかもしれませんが、それをしっかりと踏まえて日数に余裕のある行動をするべきでしょう。
予算がなくなったら今年の補助金は終了
先ほど申請受付期間を過ぎると申請できないと述べましたが、状況によっては申請期間内なのに受け付けてもらえないことがあります。それは、予算を使い切ってしまった時です。役所は確保した予算を執行しているだけなので、予算がなくなったら執行も終了です。人気のある補助金は期間内であっても前倒しで終了になることがしばしばあります。
令和6年度の補助金は5月から申請受付が始まります。V2Hの導入を検討しているのであれば、申請受付が始まった直後から動くというスピード感でもちょうど良いかもしれません。
地方自治体の場合は制度が異なる
地方自治体はそれぞれ独立した行政機関です。どんな分野に補助金を出すかは自治体の事情や方針によって異なるため、日本全国どこでもV2Hの補助金があるとは限りません。
地域によっては都道府県に補助金がなくても、市町村に補助金があることもあります。
先ほど都道府県名だけでなく市町村名も検索してみるべきと述べたのは、そういったケースがあるからです。
V2H補助金を確実に受け取るために

相手が「お役所」で、手続きにも正確性が求められるV2H補助金。それを自分でやることに不安を感じる人は多いと思います。そんな時に頼りになるのが、太陽光発電やV2Hなどを取り扱っている施工店、販売店です。
補助金に強い施工店、販売店を探そう
V2Hは設置しなければ使用できない機器なので、必ず施工店に依頼することになります。その施工店を探すのにあたって、補助金の申請などにしっかりとノウハウやサービスがあるかをチェックしましょう。
各社のホームページにはサービスの内容が詳しく書かれているので、その中に補助金申請についての言及があるか、また問い合わせをする際にも補助金を受給したい旨を伝えてそれに対してどんなサービスを受けられるのかを確認するのが良いでしょう。
曖昧な回答をするような施工店、販売店だと補助金に対するノウハウがあまりない可能性もあるので、補助金に対してしっかりと回答してきている業者がおすすめです。
施工店、販売店に任せるメリット
最後に、信頼できる施工店、販売店に任せることで得られる2つのメリットにも触れておきましょう。
1. 漏れがなく確実性が高い
最も大きなメリットは、漏れがないことです。「お役所」が相手の手続きだけに漏れや不備があると補助金を受けられないような事態も考えられますが、プロに任せることでその不安が解消されます。
「不安の解消」も、実は大きなメリットです。本当に大丈夫かと思いながら手続きを進めるのはストレスになりますし、それで本当に受給できなかった時の落胆はとても大きいでしょう。
そんな時に頼りになるのが、プロです。
2. 施工から補助金申請まで任せられる
補助金の申請に関するサービスを受ける場合、それを依頼するのはV2Hの施工を依頼するのと同じ業者でしょう。同じ業者であれば設置する機器に関する情報を持っていますし、ひとつの窓口で進めることができます。
まとめ
とてもメリットの多いV2Hの補助金について、国や地方自治体の情報について解説しました。滞りなく補助金を受給するための注意点や施工店、販売店の探し方についても解説しましたので、プロに任せられることはプロに任せて、しっかり受給できるように手続きを進めてください。
弊社和上ホールディングスでは、全量自家消費型太陽光発電の設計から部材調達、施工・保守運用まで一括サポートしています。累計15,000棟の実績によって培われた技術とノウハウがあるので、設置予定場所や予算に合ったプランをご提案いたします。少しでも気になった方は、この機会にお電話やWebフォームよりお気軽にご相談ください。