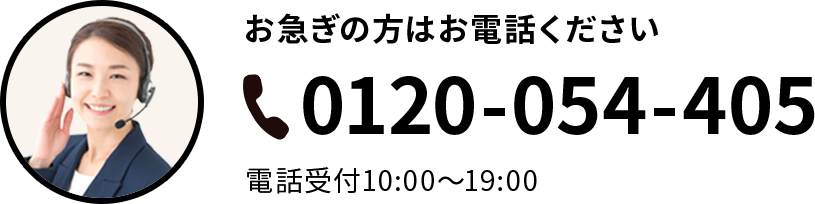近年、ESGや脱炭素経営、SDGsを取り入れたサステナビリティな事業活動が求められています。またSXは、企業と社会のサステナビリティを両立させる新しい概念で要注目の内容です。
そこで今回は、SXの意味や注目されている背景、GXやDXとの違いについて詳しくご紹介します。脱炭素経営に向けて関連情報を調べている方などは、参考にしてみてください。
SXとは?

SX(Sustainability Transformation:サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、社会と企業のサステナビリティを両立・同期させるための経営、事業変革のことです。
サステナビリティ(持続可能性)は、環境・経済・社会に配慮された活動に取り組むことで、持続可能な発展を目指す考え方を指します。
経済産業省の「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会中間取りまとめ」によると、SXにおける社会のサステナビリティは、「将来的な社会の姿や持続可能性」を指す言葉として認識されています。
つまり、新型コロナウイルスやロシアによるウクライナ侵攻、地震をはじめとする災害といった不確実性の多い状況に備えながら事業に取り組むことに加え、環境や社会問題へ対応した経営にシフトしていくのが、社会のサステナビリティと言えます。
一方、企業のサステナビリティは、「企業の稼ぐ力の持続性」という意味合いで用いられているのが特徴です。例えば、自社の強みや優位性、企業価値を向上させながら中長期的に事業を継続および強化させていく取り組みが、企業のサステナビリティです。
このように、変化の激しい環境で中長期的に事業を発展させ、なおかつ持続可能な社会に向けた取り組みを両立させるのが、SXの主な目的です。
出典:経済産業省ウェブサイト
SXと類似用語(GX、DX)の違い

SXと似た用語にGXやDX、ESG、SDGsがあります。それぞれ環境や社会などに関する専門用語ですが、異なる意味で用いられています。以下に4種類の類似用語に関する概要を紹介します。
| GX | Green Transformation:グリーントランスフォーメーションの略称 経済の成長と環境保護を両立させる取り組み。日本政府では、GXの実現に向けたGX実行会議、官民学で連携しながら取り組むGXリーグなどさまざまな対策が行なわれている。 →GXは事業の発展と環境保護を両立させる取り組み。一方、SXは、事業の発展と環境に加えて社会問題の解決に向けた取り組みも含まれているのが違いのひとつ。 |
|---|---|
| DX | Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーションの略称 IoT技術・デジタル技術を用いながら、自社の業務フローなどを改善したりデジタルやビッグデータを活かした製品・サービスの展開などを進めたりしていく取り組み。 →DXは技術面での変革に関する考え方だが、SXは企業・社会の両面から持続可能な発展を模索していく概念という違いもある。 |
| ESG | Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字を合わせた用語 主な意味は、環境問題、労働や所得格差といった社会問題、自社の健全な管理体制の3点を軸にした経営を行なっているかを分析するための基準。 →企業にとってESGは投資家からの評価に関わる概念。SXは、社会の持続可能な発展を重視した企業活動で、ESGの評価向上にもつながる。 |
| SDGs | Sustainable Development Goals:サステナブル・デベロップメント・ゴールズの略称 持続可能な世界を目指す国際目標で、17のゴール、169のターゲットに分かれている。内容は気候変動対策や海や陸の資源保護、人権やジェンダー、経済発展など多岐にわたるのが特徴。 →SXは企業向けの考え方。一方、SDGsは国や企業だけでなく、個人にも求められているのが違いのひとつ。またSXを重視した事業活動は、SDGsの貢献につながる可能性がある。 |
GXやDXは、SXとは目的や対象の取り組みに違いがあります。また、ESG経営は投資家からの評価向上やブランド力アップにつながる取り組みで、SXと得られるものや目的が異なります。
SDGsは地球全体のさまざまな問題を解決するための目標で、企業だけでなく個人にも求められているのがSXとの違いと言えます。
なぜSXが注目されているのか

SXの概要を把握した方の中には、なぜSXに注目が集まっているのか疑問を抱いている方も多いかと思います。続いては、SXが注目されている理由についてわかりやすく解説します。
世界情勢の急激な変化に対応する必要がある
世界情勢の急激な変化に対応するため、SXを取り入れた事業活動へ取り組む企業も出てきています。
近年、2020年の新型コロナウイルスによる自粛や時短営業、リモートワークへの切り替え、事業の見直しをはじめとした影響のほか、ロシアによるウクライナ侵攻などによる燃料価格の高騰および物価高といった突発的で急激な変化が起こり続けている状況です。さらに、気候変動問題による食糧不足などのリスクも高まっています。
そのため、企業は従来のようなシステムではなく、不確実性の高い環境でも事業を継続し、なおかつ成長するための仕組み作りに取り組まなければいけません。
そこで、社会の不確実性に対応しながら持続可能な発展を続けるため、SXに注目が集まっていると考えられます。
自社の企業価値向上につながる
SXを通じた環境負荷軽減に向けた取り組みやサービス開発、エネルギーや社会問題の改善につながる事業活動などは、自社の企業価値やブランド力、信頼性の向上につながります。
前段で触れたように、新型コロナウイルスや気候変動問題と食糧不足、戦争による物価高、災害といったリスクが高まっているため、消費者もさまざまな社会問題に意識を向けています。
さらに、企業の信頼性や透明性などにも目が向けられている状況です。SXをはじめとした環境や社会に配慮された事業活動を続けることは、消費者からの信頼を得られる可能性があります。
また、投資家も企業の環境・社会に関する取り組みを基準に評価する傾向なので、投資先として選ばれたり評価を高めたりする上でも重要と言えます。
SXに必要なダイナミック・ケイパビリティとは

SXを実践する場合、何を基準・参考に進めればいいのかわからないところではないでしょうか。そこで注目すべき内容が、ダイナミック・ケイパビリティという理論です。ここからは、SXの実践に必要なダイナミック・ケイパビリティの意味やポイントについて解説します。
環境に合わせて変化しながら対応していく能力
ダイナミック・ケイパビリティとは、環境や状況の変化に合わせて自社を変革させていく力のことです。
SXを実践するためには、突発的な変化に対してスピーディに反応し、なおかつ対応していく必要があります。そのため、ダイナミック・ケイパビリティがSXを取り入れる上で重要とされています。
また、ダイナミック・ケイパビリティは、感知力(Sensing)と捕捉力(Seizing)、変容力(Transforming)という3つの能力に分かれているのが特徴です。
| 感知力(Sensing) | 自社に関わるリスク、トラブルを察知するための能力。 不確実性の高い環境で経営を継続させるには、何が起きているのかスピーディに情報を取得し、分析する力が必要。 |
|---|---|
| 捕捉力(Seizing) | 変革の必要なタイミングを捉えて既存の資産や知識、技術を再構成し、競争力を獲得する能力。 他社の模倣や既存のデータに頼るのではなく、今何が起きているのか理解し、変革の必要なタイミングで自社独自の技術や資産を再構築する必要がある。 |
| 変容力(Transforming) | 捕捉力によって獲得した競争力を活用するため、組織の刷新と変容を行なう力。 競争力を効率的に運用するには、組織を新しいものへ変える必要がある。そのため、変容力が重要とされている。ただし、1度に組織構造を変えるのはコスト面でも現実的ではなく、少しずつ目標とする組織に構築し直し、継続的に進めていくことが大切。 |
つまり、将来の変化につながる事象もしくは現状把握をスピーディに行なうためのシステムや組織づくり、競争力を獲得・強化するための能力などが、ダイナミック・ケイパビリティに求められている力です。
また、3つの能力を獲得できれば、変化への対応が必須のSXを軸にした経営へシフトすることも可能です。
自社のデータとデジタルの活用がポイント
ダイナミック・ケイパビリティを獲得・強化するためには、AIやビッグデータをはじめとする最新のデジタル技術を活用するのが重要です。
デジタル技術やシステムは、より迅速にデータを取得したり分析を行なったりする上で役立ちますし、分析力の向上による捕捉力の強化につながります。特にAIを活用したデータ分析では、変化の兆候を掴んだり予測したりできる可能性があるので、導入を検討しておきましょう。
SXへ取り組む際に押さえておくべきポイント
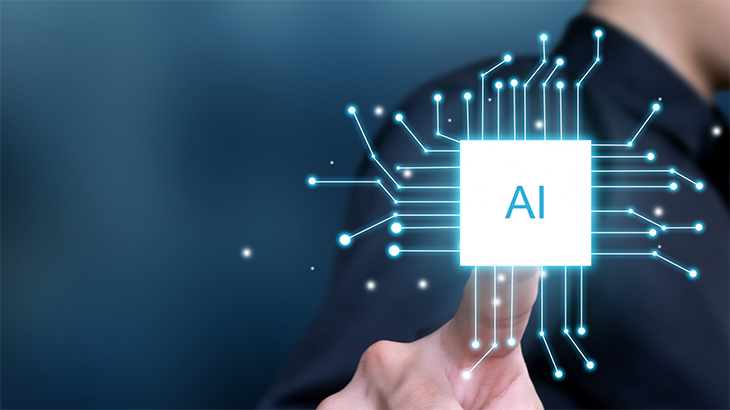
続いては、SXへ取り組む上で押さえておくべきポイントを解説します。
SXによって目指す姿を明確にする
SXへ取り組む際は、まず自社のあるべき姿・SXによって目指す姿を明確にしておく必要があります。自社の理想を明確にしなければ、SXの取り組みによってどのようなメリットを得られるのか、現時点で効果が出ているのか不明瞭なままです。
そのためSXを考える際は、環境や社会・人にどのような形で貢献できるか、持続可能な発展につながる事業活動とは何かを明確にしておきましょう。
長期的な視点で取り組む必要がある
SXへ取り組む場合は、短期的な目標作成だけでなく長期的な視点での対策、目標などを定めておくのが大切です。
ダイナミック・ケイパビリティを強化させるには、AIをはじめとしたデジタル技術の導入やデータ収集、分析などが必要ですし、組織の再編といった長期的な視点で取り組まなければいけない内容も含まれています。
例えば、持続可能な社会へ貢献するために温室効果ガスの削減を行なうとしても、年単位で取り組まなければ効果を測定するのは難しいと言えます。
SXを行なっている企業の事例
SXへ取り組んでいるケースは、国内でも出てきています。
以下にSXを行なっている企業の事例を紹介します。
| TOYOTA | TOYOTAではサステナビリティ基本方針として、社会、従業員、お客様、株主、環境に対するサステナビリティ関連の取り組みや目標を掲げている また、環境負荷軽減のために工場CO2ゼロチャレンジを掲げ、太陽光発電や風力発電などで自動車の製造時に発生するCO2排出量ゼロを目指している |
|---|---|
| 大林組 | サステナビリティに関する課題や目標設定などは、社内に設置されたサステナビリティ委員会および取締役座談会によって議論され、取締役会で決定される仕組みを構築 さらにサステナビリティへの取り組みは、良質な製品やサービス、環境への配慮、人材、安全衛生、調達先との信頼関係強化、社会貢献といった6つのテーマに分けて進められているのが特徴 |
| NEC | NECの場合は、サステナビリティ経営基本方針を策定し、NEC Wayという4種類の原則に基づいてサステナビリティを推進 また、サステナビリティ経営に含まれているNEC 2030VISIONでは、事業を通じた脱炭素社会の実現、データを活用した生活者目線の行政サービス実現・就労格差解消など、環境・社会・暮らしに関する社会貢献を目指し取り組みを進めている |
企業によってSXの取り組み内容は異なるものの、いずれのケースでも環境負荷軽減に向けた目標や活動などが含まれています。
現時点でどのような取り組みを進めていくべきか悩んでいる場合は、イメージしやすい環境負荷軽減に関する対策や活動を検討してみるのもおすすめです。
例えば、上記事例のTOYOTAで示されているような太陽光発電を活用した脱炭素経営およびCO2削減は、SXやGXにもつながるメリットの大きな取り組みです。
中でも非FIT型太陽光発電の導入は環境価値を保った電力を自由に活用できるため、電気代削減効果だけでなく再エネ電力を必要としている企業への供給および売電収入の確保など、事業の幅を広げやすいと言えます。
SXとは社会と企業のサステナビリティを同期化させる取り組みのこと!
SXとは、社会と企業のサステナビリティを同期化・両立させながら自社の事業を長期的に発展させていく経営・取り組みのことです。また、SXでは環境に関する内容も含まれているので、GX・脱炭素経営を重視している企業にとっても要注目の内容と言えます。
SXへ取り組むために再生可能エネルギーを検討している方や脱炭素経営およびSXにつながる事業を模索している方は、今回の記事を参考にしながら非FIT型太陽光発電を検討してみてはいかがでしょうか。
15,000件以上の実績を持つとくとくファーム0では、製造や小売などさまざまな業種の企業様へ向けて非FIT型太陽光発電の導入サポートをしています。
また、再生可能エネルギーを求めている需要家と非FIT型太陽光発電の導入企業様をつなぐためのサポートまで行なっており、FIT制度以外による売電を検討している方にもおすすめです。
お電話やWebフォームのほか、無料の個別セミナーにてお気軽にご相談ください。
個別セミナーはオンライン開催が可能で、非FIT型太陽光発電とは何か、脱炭素経営の基本からご説明します。